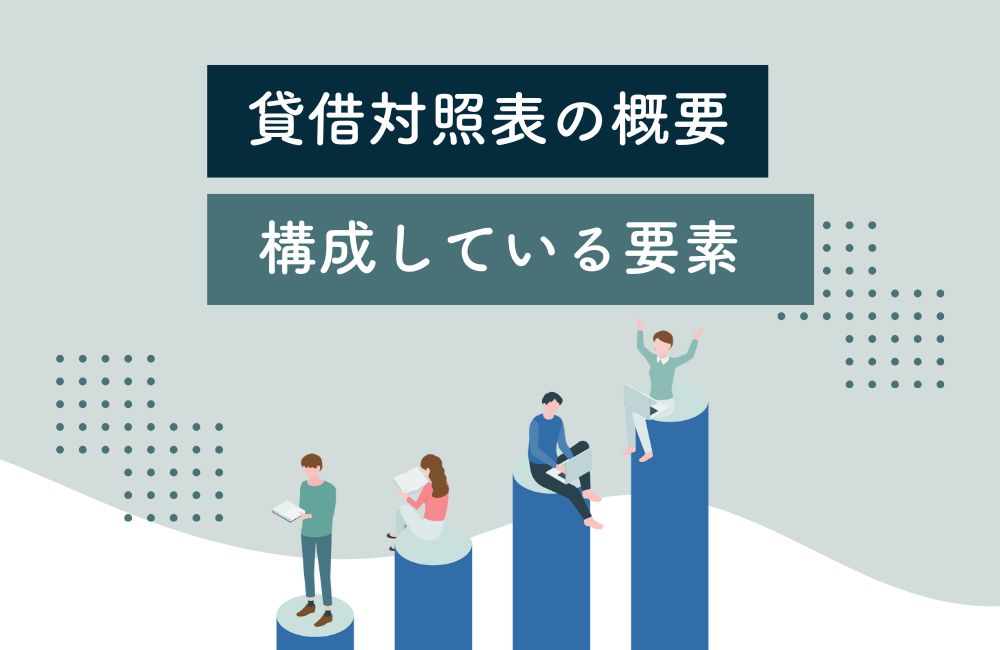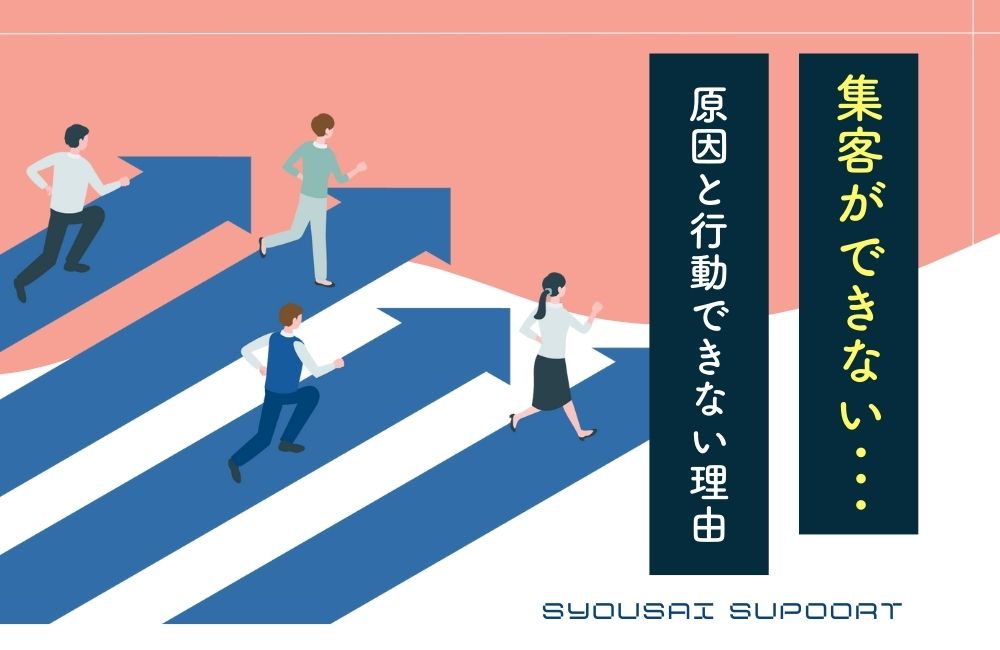経営者は知っておくべき貸借対照表の概要と構成している要素について
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
『毎月試算表を作っていないから、貸借対照表が何なのかよく分からない』
『売上や利益は知りたいから損益計算書は見たことあるけど、貸借対照表はどこを見たら良いか分からない』
『つい忙しくて経理担当にまかせっきりになっている』
貸借対照表のことを知ることで自社の業績を把握できるだけでなく、会社をもっと成長させるための経営改善のヒントが分かるようになります。
そこでこの記事では、貸借対照表の概要と構成している要素について、開業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。
貸借対照表のことを今さら誰にも聞けないという方は、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。
貸借対照表とは?

ある一定時点での会社の財政状態を表した決算書のひとつです。バランスシートとも呼ばれ、資金調達の状況や資金をどのように保有・運用しているのかを客観的に数字で示す資料です。
貸借対照表は、資産の部と負債の部、純資産の部のバランスによって成り立っています。
例えば、経営が悪化してしまうと負債の部が膨らんでしまい、資産の部を超えてしまう場合があります。
これを債務超過といいます。実質的には経営破綻したと同じ状態と意味しており、非常に深刻な状況であるといえることになります。
現預金が残っていたとしても早期に改善すべきものになります。
このように貸借対照表からは会社の財政状態を知ることができ、貸借対照表を見ることで「その会社が健全な状態か」を判断することができます。純資産の部と負債の部を細かくみると、その会社が債務超過の状態であるか否かも把握することができます。
貸借対照表を構成する要素は、主に下記の3つです。
- 資産の部
- 負債の部
- 純資産の部
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
資産の部
資産の部は、貸借対照表の借方(左側)の表記されます。ここには、会社が保有する資産が記載され、その中でも「流動資産」と「固定資産」と「繰延資産」の3つに分類されます。
また、流動資産と固定資産は、正常営業循環基準と一年基準に基づき、区分されます。
「流動資産」と「固定資産」と「繰延資産」の3つから構成されます。
流動資産
短い期間ですぐに現金化することができるものを指します。「仕入→製造→在庫→販売→回収」という営業活動の中で発生する資産や、1年以内に現金化できる資産が流動資産に含まれます。
ただし、流動資産に含まれている場合であっても受取手形や売掛金、商品在庫などは場合によってはすぐに現金化が難しい場合もあります。
流動資産に分類される主な勘定科目は、現金、預金、売掛金、受取手形、前払費用、有価証券、商品、製品、貸倒引当金などがあります。
固定資産
固定資産とは継続的な使用などの目的で会社が長期間保有する資産のことです。固定資産は資産の性質や特徴を元に、「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」の3つに分けられます。
有形固定資産に分類される主な勘定科目は、機械設備や建物、建物付属設備、構築物、土地、車、一括償却資産などがあります。
有形固定資産はさらに「減価償却資産」と「非減価償却資産」とに分類されます。「減価償却資産」が、経年劣化(時間が経過しただけ価値が減少)する固定資産に対して、「非減価償却資産」は、土地や骨董品など時の経過によって価値が落ちない、むしろ将来値上がりする固定資産のことです。
無形固定資産に分類される主な勘定科目は、独占権利や施設権利、特許権、営業権、ソフトウェアなどが分類されます。
投資その他の資産に分類される主な勘定科目は、投資有価証券や長期預金、長期前払費用などがあり、「投資を目的とした固定資産」や「1年を超えて現金化される資産」の他、「その他の固定資産」のことをいいます。
繰延資産
事業用として支払ったもののうち、将来の収益に貢献するという意味合いの資産のことをいいます。そのため、単年度の経費にはしなくても数年かけて費用化することが認められています。具体的には創立費、開業費、株式発行費、社債発行費、開発費などが挙げられます。
負債の部
負債の部は、資産とは反対の貸借対照表の貸方(右側)の上部分に表記されます。ここには、会社が保有する負債(債務)が記載され、「流動負債」と「固定負債」の2つから構成されます。
また、流動負債と固定負債は、資産の部と同様に正常営業循環基準と一年基準に基づき、区分されます。企業が保有する負債(債務)が記載される所で、「流動負債」と「固定負債」の2つから構成されます。流動負債か固定負債かの違いは、正常営業循環基準と一年基準に基づいて区分されます。
流動負債
流動負債とは、会社が抱える負債のうち、支払期限が1年以内に到来するものです。会社が仕入れた材料や商品、製品、サービスの支払対価の他、短期的に支払わなければいけない借入金や未払税金、社会保険料などの預かり分も含まれます。
流動負債に分類される主な勘定科目は、買掛金、支払手形、預り金、前受金、前受収益、未払金、未払費用、短期借入金などがあります。
固定負債
固定負債とは、1年以内に支払い義務が到来しない債務のことです。会社が抱えている債務のうち、借金の返済に時間的な余裕があるものを指します。固定負債には社債などの長期金銭債務や、金融機関から長期的に融資を受けている借入金も含まれています。
固定負債に分類される主な勘定科目は、社債、長期借入金等の長期金銭債務、退職給付引当金等の長期性引当金、その他繰延税金負債などがあります。
流動負債と固定負債とはどういうものか、その具体的な勘定科目ついて解説しましたが、固定負債は、単に会計処理で振り分けられるためのものではありません。会社における経営状況や財務状態を正しく知るためにとても重要な項目です。固定負債は、会社が抱えている負債のうち、返済期間に時間的な余裕がある負債です。
経営は長い目で見なければいけませんが、資金繰りのことを考えればそうも言っていられません。当該事業年度における返済金額もしくは支払義務のある金額がいくらなのかを正確に算出することが重要です。
ぜひ、皆さんご自身でも売上がなかったとしても発生する固定費と上記の支払金額を合わせたときの『損益分岐点売上高』を計算してみてください。毎月その金額を達成できているか、達成するためには、1日何人の来客があって販売単価がいくらを割ってはいけないのかというところまで落とし込みましょう。
策を講じるのはその後です。
純資産の部
貸借対照表の右側の下部分に表示される項目で、株主から出資してもらった事業の元手と事業を始めてから蓄積された利益のうち内部留保されているものが計上されている項目です。
貸借対照表から分析できる指標

貸借対照表から分析できる指標は、主に以下の5点です。
- 流動比率・当座比率
- 固定比率
- 負債比率
- 自己資本比率
- 自己資本利益率
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
流動比率・当座比率
流動比率とは、流動負債に対して流動資産の占める割合を示す指標です。流動比率から、企業の当面の資金繰りや短期的な支払い能力を確認することができます。
流動比率の数値が高いほど、流動負債の支払いができている企業だと判断できます。
また、企業の支払い能力をより正確に判断できる指標として参考になるのが、当座資産から求める「当座比率」です。当座資産とは、換金性が不確実なものを省いた換金性の高い資産を指します。
流動比率(%) = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
当座比率(%) = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100
固定比率
固定比率とは、返済義務のない純資産(自己資本)に対する固定資産の割合を示す指標です。固定比率が低ければ、財務状況がよく、企業経営が長く安定しやすいことが確認できます。
固定比率(%) = 固定資産 ÷ 純資産(自己資本) × 100
負債比率
負債比率とは、返済義務のない純資産(自己資本)に対する負債の割合を示す指標です。負債比率が低いほど財務の安定性を確認できます。
負債比率(%) = 負債 ÷ 純資産(自己資本) × 100
自己資本比率
自己資本比率とは、資産全体に対して返済の必要がない純資産がどれくらいの割合を占めているかを表す指標です。自己資産比率が高いほど、財務上の安定性が高い健全な企業だと判断できます。ただし、業種によって、平均的な自己資本比率にばらつきがあることには留意が必要です。
自己資本比率(%) = 純資産 ÷ 総資産 × 100
自己資本利益率
自己資本利益率とは、自己資本に占める当期純利益の割合を示す指標です。自己資本利益率の数値が高いほど、利益が出ている企業だと判断できます。
自己資本利益率(%) = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
まとめ:貸借対照表から経営改善を試みたい方は、翔彩サポートまで
貸借対照表とは、企業がある時点においてどのくらいの財産や権利、義務などがあるかを示す決算書です。損益計算書、キャッシュ・フロー計算書と並ぶ財務三表のひとつであり、企業の財務状況を把握するために欠かせない書類といえます。
貸借対照表に記載された数値を用いることで、自己資本比率や流動比率、当座比率などがわかり、企業の経営状況を判断し、経営改善に繋げることもできます。
これまで数字への苦手意識から貸借対照表を避けていた方やこれから経営改善をしたいと本気で思う方は、翔彩サポートまでお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。