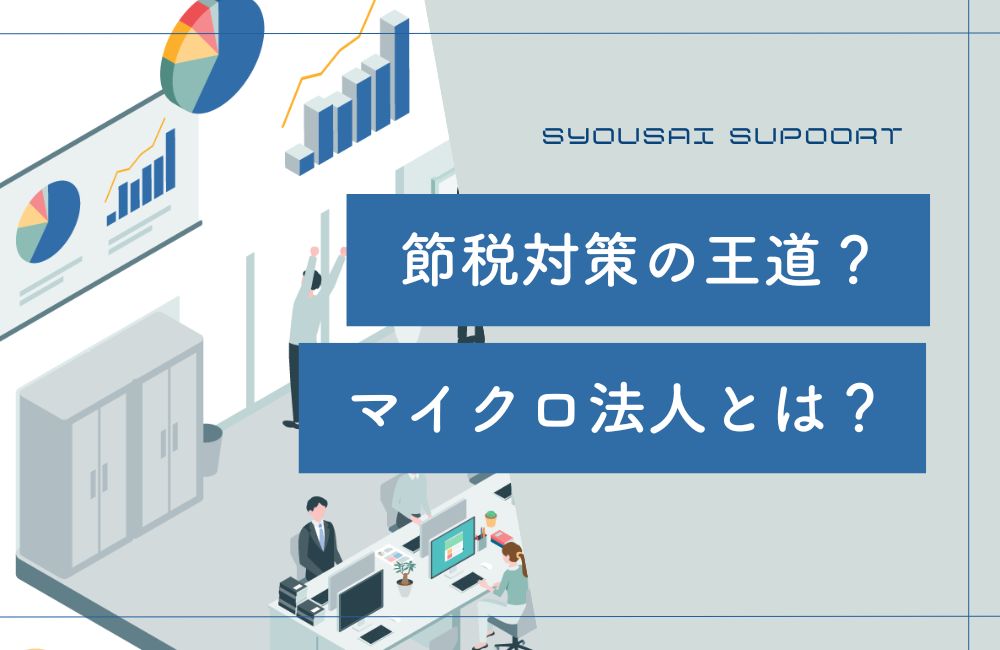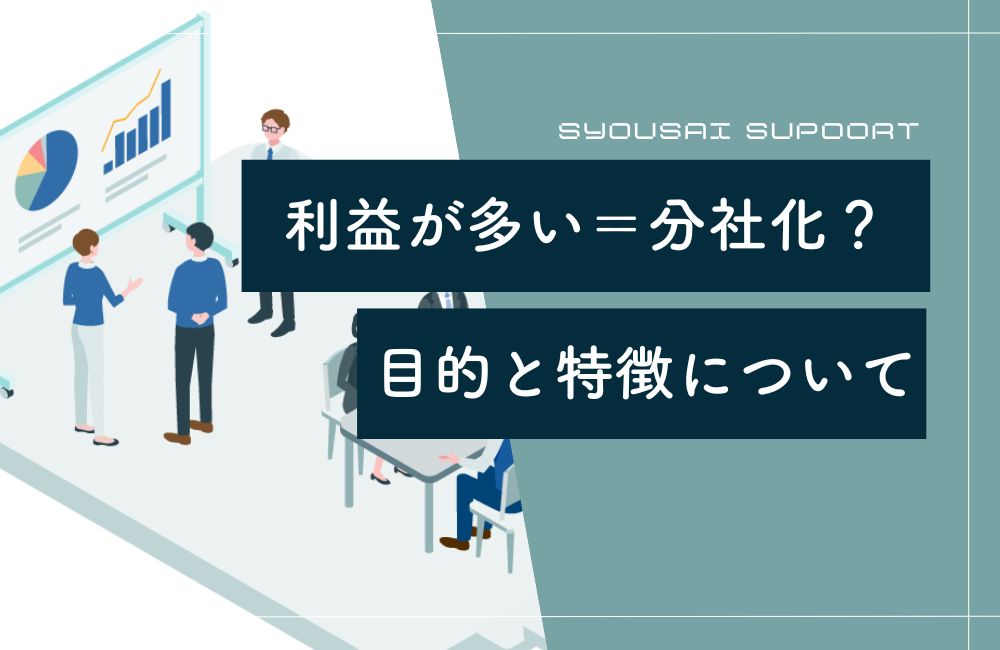節税目的で設立することが多いマイクロ法人とは何か?メリット・デメリットについても詳しく解説
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
『経営者仲間からマイクロ法人のことを聞いたけど、何のことか詳しく知りたい』
『個人事業主の節税対策ならマイクロ法人を勧められたけど、本当にメリットがあるのか知りたい』
『マイクロ法人のメリットだけではなく、デメリットの部分も知りたい』
経営者仲間で利益が順調に伸びている方は、マイクロ法人を設立して節税を図る場合も少なくありません。
ただし、マイクロ法人といっても法人格に変わりはありません。法人を設立することになるため何か目的を持たせる必要があります。
そこでこの記事では、マイクロ法人の概要やメリット・デメリットなどについて、起業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。
これからマイクロ法人を設立しようと考えている方や節税対策を効果的に行いたい方も、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。
マイクロ法人とは何か?

マイクロ法人とは、小規模なビジネスを営むために設立される法人のことです。
従業員数が少なく、創業者が社長兼主要な役職を務め、場合によっては唯一の従業員であることもあります。
マイクロ法人は法的な定義ではなく、「会社法で設立に必要な各種条件が最小のもの」ととらえるとイメージしやすいです。
マイクロ法人は、現在設立できる会社形態のうち、株式会社や合同会社、合名会社で設立することができます。
経営体制がシンプルで、運営が比較的容易であるため、個人事業主がビジネスのスケールアップや税務上のメリットを求めて法人化を選択する際によく利用されます。
会社の性質としては、資産管理や節税のために設立する「プライベートカンパニー」に似ています。
マイクロ法人は合法なのか?

「節税を目的に会社を立ち上げる」と聞くと、なんとなく悪いことをしているような印象を受けますが、「マイクロ法人である」というだけでは違法にはなることはありません。
会社を1人で立ち上げることも、家族だけで事業を行うことも法的に問題はなく、一般的に行われています。
ただし、マイクロ法人に事業実態がない場合には違法な会社設立であると見なされます。
節税を目的にして会社を立ち上げることは違法ではありませんが、事業実態がないのに会社という存在を使って税金を安くしようとすることが、節税ではなく脱税と見なされ違法になります。
いわゆる「ペーパーカンパニー」による脱税と同じです。
マイクロ法人を設立するメリット

マイクロ法人を設立するメリットは、主に以下の4つです。
- 役員報酬など経費にできるものが増える
- 社会保険料を減額できる可能性がある
- 赤字を10年繰り越せる
- 社会的な信頼度が上がる
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
役員報酬など経費にできるものが増える
マイクロ法人を設立すると、役員報酬や生命保険料をはじめとした個人事業主では認められない経費計上が可能となるため、節税の観点からメリットがあり、特に収入が高くなってきた時にマイクロ法人の設立による節税効果も大きくなります。
マイクロ法人の設立で得られる大きなメリットが、節税です。
法人が事業で得た所得には、個人に課される所得税にあたる「法人税」が適用されます。
所得税が累進課税で所得に応じて税率も高くなるのに対し、法人税は所得にかかわらず税率は一律です。
所得が多いほど、個人でいるより法人になった方が税金を安くできます。中小企業であれば、法人税の税率は優遇されています。
社会保険料を減額できる可能性がある
個人事業主とマイクロ法人の二刀流とする場合には、社会保険料が節約できる可能性もあります。
マイクロ法人を設立すると、代表取締役自身も社会保険の加入対象となります。
個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入しますが、マイクロ法人の場合は、健康保険と厚生年金に加入します。
個人事業主が国民健康保険と国民年金に加入する場合、被扶養者分の保険料も納付する必要があります。
しかし、マイクロ法人の健康保険と厚生年金の場合、被保険者分の保険料を納付するだけで、被扶養者が何人いても追加の保険料負担はありません。
赤字を10年繰り越せる
個人事業主で青色申告をした場合、個人事業主でも3年間は赤字の繰り越しができます。
平成30年4月1日以降に開始する事業年度から、法人は赤字(青色欠損金)を最大10年間繰り越すことができます。
赤字を繰り越すことができるため、その期間にマイクロ法人が利益を出したとしても、過去の赤字と相殺することで納税額を減らすことができ、結果的に節税効果が得られます。
赤字が出ることは悪いイメージを持たれるかもしれませんが、その赤字を上手に利用することで節税に繋げることが可能です。
社会的な信用度を上げられる
マイクロ法人の設立では、個人事業主のデメリットである信用度の低さを払拭できるメリットもあります。
大手企業は個人事業主と契約を結ばなかったり、取引金額を抑えたりする場合もありますが、マイクロ法人なら取引できることもあるのがメリットといえます。
会社は個人事業主と比較して社会的な信用力が強いため、マイクロ法人を設立することで事業の信頼性が増します。
信頼性を獲得することは、ビジネスを継続していく上でとても重要な要素です。
マイクロ法人は実体としてフリーランスととくに変わりはないのですが、顧客や取引先からすればやはりきちんとした会社があると信頼できるものなのです。
また、マイクロ法人を設立することで社会的信用度が上がり、金融機関の融資も受けやすくなる可能性があります。
銀行が融資の際にもっとも恐れることは、貸したお金がきちんと返ってこないということです。
個人事業主は信頼性が低いため返済能力を疑われる傾向にあり、なかなか融資を受けられません。
この点、マイクロ法人を設立することで信頼性が増せば、銀行からの評価も上がり、融資を受けられる可能性が高くなるのです。
マイクロ法人を設立するデメリット

マイクロ法人を設立するデメリットは、主に以下の3つです。
- 設立に費用と手間が必要
- 税務申告が複雑になる
- 赤字でも法人住民税の納付が必要
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
設立に費用と手間が必要
設立するのが大企業でもマイクロ法人でも、法的に必要な設立手続きは同じです。
会社を設立するにはとまず定款を作り、株式会社では公証役場での認証を受ける必要があります。そのうえで、法務局に登記申請をしなくてはならず、手続きの手間や費用がかかります。
マイクロ法人を設立するときの費用やランニングコストが発生する点もデメリットです。一般的な株式会社の場合は、設立に220,000〜240,000円程度、合同会社なら75,000円程度必要です。
税務申告が複雑になる
マイクロ法人を設立すると個人事業主のときよりも経理業務や事務手続きに手間がかかります。
個人事業主の場合は、年に1回確定申告をすれば終わりですが、マイクロ法人を設立すると確定申告だけではなく決算申告を行わなければいけません。
貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの書類作成と提出が必要です。
自分でこれらの複雑な書類を準備できない場合は税理士に依頼することになり、そのコストも発生します。
赤字でも法人住民税の納付が必要
法人には、個人事業の場合と異なり事業が赤字でも納めねばならない税金があります。それが法人住民税の均等割の部分です。
マイクロ法人を設立すると、赤字経営のときも法人税を支払わなければいけません。
個人事業主の場合は、赤字なら所得税や住民税は免除されて支払う必要がありませんが、法人化すると赤字でも均等割の法人住民税は納付しなければいけません。
マイクロ法人を設立する注意点

マイクロ法人を設立する注意点は、主に以下の3つです。
- 初期費用は極限まで抑える
- 登記事項は変更がないようにする
- 資本金の金額は1,000万円以下での設立をする
- 融資を受けるなら事業計画書を作成する
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
初期費用は極限まで抑える
マイクロ法人設立に限ったことではありません。
個人事業主やフリーランスとして開業する時にも同様で、初期投資に多額の費用をかけることは禁物です。
開業後すぐに事業が軌道に乗ることはまれであり、数カ月は我慢の生活となる人が多いでしょう。
事務所に地代家賃の高い物件を選んだり、内装や外装などに凝りすぎてしまったりすると、資金が底をついてしまうことも少なくありません。
小規模で事業を行うのがマイクロ法人です。初期費用は極限まで抑えましょう。
登記事項は変更がないようにする
会社の設立は、基本的な事柄を登記することで成立します。登記すべき事項は決められていますが、その内容を変更すると、その度に変更登記の手続きをする必要があります。
変更登記にも3万円の登録免許税が必要となるため、定款作成時からなるべく変更しなくて済むように考えて決める必要があります。
事業の目的として1つのことしか記載していなかった場合、別の事業も始めるには定款の変更と変更の登記が必要ですので、将来的に行いたい事業内容は最初のうちから登記しておくことです。
定款を作成する段階から、司法書士などに相談して決めるとよいでしょう。
ただしそれには報酬の支払いも発生します。
資本金の金額は1,000万円以下での設立をする
マイクロ法人は事業実態がなければペーパーカンパニーと見なされます。
株式会社は1円からの設立が可能であるものの対外的な人からの印象は、事業実態や事業への誠意・熱意などに懸念を抱かれやすいです。金融機関から融資を受けたり、法人口座を開設したりする際に困ることになります。
ただ、資本金は高すぎてもいけません。1,000万円を超えると、事業年度1期目から消費税の課税対象となったり、法人住民税の均等割りが高くなったりして、節税効果は薄まります。
融資を受けるなら事業計画書を作成する
マイクロ法人の設立で事業内容も明確で、そのための融資が必要なら事業計画書をしっかり現実味のあるものを作成する必要があります。
金融機関に融資を依頼する際に事業計画書は必ずといっていいほど提出を求められます。
その内容や経営者本人との面談で審査されます。
計画書の内容は、単に数字を並べたものではなく、法人設立の経緯から実務経験、ビジネスモデルや取引先・顧客の状況、売り上げ見込み、そして経営者の思いを記載することになります。
数字などの根拠を含めて具体的な計画にするのがポイントです。
まとめ:マイクロ法人設立をしたいと思ったら、翔彩サポートまで
マイクロ法人の設立には、節税対策や事業の信頼性向上につながるなどのメリットがある一方、法人格としての煩雑な手続きがあるなどデメリットもあります。
自身の行っているビジネスの状況やこれからの節税対策として得策なのかを総合的に検討して、マイクロ法人の設立を進めるようにしてください。
マイクロ法人を設立することで節税メリットがでるかのシミュレーションをしたい方やマイクロ法人設立を進めるべきか迷っている方は、ぜひ翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。