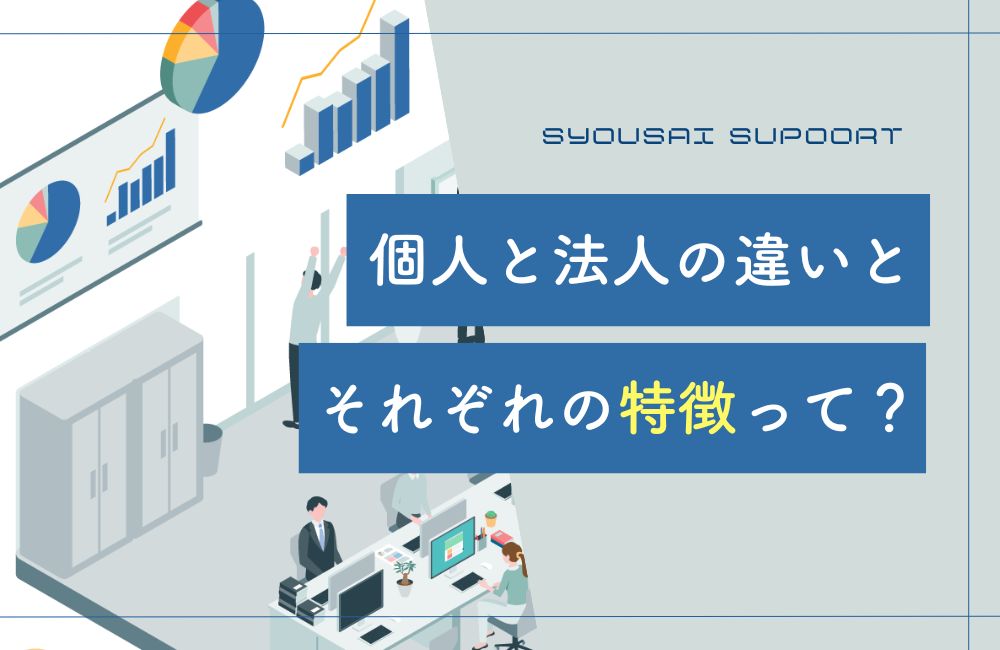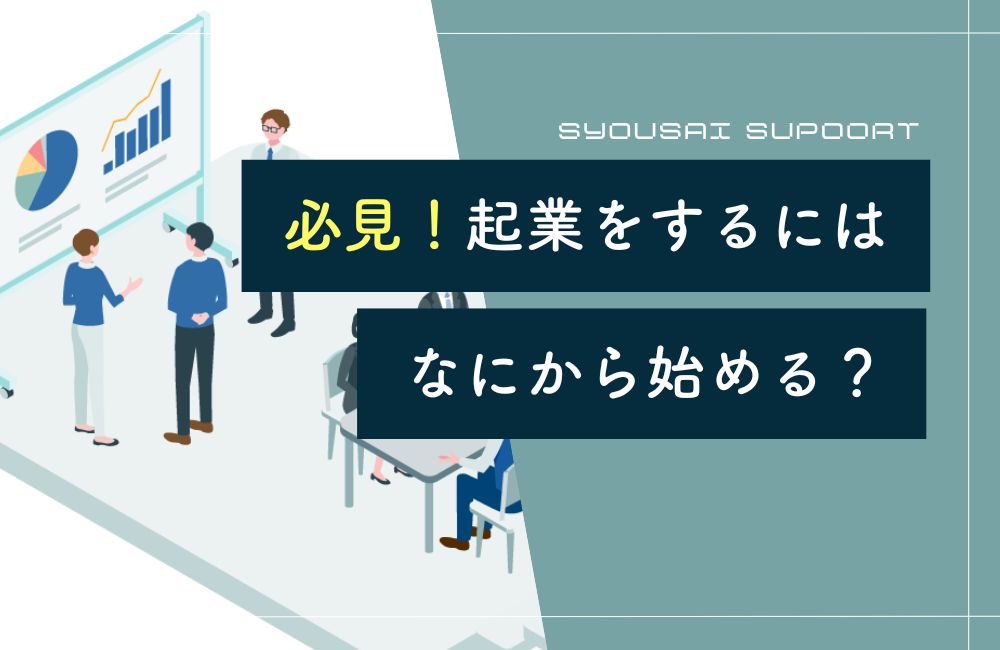個人と法人の違いとそれぞれの特徴について
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
『個人事業と法人どちらが良いですか?』
『個人事業から法人化した方が経営にとってメリットが多いと聞きましたが本当ですか?』
『個人事業と法人の違いがよく分かりません』
起業を考えている方や個人事業を長く続けている方からこのようなご相談をいただきます。
実際に、本当だったら法人で経営した方が手元に資金は残せていたのに、それぞれの良さ悪さを知らなかったまま経営を続けていたというケースもあります。
そこでこの記事では、経営を長く続かせるために自社の経営形態に合っているものがどれかを見極められるために、開業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。
個人事業主から法人化される方以外にも、法人から開業を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。
個人事業主と法人
起業する際に問題となるのが、個人事業主でスタートするか、法人を設立するかではないでしょうか。
同じ事業を行う場合でも、個人事業主と法人では違いがあります。
個人事業主になるために必要なのは、開業届です。開業届の提出で法人用の銀行口座が開設できるほか、青色申告を選択して税制面での優遇を受けることが可能。
法人とは、法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織のこと。これは人間と法人が別の存在として、法律上人格が認められていることを意味します。
会社の設立によって、個人が加入する生命保険に法人名義でも加入できる例があげられます。
法人と聞けば、会社や社団法人をイメージするかもしれません。
しかし、労働組合や神社、私立の学校も手続きで法人格を与えられれば、社会的な存在として法人になります。
個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人の違いは、主に以下の7点です。
- 事業開始までの手続き
- 事業開始までにかかる費用
- 掛かってくる税金の種類
- 社会保険負担の有無
- 経費の範囲
- 社会的信頼度
- 赤字の繰越
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
事業開始までの手続き
個人事業主は、開業届や青色申告を希望する人は「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出しますが、法人では法務局での法人登記が必要です。また、会社設立に必要な書類や会社の実印の用意が必須になります。
事業開始までにかかる費用
個人事業主として開業する場合は、設立費用などは一切かかりません。法人として起業する場合は、株式会社か合同会社かによって異なります。株式会社の場合は諸々の費用を含めて約20〜25万円、合同会社の場合は約5〜10万円の金額が必要です。法人の実印を作成する場合は約1〜2万円、書類の取得費用等で約3,000〜5,000円の費用も必要となります。
掛かってくる税金の種類
個人事業主にかかる税金は「所得税」「住民税」「消費税」「事業税」の4種類です。このうち、所得税と住民税は必ず納める必要がある税金です。消費税と事業税は、要件によって加算される税金となります。
法人にかかる基本的な税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・消費税の5種類です。個人事業主に比べて法人は経費として計上できる範囲が広く、所得によっては法人の方が節税額は大きくなります。
社会保険負担の有無
個人事業主は、従業員が5人未満であれば社会保険への加入義務はありませんが、2022年10月以降は従業員が5人以上の場合は加入義務が生じます。また、従業員が5人未満でも従業員の過半数の同意があれば加入することもできます。個人事業主が加入する社会保険は国民健康保険と国民年金で、労使折半ではないため個人の負担が大きくなります。
一方、法人は役員報酬が0円である場合を除き、自分ひとりだけの会社であっても社会保険への加入義務が生じます。社会保険に加入すると、法人は従業員の社会保険料の半分を負担しなければならないため、金銭的な負担が増えます。
経費の範囲
個人事業主が経費として計上できる範囲は「その事業に必要な費用」のすべてです。 例えば、仕入の費用や事務所の家賃、取材のための交通費等は経費に含まれます。 逆に、事業に関係のない費用はすべて経費にはできないので注意が必要です。
法人になると、個人事業主よりも経費として認められる項目が多く、節税メリットが大きいという特徴があります。たとえば、法人化することで、経営者本人や家族従業員への給与、生命保険料、社宅、出張費や休日出勤の手当などが経費として認められるようになります。また、賃貸している自宅や自宅の購入費も経費として計上することも可能です。
ただし、経費にできる金額については、年間を通しての上限はありませんが、事業の内容や規模など総合的に判断して妥当な範囲内であることが必要です。また、プライベートに使用した費用など、経費に当たらない支出を計上しないよう注意が必要です。確定申告の過少申告や無申告ではペナルティが課せられ、偽装などが発覚したときは重加算税が課
社会的信頼度
一般的に、法人の方が個人事業主よりも社会的信頼度が高いと考えられています。法人格が法律で認められており、会社法などの法律に基づいて厳格に運営されるためです。
法人化すると、取引先の開拓や銀行の融資審査、社員の採用など、さまざまな面で有利に働く可能性があります。たとえば、法人名義で銀行口座や融資を受けられるようになったり、第三者の保証人を用意することなく事務所を借りられたりします。また、金融機関からは「事業のための人格であること」「基本概要が登記により公示されていること」「明確な経理処理が期待できること」などが評価される傾向にあります。
赤字の繰越
青色申告をしている個人事業主は、その年に生じた損失(赤字)を翌年以後3年間繰り越せます。
青色申告の場合、欠損金(赤字)が生じた年(事業年度)の翌年度以降、欠損金を繰り越すことができます。
繰り越すことができる期間は、10年です。
※平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
個人事業主のメリット

個人事業主のメリットは、主に以下の3点です。
- 手続きが簡単で事業を始めやすい
- 税務の申告が簡単
- 所得によっては税金がお得な場合もある
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
手続きが簡単で事業を始めやすい
個人事業は法人設立に比べて開業手続きが簡単です。税務署や都道府県税事務所、市町村に開業届を提出するだけですぐに開業できます。費用もかかりません。
税務の申告が簡単
個人事業では毎年、確定申告を行います。白色申告より手間がかかる青色申告でも、経理ソフトを使って記帳し、確定申告をしている人は多いです。簿記の知識がない初心者でも使い勝手のよいソフトが販売されています。
法人では法人税の申告書を作成しますが、税理士に依頼せずに作成するには相当の知識が必要になります。個人事業より作成の手間もかかりますので、税理士に申告書の作成を依頼する法人は多いです。
個人事業でも税理士に依頼する人は少なくありませんが、法人税の申告に比べて税理士の依頼費用は安いことが多いようです。
所得によっては税金がお得な場合もある
個人事業主の場合は所得税が課税され、法人は法人税が課税されます。税制上、利益が少ない間は、法人税よりも所得税のほうが少なくなります。
そのため、事業が大きくなるまでは個人事業主として所得税で申告、利益が増えた段階で法人化して法人税に切り替える戦略も選択肢のひとつに考えられるかもしれません。
個人事業主のデメリット

個人事業主のデメリットは、主に以下の3点です。
- 確定申告が必要
- 社会保険や雇用保険に入れない
- 個人としての社会的信用度が低い
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
確定申告が必要
個人事業主は自分で確定申告をする必要があります。
確定申告は手間がかかるので、デメリットという見方もできるでしょう。
確定申告は自分の所得税を計算して申告するもので、納税するために必ず行なわなければなりません。
もし確定申告をしなければ、脱税と見なされ、犯罪として扱われる可能性もあります。
働き方の自由度が高い分、公的な手続きはきちんとしなければ、大きなトラブルにつながりかねません。
社会保険や雇用保険に入れない
個人事業主は社会保険や雇用保険に加入できません。
保険による保障が受けられないのはデメリットと言えます。
ここでの社会保険とは、会社に雇用されることで受けられる「厚生年金」「健康保険」のことです。
さらに、雇用されていないので「雇用保険」も受けられません。
一応、個人事業主も「国民年金」「国民健康保険」への加入は可能です。
しかし、将来の年金受給額などに大きな差が出ます。
個人としての社会的信用度が低い
個人事業主は、個人としての社会的信用度が低いこともデメリットです。
収入が不安定で、会社に所属せず後ろ盾がないことから、社会的信用が低く見られてしまいます。
会社員は、会社に就職すれば自然に社会的信用を得られるものです。
しかし、個人事業主はそうはいきません。
社会的信用が低いと、住宅ローンやクレジットカードの申請に通りにくくなります。
法人のメリット

法人のメリットは、主に以下の5点です。
- 一定以上の所得があると税負担が軽くなる
- 取引先や金融機関からの信用が高くなる
- 法人の経費負担で退職金の準備ができる
- 社会保険に加入できる
- 決算期を都合に合わせて決定できる
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
一定以上の所得があると税負担が軽くなる
法人化すると、一定以上の所得がある個人事業主よりも税負担が軽くなるのがメリットの1つです。個人事業主と法人では課せられる税負担の種類が違います。
上述したように、個人事業主には所得税、法人には法人税が課せられます。所得税は累進課税制度が適用されているため、所得が増えれば増えるほど税の負担割合が増加していきます。加えて個人事業税がかかる場合はそれも考慮が必要です。
その点で、法人税には累進課税制度は適用されていないため、税率はほぼ一定になります。そのため、所得が一定以上になった場合は、法人に課せられる法人税の方が税負担が軽くなります。
取引先や金融機関からの信用が高くなる
法人であれば、取引先や金融機関からの信用が高くなるメリットがあります。信用度が高ければ、事業用の交渉が事業者に有利になり、売り上げ増に寄与することになります。
また、事業の発展のための資金を金融機関から融通してもらう際に、個人事業主よりも有利です。そのため、法人化して信用度を上げることは、事業の発展につながります。
法人の経費負担で退職金の準備ができる
法人化すると、経費負担で退職金の準備ができるのもメリットの1つです。退職金は節税効果とともに、社員募集などにも効果が見込めます。
また、個人に対しては法人の経費負担として、社長は会社から給料をもらっているという手続きになります。
そのため、この点においても節税の効果があるのです。法人化は経費負担として退職金の準備ができて節税をすることができるメリットがあります。
一方で、社長個人の給料にも所得税・住民税はかかります。法人と個人のトータルで考えることも必要です。
社会保険に加入できる
法人化のメリットは社会保険に加入することも挙げられます。社会保険は個人事業主の時に支払っていた国民健康保険よりも高額です。
しかし、社会保険に含まれる厚生年金は、国民年金に比べて老後に受け取れる金額が高くなるので老後の備えが手厚いです。
また、社会保険に加入できる福利厚生があれば、社会保険に加入したい優秀な人材が多く集まることが期待されます。多くの優秀な人材を抱えることで、会社の発展に大きく寄与することになります。
決算期を都合に合わせて決定できる
法人化すると決算期を会社の都合に合わせて決定できるのもメリットです。個人事業主は12月31日が締め日であり、納税は3月15日までに行わなければいけません。
しかし、法人の場合は事業の繁忙期を避けて決算期を設定できるので、事務手続きが本業の妨げになることはありません。
納税のタイミングが繁忙期と重なる事業の場合は、決算期を自由に設定できるメリットが大きいです。
法人のデメリット

法人のデメリットは、主に以下の4点です。
- 会社設立費用がかかる
- 社会保険に加入する義務が生じる
- 税理士費用がかかる
- 赤字でも税金の支払義務が生じる
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
会社設立費用がかかる
会社設立のためには定款認証手数料(3万円~)、登記の際に登録免許税(15万円~)などの費用がかかり、手続を専門家に依頼する場合は報酬としてさらに5万円程度かかる場合があります。さらに、資本金も必要となるため、会社設立は決して気軽に行えるものではありません。
逆に、これだけの費用をかけているからこそ社会的信用が増すというメリットを享受できるのです。
なお、資本金は1円からでも会社設立は可能です。ただし、設立費用や運転資金が必要になることや、取引先や金融機関からの信用を考慮すると現実的ではありません。適切な額になるよう注意しましょう。
社会保険に加入する義務が生じる
法人化した場合、事業に従事する者が1名のみであっても社会保険に加入しなければなりません。つまり、社長1名しかいないとしても社会保険に加入する義務があります。
健康保険料と厚生年金保険料は、会社が従業員の保険料の半分を支払う必要があるため、個人事業主よりも負担が増えてしまうことは否めません。
とはいえ、社会保険に加入することで人材確保のメリットにもつながるので表裏一体といえます。
税理士費用がかかる
個人事業主の場合、事業の規模や取引数次第では自分で確定申告が十分に可能であり、現に自分で確定申告している個人事業主も多いです。
しかし、法人化すると、作成すべき書類が増え、計算も複雑になるため税理士へ依頼する必要性が高まります。法人化し、事業が拡大した場合は税理士費用の負担は免れられないと考えておくべきでしょう。
赤字でも税金の支払義務が生じる
個人事業主の場合、赤字であれば課税所得が存在しないことになりますので所得税は不要ですし、住民税も課税されません。
しかし、法人化すると、たとえ赤字であっても法人住民税の支払が必要です。法人住民税は、資本金や従業員数に応じて算出される均等割と法人税に応じて算出される法人税制があります。
まとめ:自社に合った経営形態を知りたいなら経営全てをサポートできる翔彩サポートまで
個人事業でも法人でも、それぞれのメリットデメリットが存在します。自社の経営にどちらが合うかは特徴を把握した上で判断するようにしましょう。
上記以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。