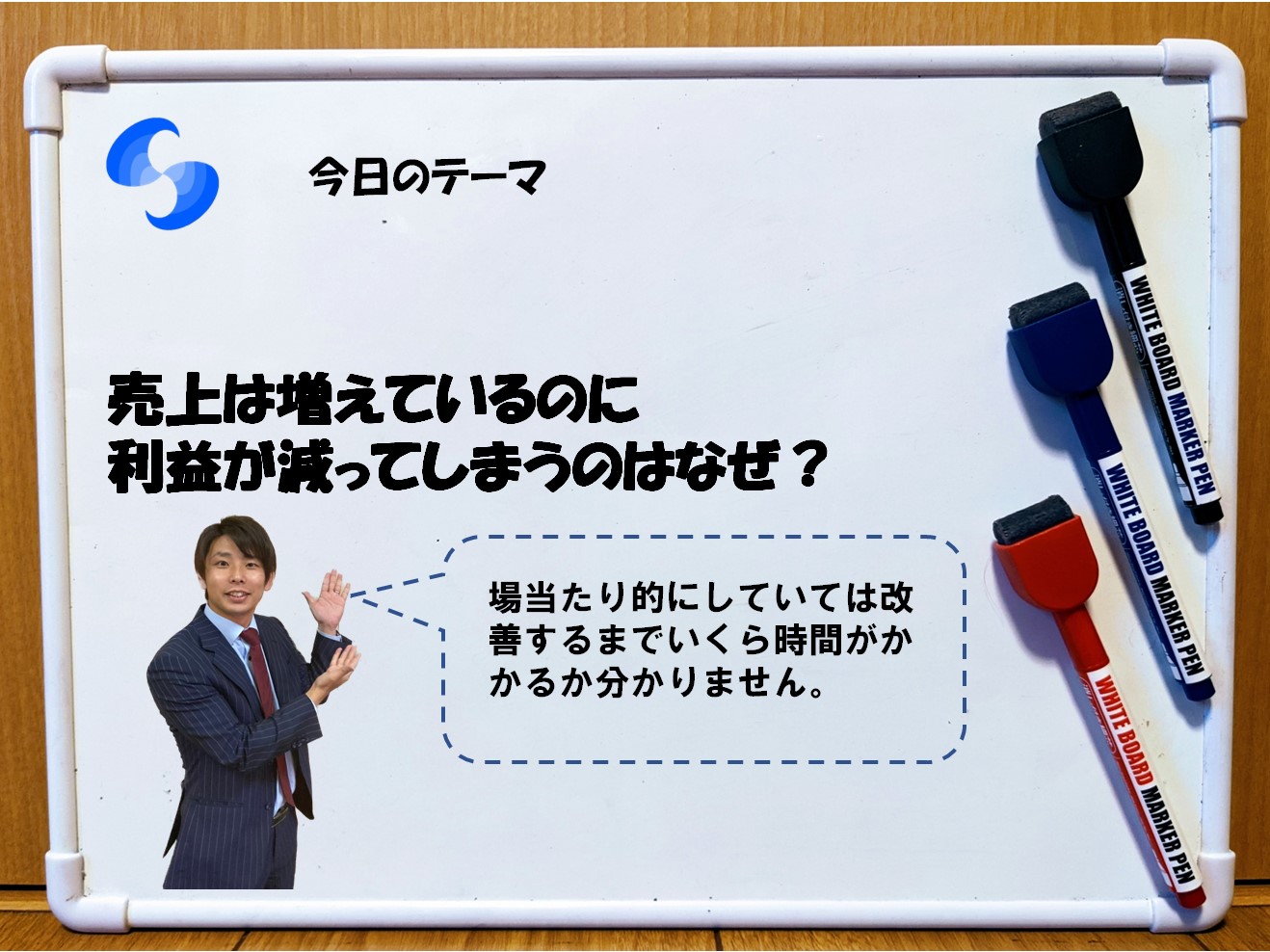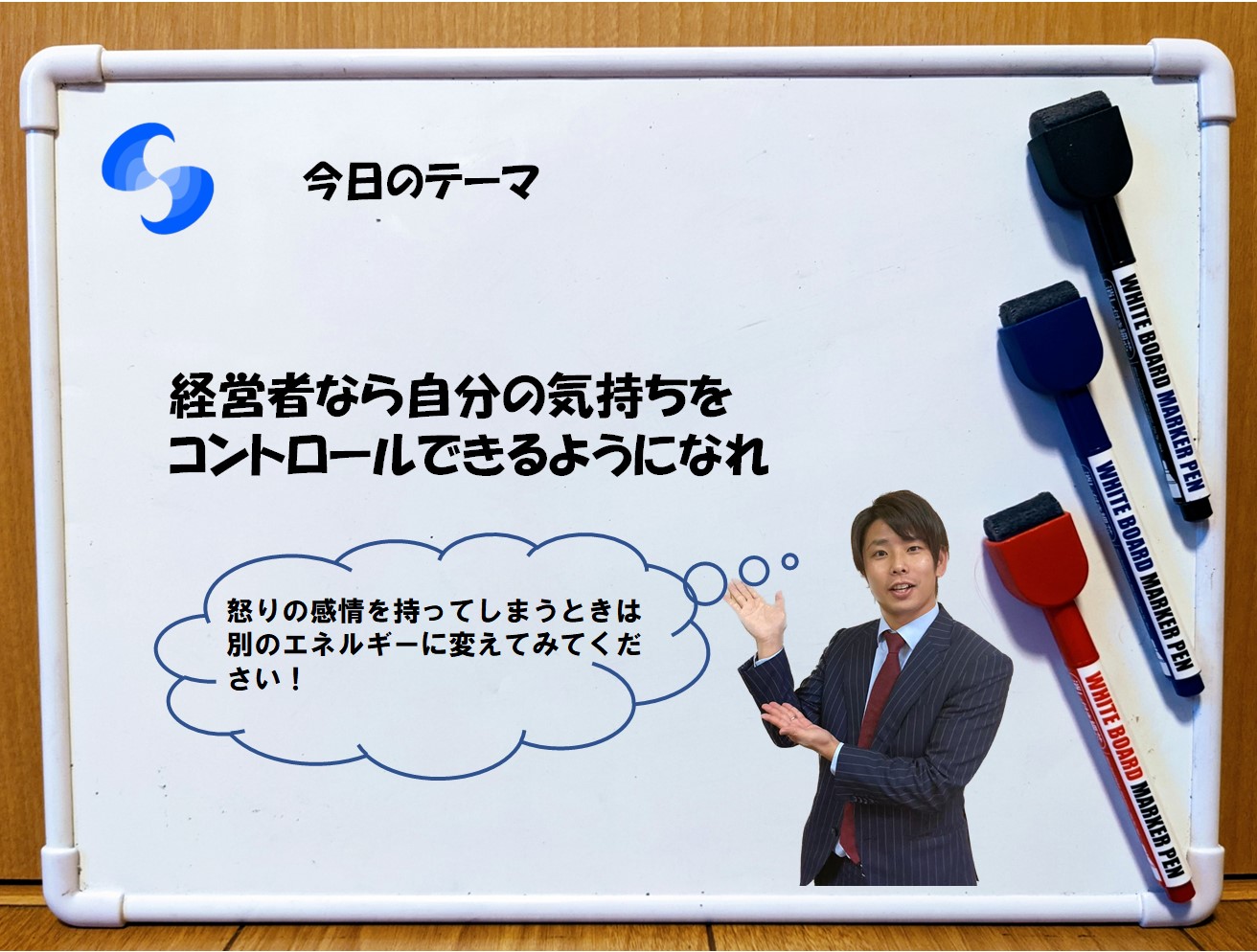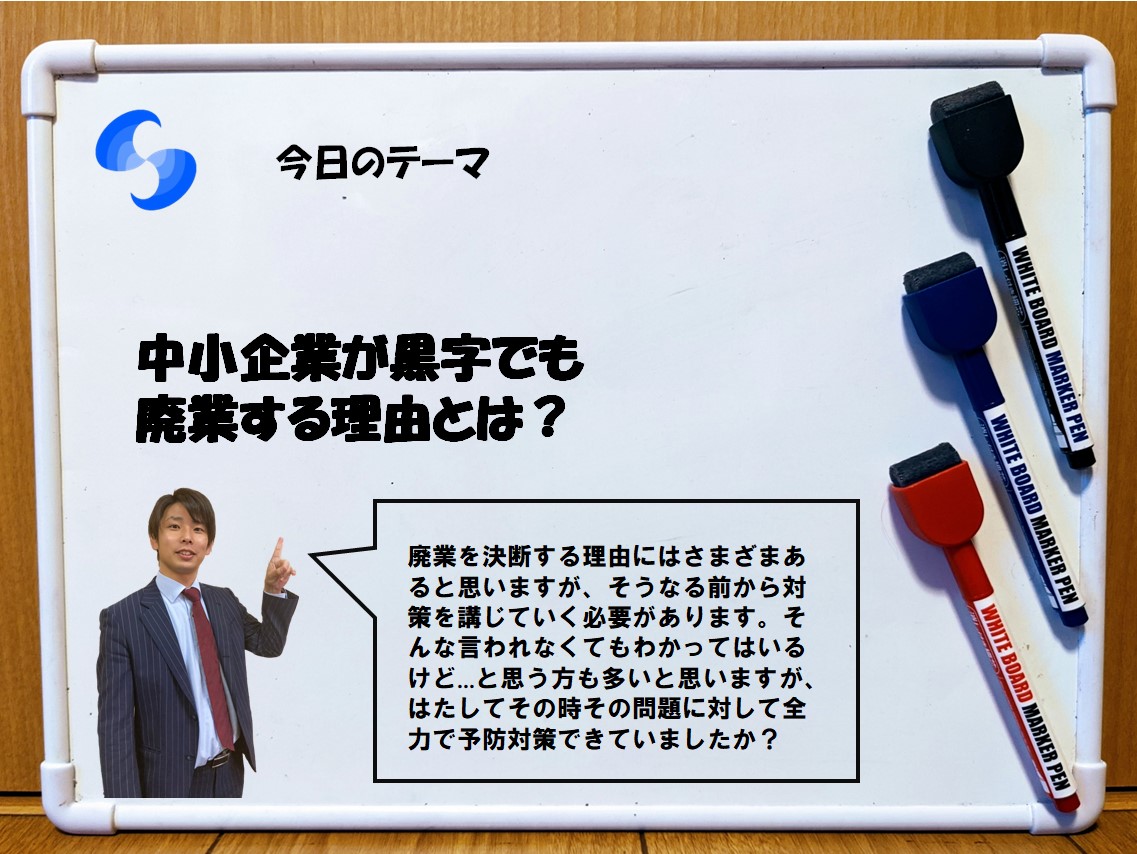売上は増えているのに利益が減ってしまうのはなぜ?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「売上は増えているのに利益が減ってしまう原因」について解説します。
事業の売上が増えているのに、利益が下がってきたときに疑問に思う経営者もいることでしょう。
そこで、売上至上主義の経営者ならより売上を伸ばすための取り組みを考えると思いますが、一度踏みとどまってください。どこかのタイミングで経営者自身、利益体質の方が重要だと気付く時があると思いますが、売上至上主義をまっしぐらの中では気づくことが難しいでしょう。
ハッキリと断言しますが、経営において大切なのは売上高ではなく利益額です。
どれだけ売上を伸ばしても利益が残らなければ生き残れません。
利益と一言で言っても経営における利益にはいくつか種類があります。
経営における利益とは?
「売上高が上がったのに、利益が下がってしまった」とお考えの経営者であれば、まずは次の利益額に着目してみましょう。
売上総利益(粗利益)
売上総利益は、売上からその売上を作るためにかかった経費(変動費)を引いた利益のことをいいます。
歯科医院であれば、材料代や技工代などがありますが、これは業種や自社製造している業務形態によって違いがありますので、ご自身の経営に落とし込んでみてください。
このように、売上高によって変動する費用のことを、「変動費」といいます。
営業利益
営業利益は、売上総利益から製造とは関係のない販売費や管理費といった費用を引いたものです。
販売費とは、ホームページやチラシの代金であったり、営業担当者や販売スタッフの人件費です。
管理費とは、経営幹部や事務スタッフの人件費であったり、オフィスの家賃であったりします。
これらの費用は、売上高の増減によって変動しない費用ですので、「固定費」といいます。
しかし、売上高によって変動しない費用なのに、「売上高が上がったら、それ以上に固定費が増えてしまい、利益が減った」という場合もあります。
営業利益とは、本業となる事業活動で得られた利益のことです。
それに対して経常利益とは、本業以外での利益や損失を増減させた利益のことです。お店を経営していて、たまたま空いている土地を駐車場として貸していたら、そのお家賃が毎月入ってきます。その利益が営業外での収益となり、経常利益に加算されます。
本業以外の収入や損失がない場合は、「営業利益=経常利益」となります。
利益額も大切だが、利益率はどうか?
売上高が増えたのにもかかわらず、利益が減ったということは、原因は利益率が悪くなったからです。
例えば、10億円の売上高で利益率が10%であれば、利益は1億円です。売上高が2倍の20億円に増えて、利益率が3%に減ってしまったら、利益は6,000万円に減ってしまいます。
せっかく努力して売上高を増やしても、利益率が下がってしまったら、残る利益が反対に減ってしまうことを意味します。努力した営業担当も報われません。そのときに社長は、「売上高を増やすだけではいけない」と気が付くのです。
利益率の高さは、生産性や付加価値の高さとも言えます。事業活動の生産性が下がったり、市場が求める付加価値に対して自社の付加価値が高まっていない場合、つまり薄利多売をした場合には、売上高が上がっても利益が下がってしまいます。
営業担当に目標値を示す場合は、必ず、「売上高」以外に、「利益率」や「利益」など、2種類以上設定してください。
利益率が低下する要因を考える
変動費率の増加
1つ目の原因は、変動費率の増加です。
変動費率とは、売上高に対する変動費の割合です。変動費率が増加する場合は、仕入れ原価が高くなってしまった場合と販売価格が下がってしまった場合です。
例えば今まで1個当たり10,000円で仕入れていて、販売価格15,000円で売っていたものがあったとします。粗利益は5,000円です。
仕入れが12,000円に上昇してしまい、販売価格が15,000円のままであれば、粗利益が3,000円に減ってしまいます。
また、仕入れが1個当たり10,000円のままであったとしても、販売価格が13,000円に下げてしまったら、これも粗利益が3,000円に減ってしまっています。
仮に営業担当がいる会社では、経営者からの売上至上主義の圧力によって「たくさん売るためには、値下げするしかない」という現場の判断で、安売りをして売上を確保しているケースもあるでしょう。
値下げしているため、売上高は高くなって当然です。
ところが、利益の総額が安売り以前よりも下がってしまうだけではなく、値下げは自身の商品サービス価値を下げることにも繋がりますので、簡単に値下げはしないことをおススメします。
固定費の増加
利益率が下がる原因として、固定費の増大があります。
固定費の増大によって下がる利益は、販管費をも含めた「営業利益」です。
売上高を増やすためには、PR活動が大事になります。売上高は、自社製品がどれだけ認知されたかの成績でもあります。
そこで、営業担当はムリなPR活動で費用を使ってしまい、固定費が増大してしまって、利益率が低下してしまうことになります。
利益率が下がっている商品やサービスを見出せ
商品やサービスの種類が多い企業では、売上高が上がっていても利益が下がっているものを発見することが、困難な場合がありますが、最初は過去の実績を比較しましょう。
すると、利益を下げている原因を発見できると思います。
商品点数が多い場合は、商品を個別に調べていたら手間ですので、仕入れ先やカテゴリ毎に売上高と利益の推移を調べると、どの商品群が利益を下げる原因になっているのかがわかります。
売上高を増加させながら利益率も高めるのは可能か?
そんな都合の良いことは無理だと思われた方も多いと思いますが、可能です。
しかし、簡単なことではありません。根気のいることばかりです。
経営者としてそれは覚悟してください。
- 営業担当者に売上高だけでなく利益も合わせて確保するように指示
- 利益率低下の原因である割引を無くす
- 利益率の高い商品の開発
- ホームページの活用
売上高の増大と利益率の上昇を両立させられる理由は、SEO対策を行うことにより今まで認知されていなかった市場に対して訴求できるようになるからです。
そうすることで、自社の商品サービスに価値を感じていただくことができ、付加価値の高いサービスを求めるお客様を集客できるようになります。
どの会社でも必ずリソースに自社ならではの強みがあるはずです。
強みがあるからこそ今日まで厳しい市場の中で生き残っていると思います。
もし、ホームページから集客ができていないのであれば、強みが訴求できていないか、強みが間違っているかのどちらかです。一度、ご相談いただくことをおススメします。
まとめ
利益率や利益額を改善するためには数値管理が絶対条件です。
色んな取り組みを場当たり的にしていては改善するまでいくら時間がかかるか分かりません。
売上改善はもちろんのこと、利益を改善したいと思う経営者は、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。