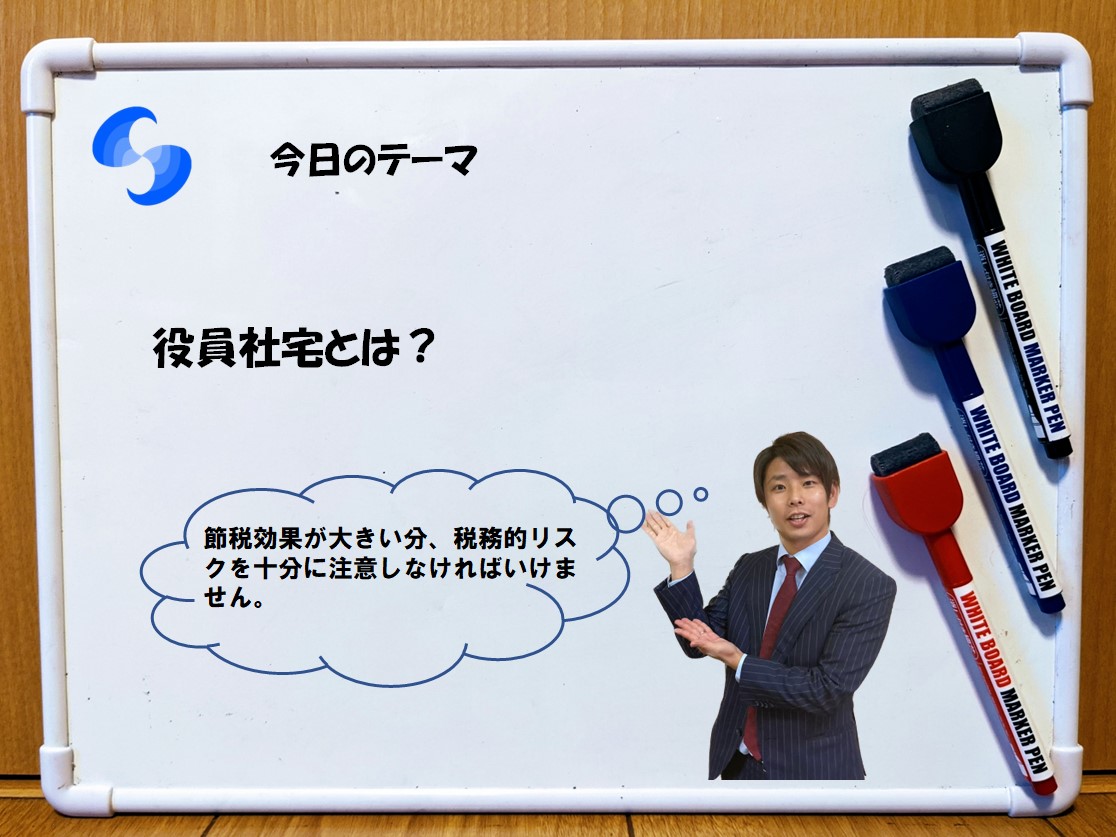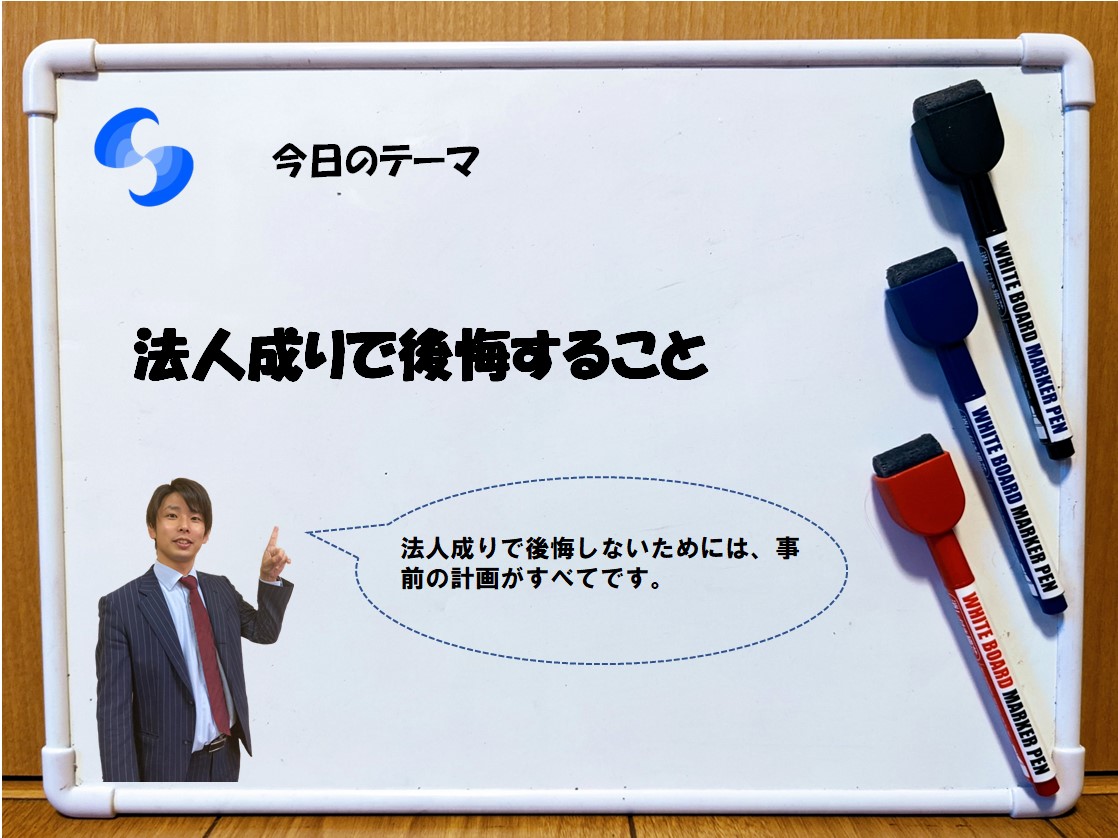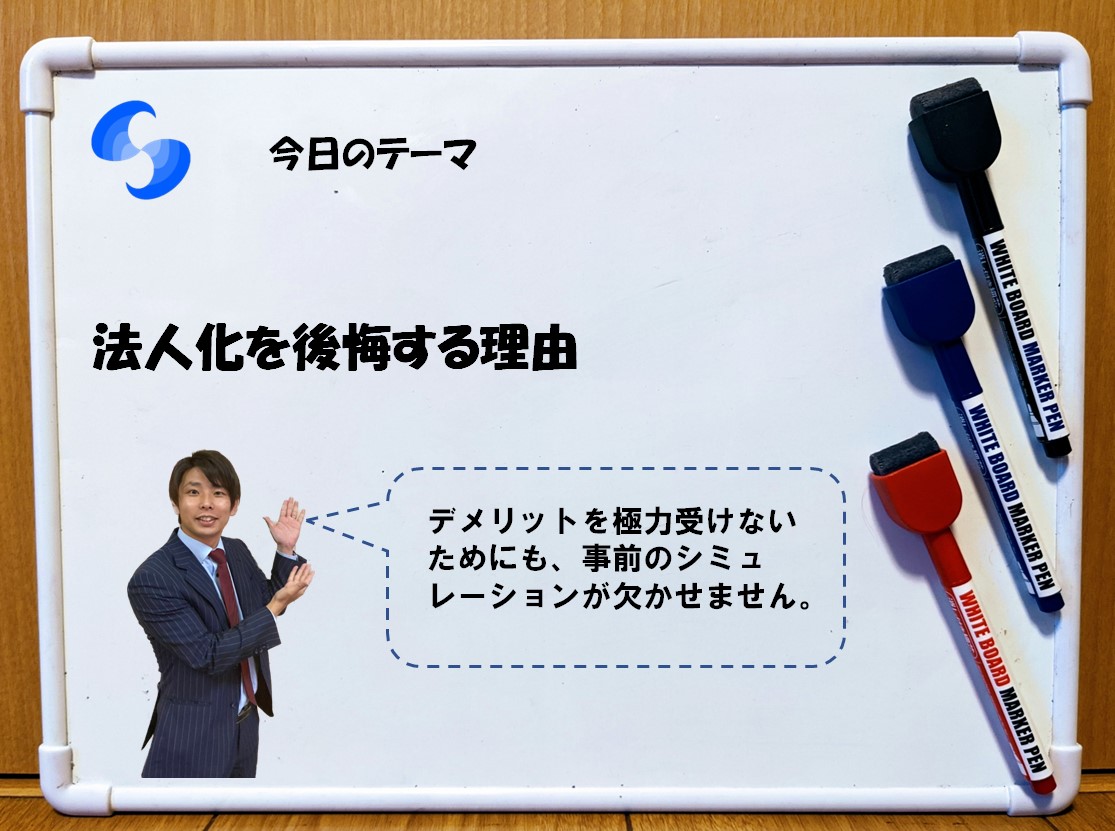役員社宅とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「役員社宅」について解説します。
「役員社宅」は、社宅の中でも特に役員が利用する社宅制度です。
会社名義で借りている賃貸物件に役員が住むと、会社側の家賃負担分は経費として計上できる=全額損金として算入できるため、節税効果が大きいのが特徴です。
役員社宅は節税になる
会社名義で借りている賃貸物件に役員が住む場合、会社側の家賃負担分は経費として計上して、その全額を損金として算入できます。
賃料30万円のマンションを借り上げ社宅として会社が契約し、半額の15万円を会社負担とした場合は、15万円✖12カ月=180万円/年が損金計上となります。
会社の利益が180万円減ることになり、その分法人税が減るので節税できることになります。
また、役員社宅にはその他にも社会保険料の負担を減らせたり、役員の可処分所得額が増えたりするなどのメリットもあります。
経営者の中には、あえて自分の住む住宅を購入せず、会社名義の賃貸に住んでいるという人もいるほどです。
ただし、どんな住宅でも役員社宅として認められるわけではありません。
どんなに豪華な住宅の高額な家賃でも際限なく経費扱いできるわけでもありません。
役員社宅として認められる要件
賃貸物件が「役員社宅」と認められるにはどんな要件を満たしていればいいのでしょうか?
それは以下の3点です。
賃貸契約は法人名義で結ぶ
特に重要なポイントとなるのは「法人名義で契約する」ということです。
役員個人の名義で契約していると、会社側の家賃負担分は「住宅手当」になるため、課税されてしまいます。
役員社宅制度を設けるのは節税のためという意味合いが大きいのに、それでは意味がなくなってしまうでしょう。
家賃の一部を役員本人が自己負担する
役員社宅の家賃が経費扱いできるからといって、全額を会社側負担にすることはできません。家賃の一部は役員本人が自己負担する必要があります。
その負担額の割合も、国税庁によって一定基準が定められています。
その基準以上、あるいは家賃全額を会社負担にした場合、「実質的には役員報酬として支払っているのと同じ(=現物給与)」とみなされます。
となると、家賃の会社負担分は「経費」ではなく「給与」扱いになり、税務調査で課税されてしまう恐れがあるのです。
大家への家賃の支払いは、名義人である法人が直接行う
家賃の一部を会社の経費扱いにするのであれば、家賃の支払いは当然ながら会社側から行わなければなりません。
役員個人が支払ってしまうと、税務調査で否認されて経費計上できない恐れがあります。
そうならないよう、
・家賃の支払いは会社から行なう
・役員の自己負担分は、会社が役員報酬から天引きする
という形にしましょう。
役員社宅のメリット
会社持ちの家賃分が全額損金扱いにできる
員社宅の家賃は会社側が支払い、その一部を社宅使用料として役員が負担しますが、会社側の負担分についてはその全額が「地代家賃」として経費=損金扱いにできます。
つまり、その分の利益が減じたことになるので、法人税も下がり、節税になるのです。
役員の可処分所得額が増える
毎月60万円の役員報酬を得ている役員が、家賃20万円のマンションに住んでいるとしましょう。
もし役員本人名義でマンションを借りていれば、通常は家賃20万円全額が個人の負担になるだけです。
が、家賃のうち10万円を会社が負担してくれるとなれば、役員の家賃負担は10万円ですみ、結果として役員報酬が10万円増えたのと同じことになります。
さらに、役員報酬から家賃負担分が天引きされるため、社会保険料や住民税、所得税も軽減され、可処分所得が増えるというわけです。
役員社宅のデメリット
敷金など初期費用が大きい
賃貸物件を契約する際には、敷金礼金などの初期費用も発生するため、これらが会社の業務や資金繰りを圧迫する恐れがあります。
たとえば、
・敷金礼金
・仲介手数料
・書類の作成費用
などはかならず必要になるでしょう。
また、役員社宅制度を明文化したり、物件選びをしたりするために、人的リソースも割かねばなりません。
もし自社で社宅用の物件を購入する場合は、さらに桁違いの費用が発生します。
役員社宅で節税する際のポイント
役員の家賃負担分を50%にすると節税効果が薄くなる可能性が高い
役員社宅制度を取り入れている企業では、家賃のうち役員の負担分=賃貸料相当額を「50%」と設定しているところも多いようです。
これは、「2. 役員社宅の家賃の決め方」 で紹介した計算方法が難しかったり面倒である場合は、「50%」と設定すれば税務署に経費として認めてもらえるためです。
ただし、実際に前出の方法で計算すれば、役員の負担分は50%よりも少なくできる場合が多く、10~20%に抑えられる場合もあるのです。
賃貸料相当額を家賃の50%と設定するのは簡単ですが、節税効果としては小さくなってしまう恐れが大きいので、面倒でもぜひきちんと計算してください。
役員の家賃負担を無償や少額にすると給与扱い=課税対象になる
役員の家賃負担が少ないほど節税効果が大きいことはわかりましたが、かといって、あまりに負担を少なくしすぎたり、無償=全額会社負担にしてしまうのは逆効果です。
税務署が会社の家賃負担を損金として認めてくれるのは、あくまで「賃貸料相当額」の計算にのっとった場合に限られます。
それを超えると、家賃の一部負担ではなく、「実質的には役員報酬として支払っているのと同じ(=現物給与)」とみなされ、課税されてしまうのです。
これでは節税効果は得られないということも知っておいてください。
まとめ
役員の社宅は節税効果が大きい分、税務的リスクを十分に注意しなければいけません。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。