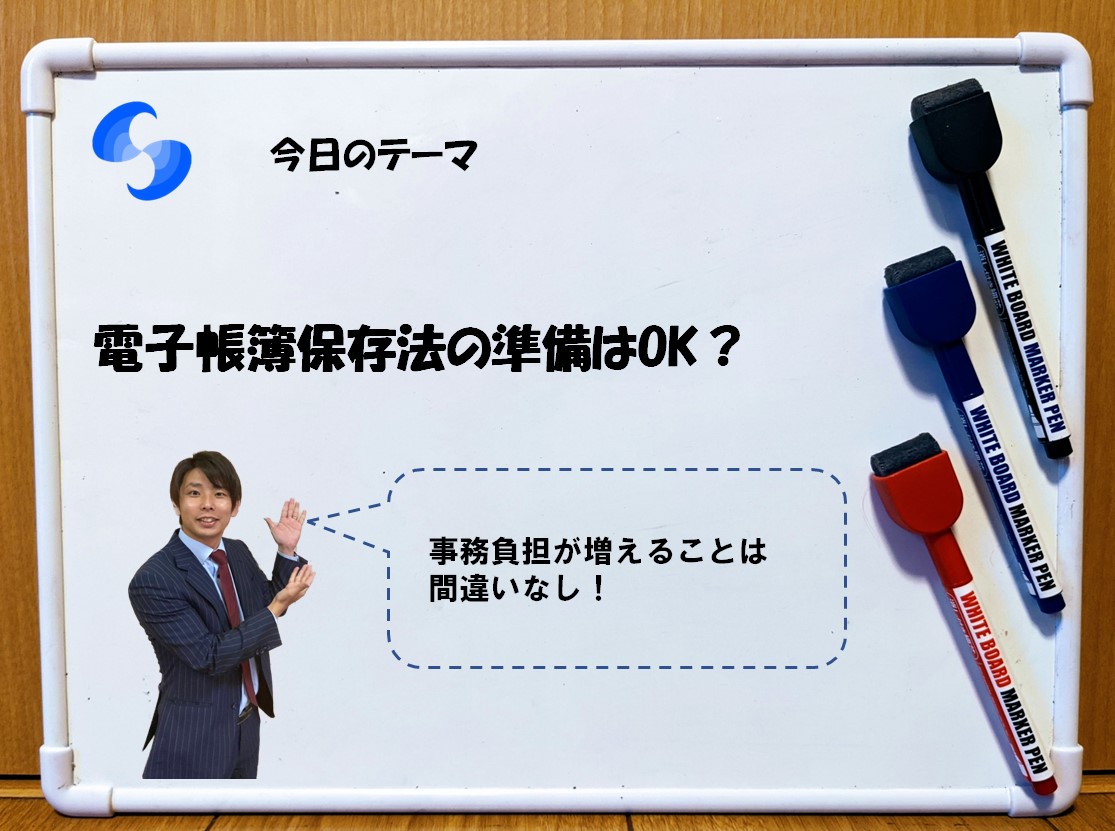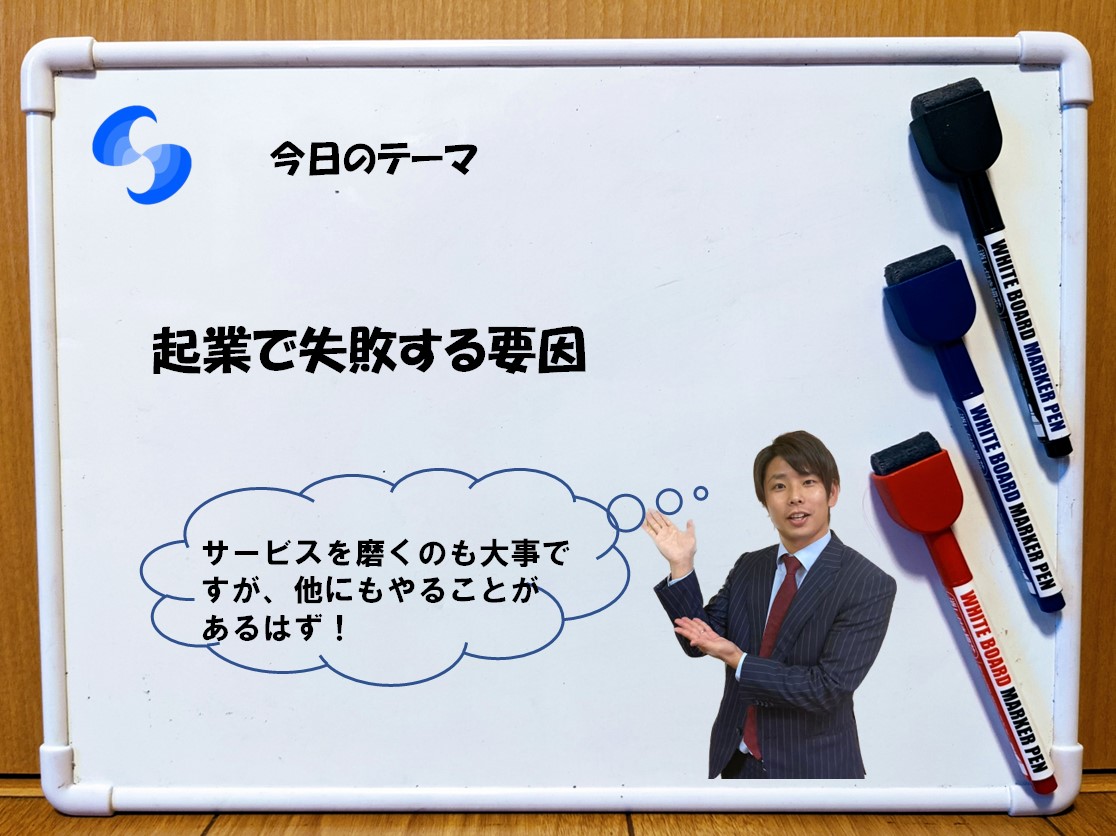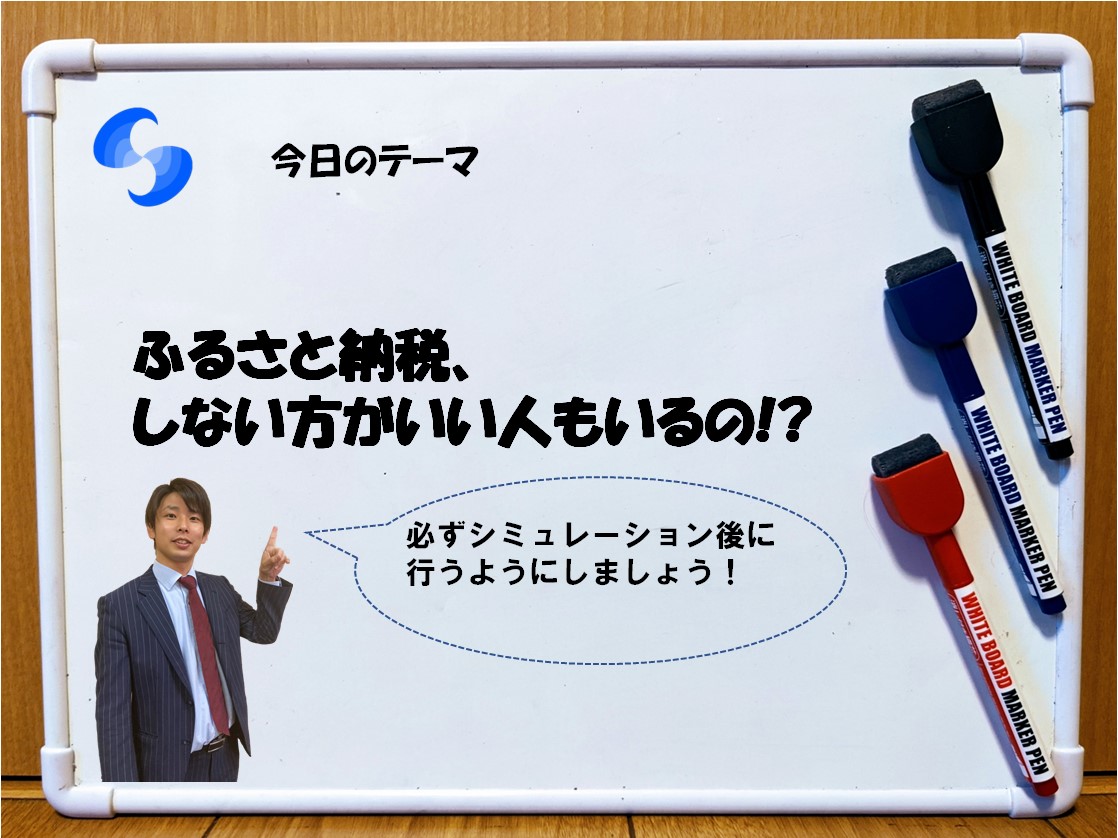電子帳簿保存法の準備はOK?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は2024年1月から始まる「電子帳簿保存法」について解説します。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法(以下、電帳法)とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。法律自体は1998年から施行され、何度か改正されています。
2022年1月の改正により、電子取引で扱った電子データを紙に出力しての保存ができなくなりました。ただし、電子保存の義務化については、企業の準備期間として2023年12月末まで2年間猶予されることになっています。
電子帳簿保存法の3つの区分
電子帳簿保存法の主な保存区分は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類に分けられます。
電子帳簿等保存
パソコンで作成したデータを保存する方法を、電磁的記録での保存といいます。DVDやハードディスクのようなメディアでの保管だけではなく、クラウドサービスを利用してサーバーに保管したデータもこれにあてはまります。
電磁的記録での保存は、データの作成者がパソコンで一貫して行う作業が必要です。クラウドサービスを利用すればデータの保存だけでなく、関係部署とのデータ共有もスムーズに行えるので業務効率化につながるでしょう。
スキャナ保存
取引した紙の書類をスキャンやスマホで撮影し、電子データに変換したものを電子文書として保存する方法も認められています。ただし、スキャナでの保存は電子データに変換する際の改ざんを防止する観点から、システム要件や日数制限が定められています。
たとえば「訂正・削除履歴が残るシステムに保存をする」「保存対象のファイルにタイムスタンプを付与する」など、一定の要件を満たさなければ、エビデンスとして認められません。
また、保存までの期間も、最長で約70日(2ヶ月とおおむね7営業日)以内とされています。
電子取引データ保存
電子データで受領する書類や電子明細は、利用者がデータを改ざんできないクラウドサービスを利用していれば、タイムスタンプ不要で保存可能です。
2023年10月1日から導入されるインボイス制度でも、適格請求書を電子データで保存することが認められています。電子データで保存した適格請求書は「電子インボイス」と呼ばれます。
電子インボイスは電子帳簿保存法に準じて保存しなくてはなりません。電子インボイスを検討している方は、電子帳簿保存法の要件と保存方法について把握しておきましょう。
電子帳簿保存法の対象書類
仕訳帳・総勘定元帳などの「国税関係帳簿」や、貸借対照表・損益計算書などの「国税関係書類」は電子帳簿保存の対象です。
国税関係書類のうち、領収書・請求書・発注書のような「取引関係書類」に関しては、自ら作成した書類の写しなどは電子帳簿保存の対象となります。
一方で、相手から受け取った書類は、スキャナ保存の対象です。またインターネット取引や電子メールでの取引などは電子取引に該当し、電子的に保存する必要があります。
電子帳簿保存法の対象とならない書類
手書きで作成した総勘定元帳や仕訳帳といった「主要簿」、同じく手書きで作成した「請求書」や「補助簿」といったものが該当します。
これらの書類はスキャナ保存をしても、電子帳簿保存法の対象とはならず、紙の原本を保存する必要があるので注意しておきましょう。
電子帳簿保存法の対象者
電子帳簿保存法の対象となるのは、国税関係帳簿書類の保存義務者です。原則としてすべての企業や個人事業主が対象になります。事業規模は問われません。
ただし、電子データを一切取り扱わない企業や個人事業主は、例外的に対象外となります。
不正行為のペナルティに注意
2022年1月から発効された改正は、電子データ保存をスムーズに行えるようになりますが、ひとつ注意すべき点があります。それは、要件緩和と同時に適正な保存を担保するための制度として、新たにペナルティが導入されたことです。
スキャナ保存や電子取引の記録を正確に行わず、隠蔽や改ざんした事実があった場合には、その事実に関する重加算税が10%加重されることになります。
まとめ
今後さらに経理処理の電子化やペーパーレス化に取り組むことは、テレワークの推進にもつながっていくと考えられます。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。