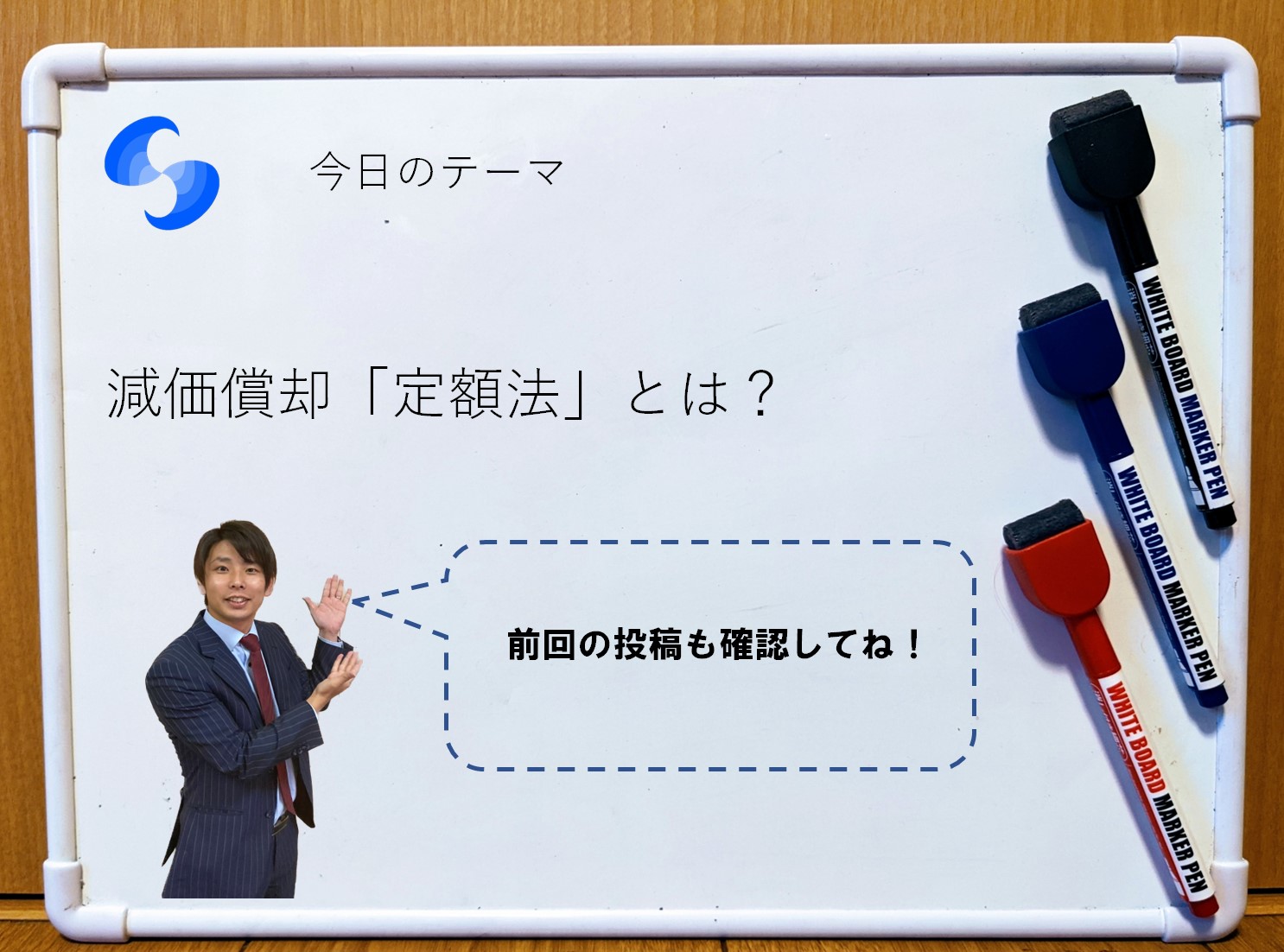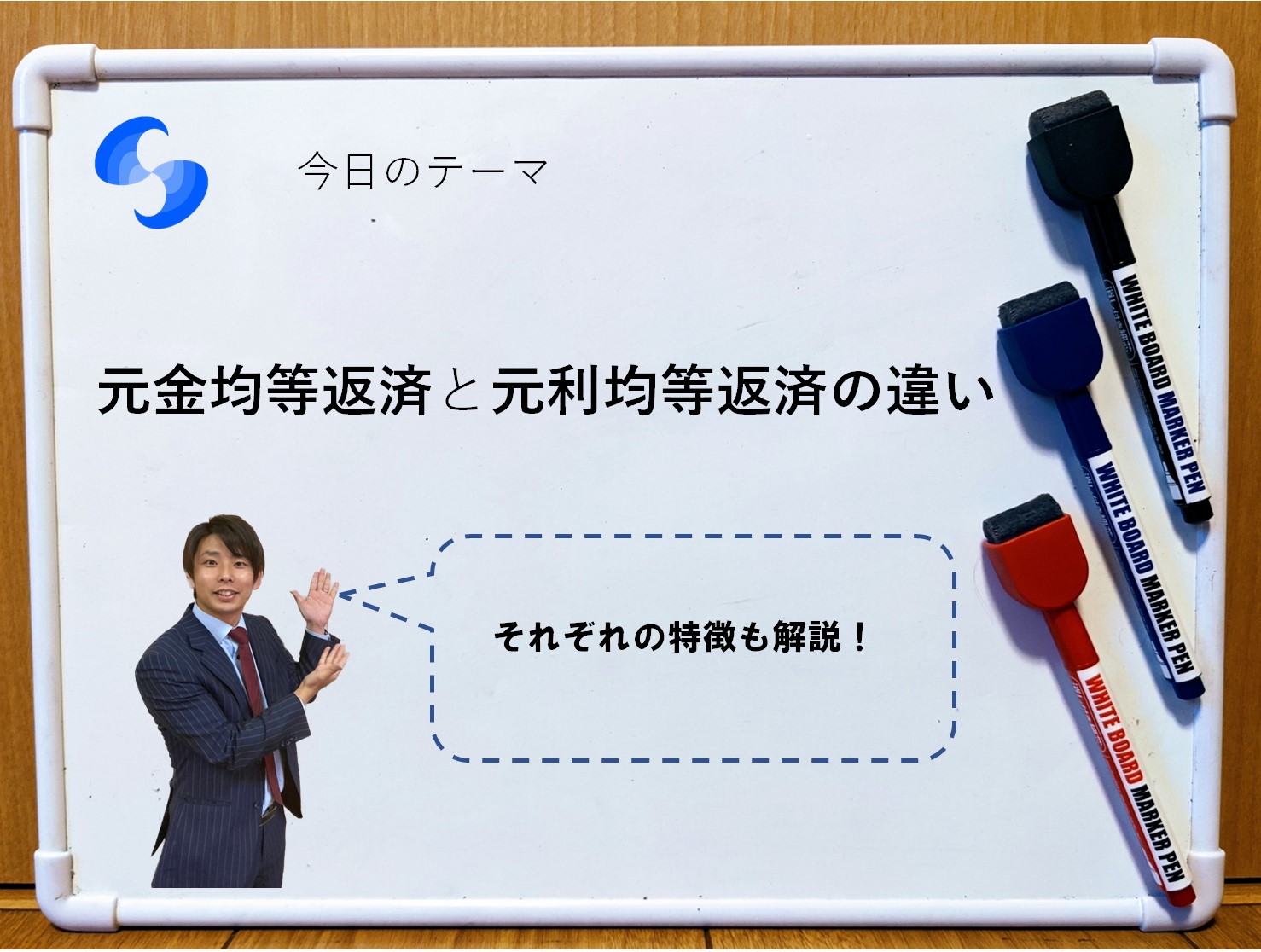減価償却「定額法」とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。 今回は、減価償却の定額法にについてです。
前回は「定率法」について解説をしましたが、はじめに減価償却について少しおさらいをし、メリットを解説しましょう。
減価償却について
建物や建物付属設備などの固定資産は、高額で、且つ、年月が経つにつれてその価値が下がっていきます。このような固定資産のことを「減価償却資産」といいます。
減価償却資産は、使用可能期間の全期間で分割をして経費としてみていくべきです。
減価償却資産の取得にかかった経費を、各年分の経費として費用計上し、分売する手続きを「減価償却」といいます。
減価償却を行うメリットについても少しお話します。
減価償却を行うメリット
節税
減価償却する最大のメリットは、節税。
正確な財務状況を確認できるメリットもあり、毎年減価償却費を計上することで利益を抑えられます。
資産が残る
減価償却は資産が残ります。なぜなら減価償却費は帳簿上費用として計上しますが、実際に現金の出費があるわけではないからです。
減価償却費は損益計算書に記載され、実際には減価償却費で記載した分の資金は会社に留まっています。
財務状況が良く見える
減価償却は財務状況が良く見えます。理由は、資産の購入額を将来に渡って分割して費用計上する仕組みになっているからです。費用が分割されているため利益は一度深く削ることがなく、安定した事業運営がされているように見えます。
損益をしっかりと把握できる
各期の実質的な損益を正確に把握することができます。
減価償却を行わないと、取得費用の全額を費用計上した場合、適正な期間損益計算ができなくなります。
減価償却の「定額法」とは
定額法は毎年の償却額が均等になるように計算します。定額法による減価償却費の計算式は、
「定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率」
資産の購入費用を毎年均等に償却していくため、計算が分かりやすいです。
ある資産を5年の定額で計算した場合、1÷5=0.2となり、この場合の定額法償却率は0.2となります。この償却率は資産の耐用年数によって、償却率が変動してくるので資産ごとに確認しましょう。
資産の耐用年数が何年かわからない場合は国税庁のHPに記載されています。
減価償却費の計算で気を付けること
耐用年数を間違わないようにしよう
固定資産には、有形固定資産・無形固定資産に関わらず、定額法・定率法が最初から決められているものがあるため注意は必要です。また、年度途中で購入した場合は、月割計算が必要になります。国税庁のウェブサイトにある「耐用年数表」などと照らし合わせて判断しましょう。
償却中の資産を処分する際の処理
償却している途中の固定資産を、何らかの理由で処分した場合、それによって発生した損失を「固定資産除却損」として計上しなくてはなりません。
除却処理を忘れてしまうと、すでに手元にない固定資産に償却資産税がかかり続けてしまうので注意が必要です。
上記の内容以外にもご不明点などございましたら翔彩サポートまでご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。