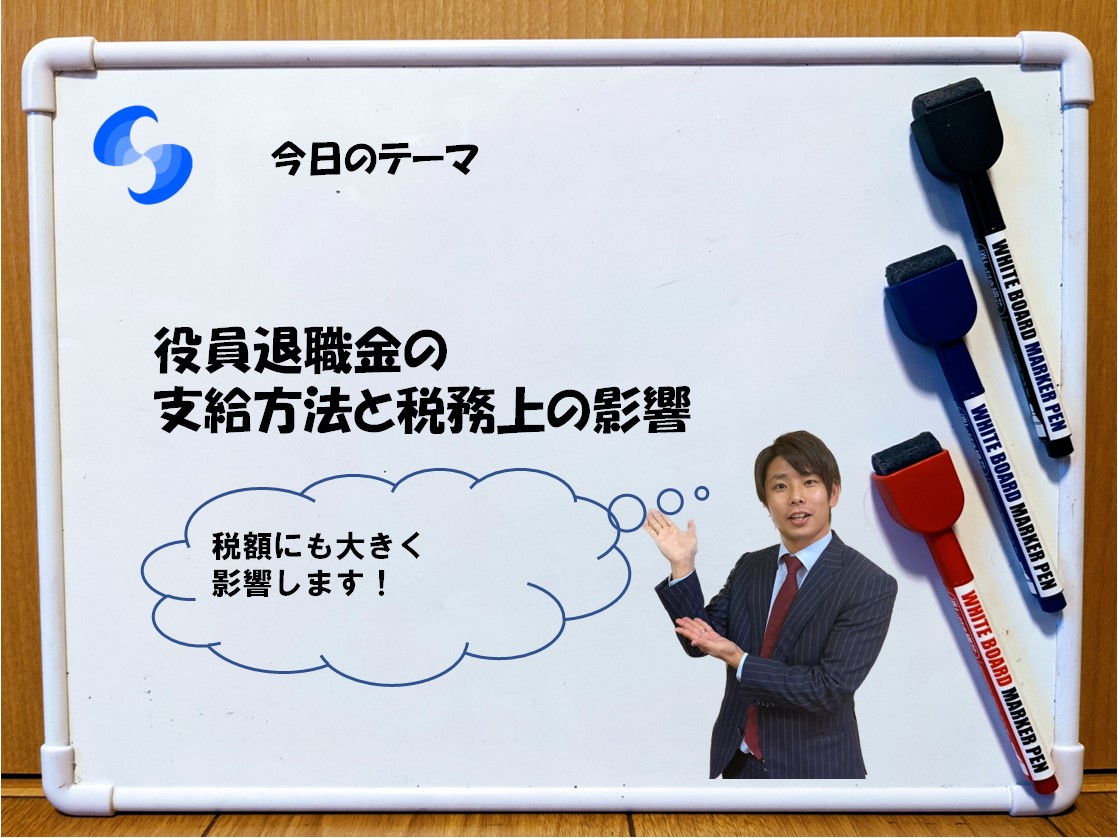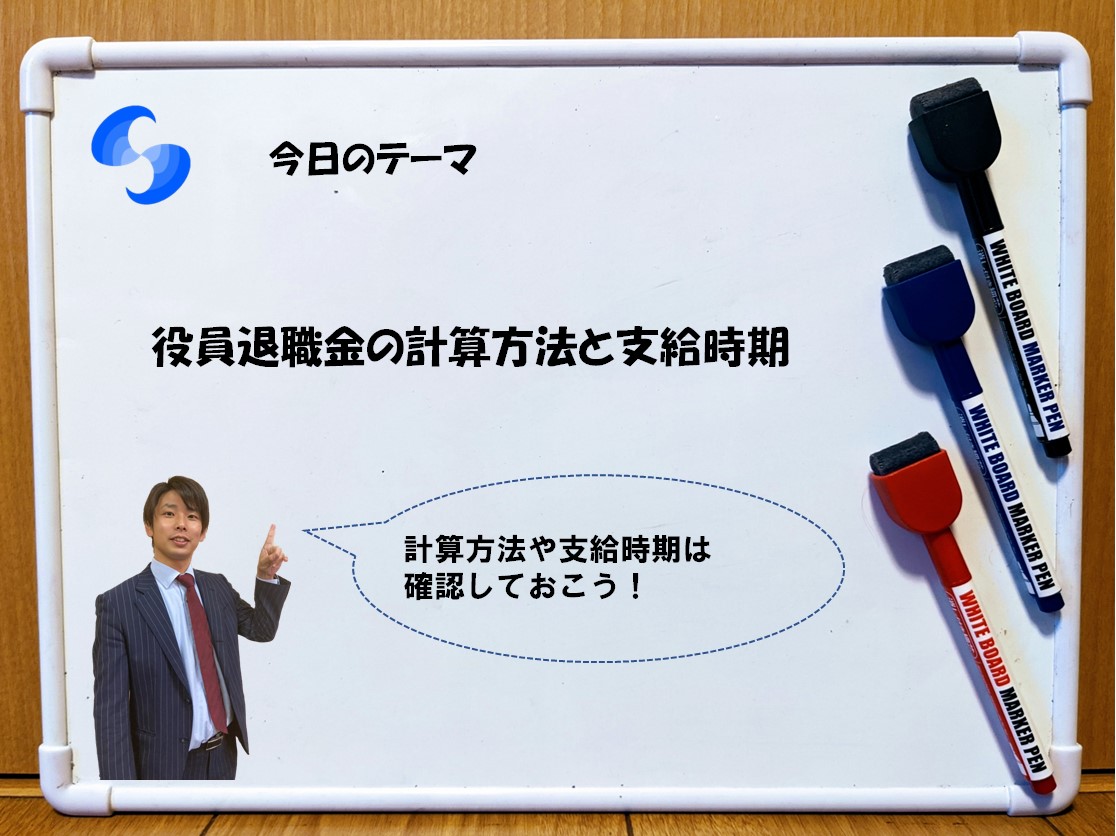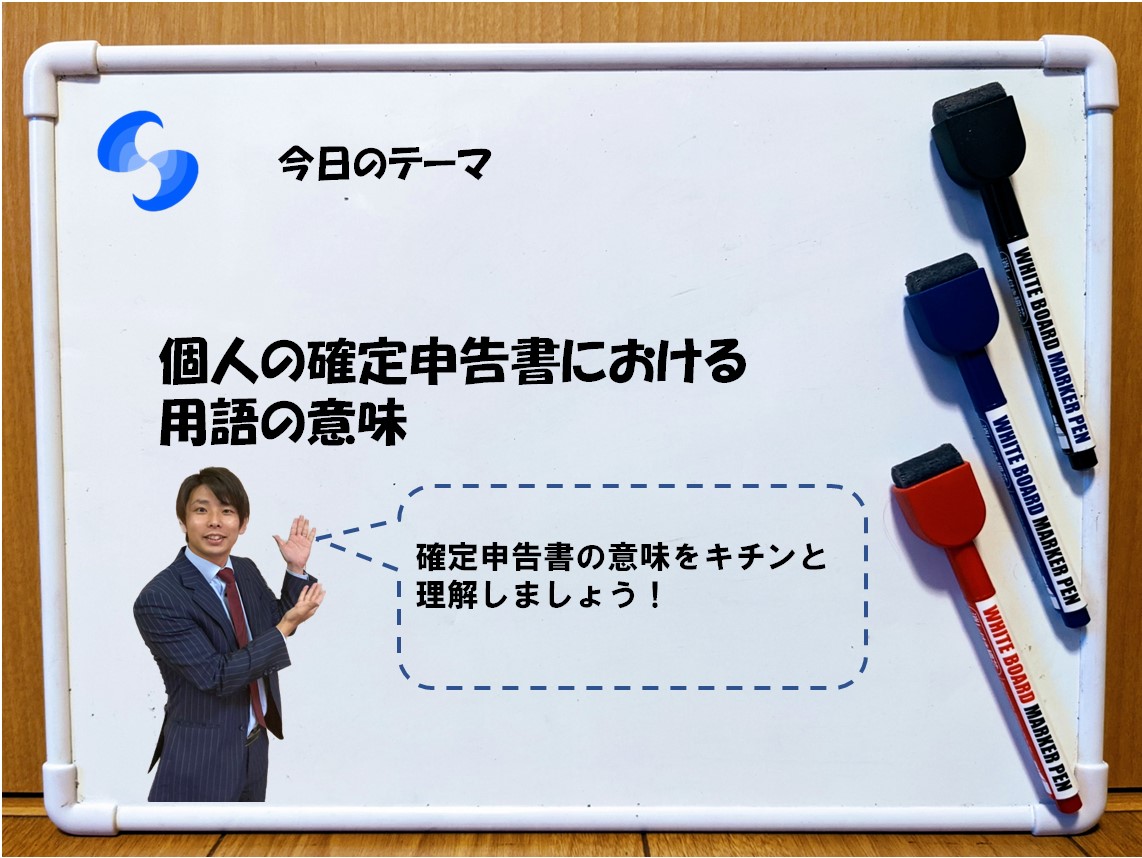役員退職金の支給方法と税務上の影響
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は『役員退職金の支給方法と税務上の影響』について解説していきます。
役員退職金の支給方法
支給方法も一括や分割または年金形式などがあり、場合によっては金銭ではなく株式や不動産など他の資産で支給することも可能です。実情に応じて決議をします。
一括支給
一括で支給する場合が多いです。
税金計算上は退職金額が確定したときでも、支給のタイミングでも費用として処理することが認められています。
分割支給
資金繰りの都合などで一括払いができず、何回かに分割して支給する場合もあります。
こちらも、分割払いについて総会などで決議されていること、分割に合理的な理由があることや分割が長期ではないという事情があれば、税金計算上も役員退職金の支給として費用処理できます。
この場合、支給総額の確定時点で税金計算上の費用とする方法と分割して支払う度に税金計算上の費用とする方法のどちらも可能です。
なお、長期とはおおむね3年程度と言われています。
年金形式での支給
退職金をはじめから長期の年金形式で払う方法もあります。
なお、この場合には税金計算上も年金として処理をする必要があります。
法人側では、年金を支払う度に費用処理、受給者側も年金の受給に応じて所得税の計算がされます。
金銭以外での支給
退職金は金銭での支給が原則です。
しかし、受給者との合意があれば金銭以外(株式・不動産・保険の権利など)での支給も可能です。
その際は、金銭以外の財産を時価で評価して、税務・会計上の処理をする必要があります。
税務上の影響
役員退職金は高額になるケースが多く、資金や会計の両面で大きな影響があります。
税務上は費用になりますが、不相当に高額な部分については税金計算上の費用として認められません。
退職金の支給によって法人税だけではなく他の税目にも影響が生じます。
税額への影響
役員退職金は金額が大きいこともあり、単年度で見た場合には欠損金が発生することもあります。
一定の要件を満たすことで、欠損金は前期の利益と相殺して税金の還付を受けたり、翌期以降の利益と相殺して税金の負担を軽減したりできます(繰越欠損金の活用)。
株価対策
会社が役員退職金を支給することにより、決算において損失が発生し、会社の税務上の株価が下がるケースがあります。
そのため、退職金を支給したタイミングで自社の株式を先代から後継者に動かすことで、退職金支給前と比べて低い価額となり、所得税や贈与税などの負担が軽くなる場合があります。
所得税の課税方法の違い
退職金は給与や年金と比べて、所得税の計算が受給者にとって有利になります。
そのため、受給者は退職金で税負担が少なくまとまった金額を受け取ることができます。
ただし、年金形式の場合には退職金ではなく年金として税金計算がされます。
上記の内容以外にも役員退職金について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。