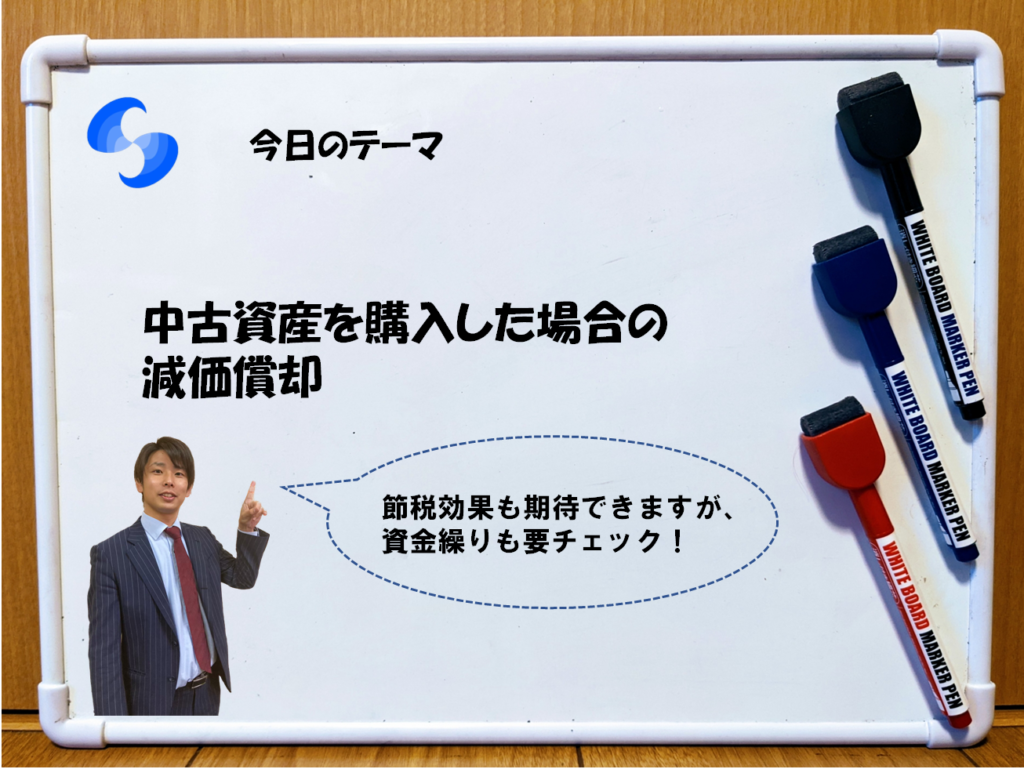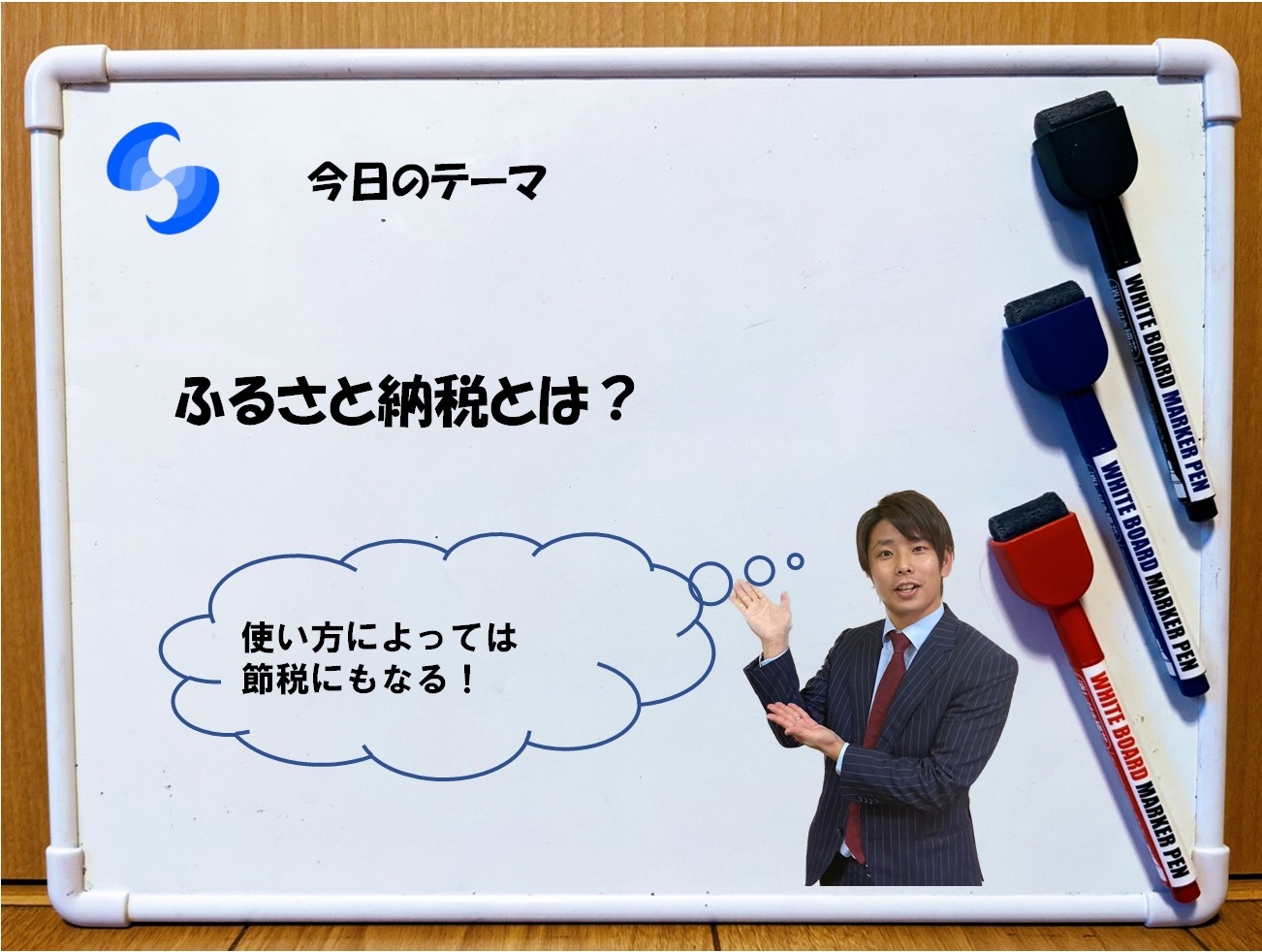中古資産を購入した場合の減価償却
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
固定資産は、取得時の資産が新品または中古かによって減価償却費の計算方法が変わってきます。
今回は『中古資産の減価償却費の計算方法』について解説していきます。
減価償却とは何?
固定資産は、購入してから長期にわたって事業収入に寄与するものと考えられているため、固定資産の購入時の支出額の全額を支出した時点で費用とするものではなく、使用する期間に応じて費用配分するべきものとされています。この取得原価を使用期間に応じて費用配分することを減価償却といい、勘定科目では減価償却費といいます。
新品資産と中古資産の減価償却費の計算方法の違い
減価償却費は、一般的に取得原価を耐用年数で除したものを減価償却費として計上をします。
取得原価とは、その資産の取得に必要となった支出額のことをいい、固定資産本体の価格だけではなく、設置費用やその本体を動作させるために必要となった部品等の付随費用も含めて計算します。
例えば、社用車を取得した場合、社用車本体のみならず、社用として使用するために必要な座席シートの変更料等のオプション料金も取得原価に含みます。
耐用年数とは、その資産が会計上で使用可能と見込まれる期間であり、資産の種類や用途、材質等で異なる年数が、固定資産ごとに国税庁により定められています。
例えば、車両運搬具でも普通車は6年、軽自動車であれば4年というふうに決められています。
新品資産と中古資産で減価償却費の計算方法が異なるのは、この耐用年数にあります。
中古資産の耐用年数
中古資産の耐用年数は国税庁で定められている新品資産の耐用年数を基に算出をして、減価償却費の計上に使用をします。
新品取得時から中古資産として取得するまでの経過年数により、その算出方法は異なります。
新品資産の法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%の年数
新品資産の法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
上記2つのいずれの算出方法においても、1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
その年数が2年に満たない場合には2年とします。
節税対策としても有効活用できる?
新品取得で300万円の普通車を取得した場合の減価償却費は、新品価格の300万円を法定耐用年数6年で除した50万円です。
ですが、中古取得の場合、耐用年数は短くなりそれに伴い1年あたりの減価償却費は大きくなります。その結果、節税効果も期待できます。
中古車のように3年ごとに乗り換えているケースも多くみられますが、減価償却とキャッシュの動きが違ってきますので、必ず資金繰りに問題ないか確認してから判断しましょう。
上記の内容以外にも中古資産を購入した場合の減価償却について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。