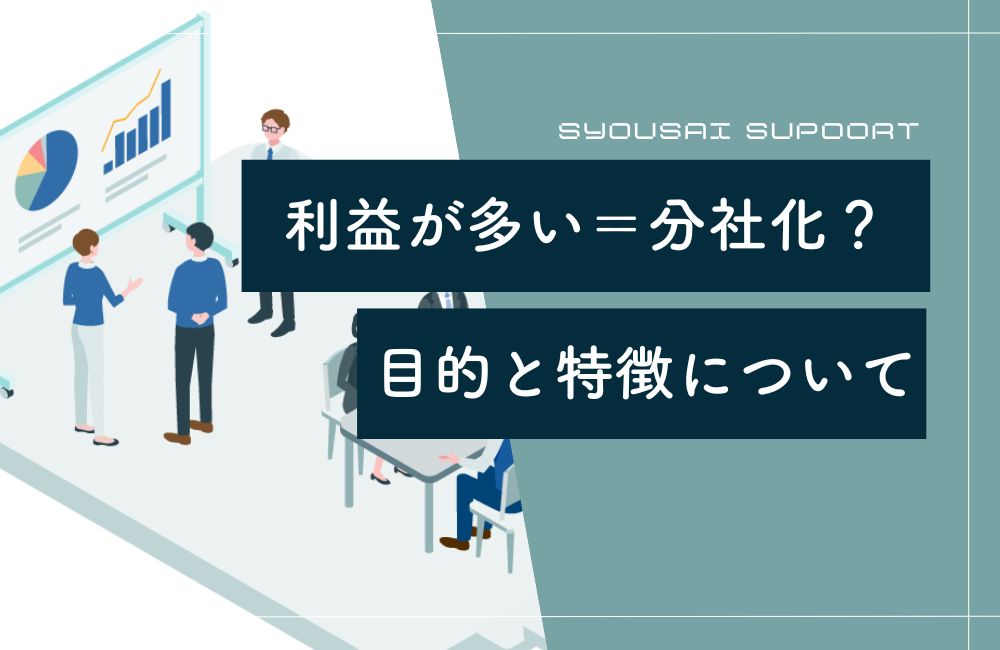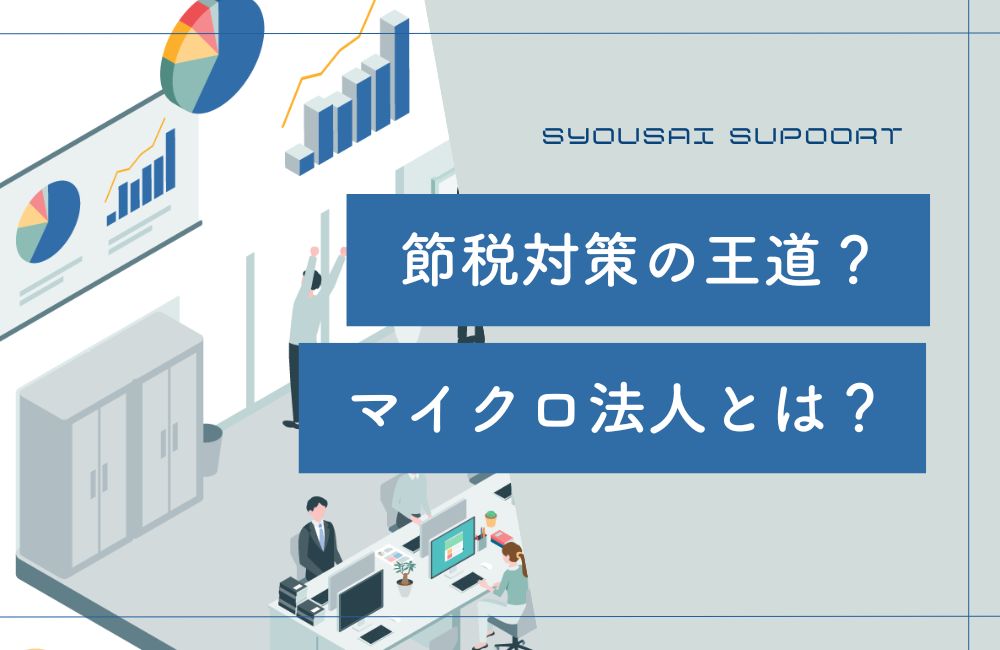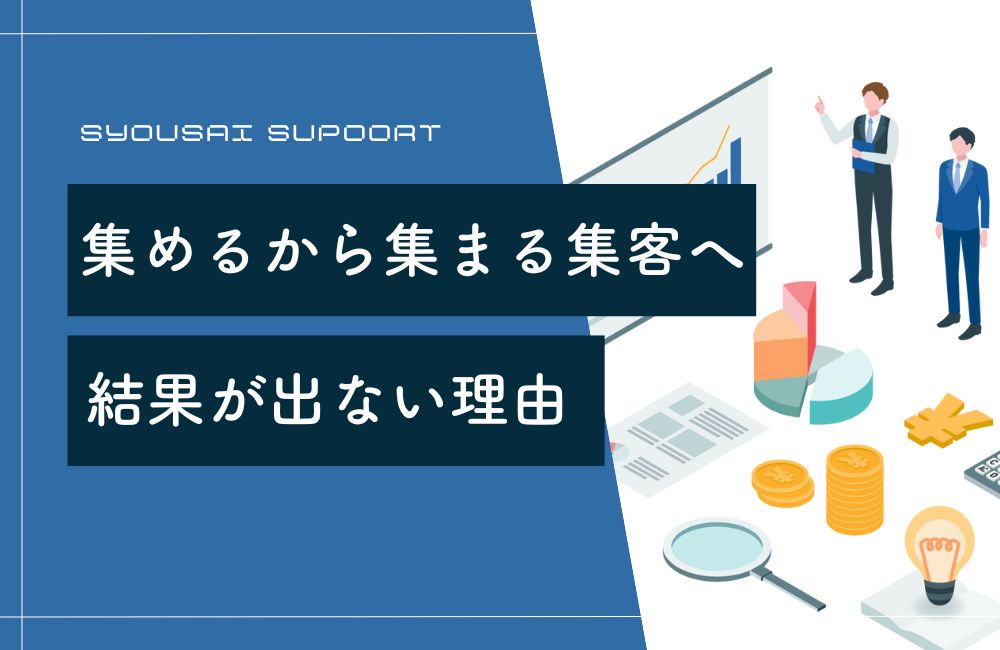利益が多いと分社化した方が良い?分社化の目的とメリット・デメリットについて
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
『利益がしっかり出るようになったら、税理士から分社化を勧められた』
『分社化を勧められたけど、何のために会社を分ける必要があるのかを知りたい』
『分社化によるメリット・デメリットを知りたい』
毎年、利益をしっかり残せるようになったときに顧問税理士や経営者仲間から勧められるケースは多いと思います。
目に見える目的としては節税が考えられると思いますが、その他にも経営の効率化や会社全体のリスク分散など、分社化することは経営を長くしていく上で大きなメリットがあります。
そこでこの記事では、分社化の目的や分社化によるメリット・デメリットなどについて、起業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。
分社化を勧められた方や分社化を勧めている中で困ったことがある方は、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。
分社化とは?

分社化とは、複数の事業を持つ企業が事業の一部を切り離し、独立した会社を作ることを指します。
切り離された事業は、子会社や関連会社として運営されます。
分社化する方法には会社分割(新設分割・吸収分割)や事業譲渡などの方法があります。
分社化が行われる背景

分社化が行われる背景は、主に以下の3つです。
- 業務効率の改善
- 新規事業への参入
- 経営の選択と集中
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
業務効率の改善
分社化すると、事業ごとに経営判断や意思決定が迅速にできるようになります。
分社化すると別法人となるため、事業単位で収益の把握を行えるようになります。同一法人では部門別での管理が必要になりますので、売上及び経費の帰属が煩雑になってしまうことがあります。
こうした業務効率・経営合理性の改善が、分社化の大きな目的のひとつです。
新規事業への参入
新規事業に参入しようとする際、社内に事業部を作って事業を行うよりも、新会社を設立した方が、手続きなどスムーズに事業を推進させられる場合があります。このような場合にも、分社化が選択肢に挙げられます。
経営の選択と集中
「経営をより選択しやすく、集中させたい」という意思によって、分社化が行われることもあります。
経営の「選択と集中」を目指す企業は、分社化を利用して、事業ポートフォリオを最適化し、核となる事業にリソースを集中させます。これにより、企業は競争力のある事業に焦点を当て、長期的な成長と収益性の向上を目指すことができます。
分社化は、企業が市場でのポジションを強化し、持続可能な成長を達成するための戦略的な手段となります。
子会社化との違いとは?

分社化は、会社の事業部門などを切り出して、独立した子会社を作ることです。
これに対して子会社化は、他の会社の株式を取得して経営権を掌握し、自社グループの傘下に迎えることを指します。
分社化と子会社化は、どちらも本社の下に子会社を作るという点では同じですが、「もともと自社にあった事業を分離して子会社化する」点と、「M&Aなどで外部の会社を子会社化する」点で大きく異なります。
一般的に親会社が子会社に対して100%の出資を行うことが多く見られます。
一方、子会社化の場合は、目的によって出資比率が異なるため、完全な親子関係にならない場合も珍しくありません。
分社化によるメリット
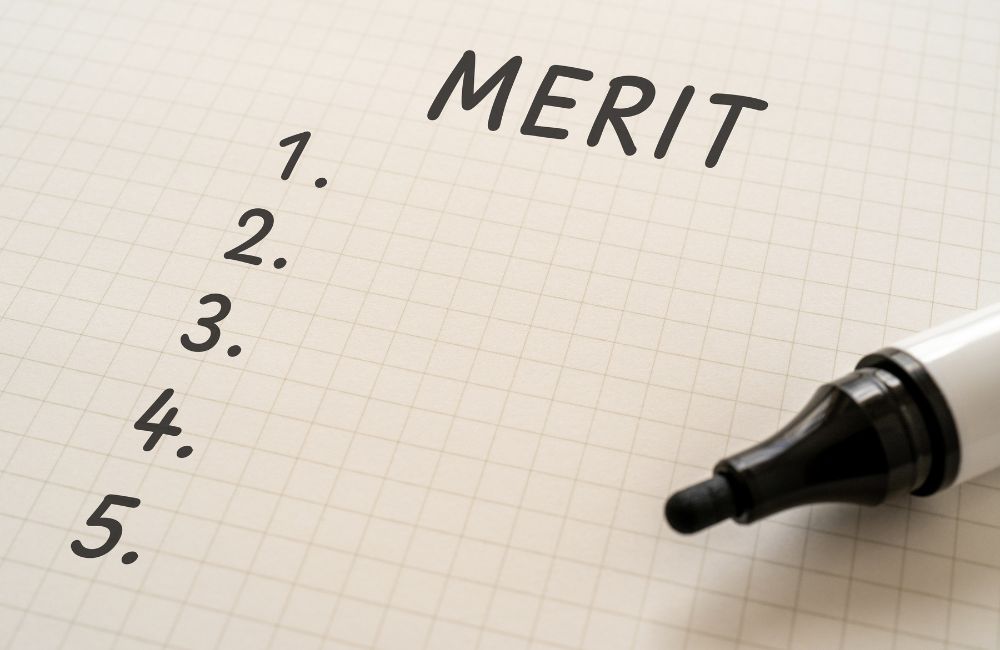
分社化によるメリットは、主に以下の6つです。
- 節税効果が得られる
- リスク分散
- 経営の効率化
- 事業承継での活用
- 資金調達の多様化
- 事業の専門性の向上
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
節税効果が得られる
所得税は所得の増加にともない税率が段階的に上がる「累進課税」を採用していますが、法人税は法人の所得の増減に関わらず税率は23.2%と一律です。
ただし、資本金が1億円を下回る中小企業に関しては、課税所得金額が800万円以下については15%、それを超える部分については23.2%と税率が2段階に分けられています。
つまり、分社化することによって利益を分散させることで、税率の低いところで計算がされ全体的な税額を抑えられることに繋がります。
リスク分散
分社化を行い業績が芳しくない事業部門を自社の財務諸表から切り離すと、収益が改善されますので金融機関などからの資金調達がしやすくなります。
試算表上、利益がしっかり出すことができていれば、信用能力が高まるため第三者からの評価が上がり、経営上のリスク分散ができます。
経営の効率化
完全に別会社となると、作成する財務諸表も別々になり、事業成果が明確化しやすくなります。このように、事業ごとの業績の「見える化」が促進されるため、経営の効率化が期待できます。
事業承継での活用
後継者候補が複数人いる場合や、長男と次男のそれぞれに会社を継がせた方が良い場合などにも、分社化は活用できます。たとえば次男に継がせたい事業部門を分社化させれば、長男と次男のそれぞれが別々の会社を継ぐことも可能です。
また事業承継前に不採算部門を本体から切り離し、少しでも良い状態にしてから継がせたいと思う場合などにも、分社化は有効な手法のひとつと言えます。
資金調達の多様化
分社化することで、資金調達を多様化できることも魅力の1つです。
各分社が独自の財務戦略を立てることができるため、株式公開やベンチャーキャピタルからの資金調達など、多様な方法で資金を集めることが可能になります。
また、特定の事業にリスクが集中することを避けることもできます。
事業の専門性の向上
事業の専門性が高まることもメリットの一つです。
各分社が特定の事業に特化することで、その分野における専門知識や技術を深めることができます。これにより、競争力のある製品やサービスの開発が可能になり、市場での優位性を確立することができます。
分社化によるデメリット
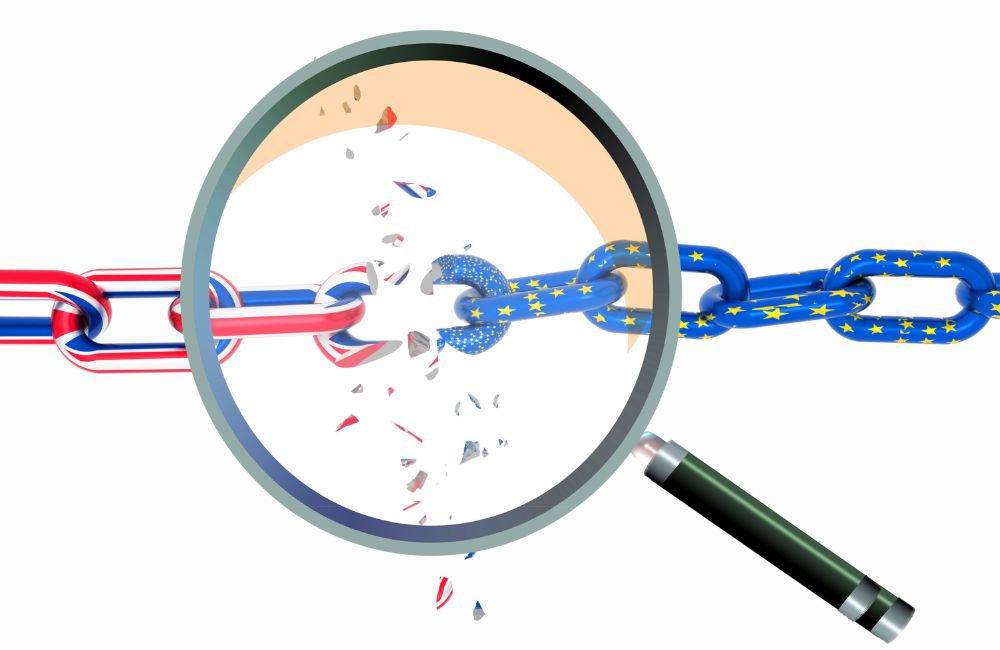
分社化によるデメリットは、主に以下の4つです。
- 煩雑な手続き
- 会社運営にコストが必要
- 親会社との関係性が薄まるリスク
- 株主から3分の2以上の同意が必要
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
煩雑な手続き
分社化を行うためには、財務・税務上の複雑な手続きを行わなければなりません。これらの手続きは専門性が高く、時間や費用も必要です。
また分社化した後は独立した企業として管理部門を立ち上げ、財務や税務だけでなく、総務などこれまで本社の管理部門が行っていたさまざまな業務を行わなければなりません。
会社運営にコストが必要
ひとつの会社であったものが別会社に分かれれば、家賃などの支払いや財務部門の人件費、顧問税理士や弁護士などに支払う費用が新たに発生することになります。
やり方次第では分社化による節税メリットよりも、分社化したために生じる維持管理コストの方が大きくなる場合もありますので、この点には十分に注意しておかなければなりません。
親会社との関係性が薄まるリスク
それぞれの会社が各目標を掲げ、日々の業務に取り組みます。
このときお互いが定期的に交流する機会が少ないと、両社の関係が希薄になってしまうことがあります。
協力関係を築くことが難しくなってしまう事態を回避するためにも、お互いに日頃からのコミュニケーションを意識しておいた方が良いでしょう。
株主から3分の2以上の同意が必要
会社を分社化するためには、株主総会を開催し、特別決議で株主の3分の2以上の同意を得る必要があります。
分社化に大きなメリットがあり、その判断がどれだけ合理的なものであったとしても、3分の2以上の株主を説得して同意を得られなければ、分社化をすることはできません。
もともと同族経営で社長が株主だけの会社はこの問題が起こりませんので、取り組みやすくなります。
分社化が向いているケース
分社化が向いているケースは、主に以下の3つです。
- 好調な事業と不振な事業の差が大きい場合
- 新規事業への参入を検討している場合
- 後継者の育成が必要な場合
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
好調な事業と不振な事業の差が大きい場合
全ての事業が業績不振の場合、分社化だけで解決するのは困難です。
業績が好調な事業と不振な事業に分かれる場合は、分社化によって経営不振から脱却できる可能性が見込めます。
分社化すれば不採算部門が本社から切り出されるため、倒産リスクを抑えることができますし、対外的な評価も違ってくるでしょう。
新規事業への参入を検討している場合
本格的に新規事業への参入を目指す場合に、分社化が選択肢に挙がるケースもあります。
定款の事業目的にない、まったく新規の事業を始める場合、株主総会の特別決議で定款変更の承認を得た上で、変更登記を行う必要が生じます。
これらの手続きと比較し、当該事業を別会社として申請する方がスピーディーと判断された場合、分社化が選択肢に挙がります。
その他、分社化することで事業の専門性を高められる点もメリットとして考えられます。 事業の立ち上げスピードが速くなるため、収益化までの時間短縮にも期待ができます。
後継者の育成が必要な場合
事業承継の過程で、後継者候補に経営者教育を行う必要がある場合も、分社化が選択肢に挙げられます。分社化した会社の経営を、後継者育成の一環として後継者候補に任せることで、企業経営の経験値を高められるというメリットがあります。
まとめ:分社化を勧められたら、翔彩サポートまで
分社化は、経営戦略の一環として多くのメリットをもたらしますが、実行には慎重な検討が必要です。
また、分社化には、新たな経営体制の構築、株主とのコミュニケーション、煩雑な税務手続き・法的手続きなど、多くの課題が伴います。これらの課題を克服し、分社化を成功させるためには、専門家の知見が不可欠です。分社化を検討する際には、これらの点を総合的に考慮し、専門家からの適切なアドバイスが必須です。
分社化を検討している方は、ぜひ翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。