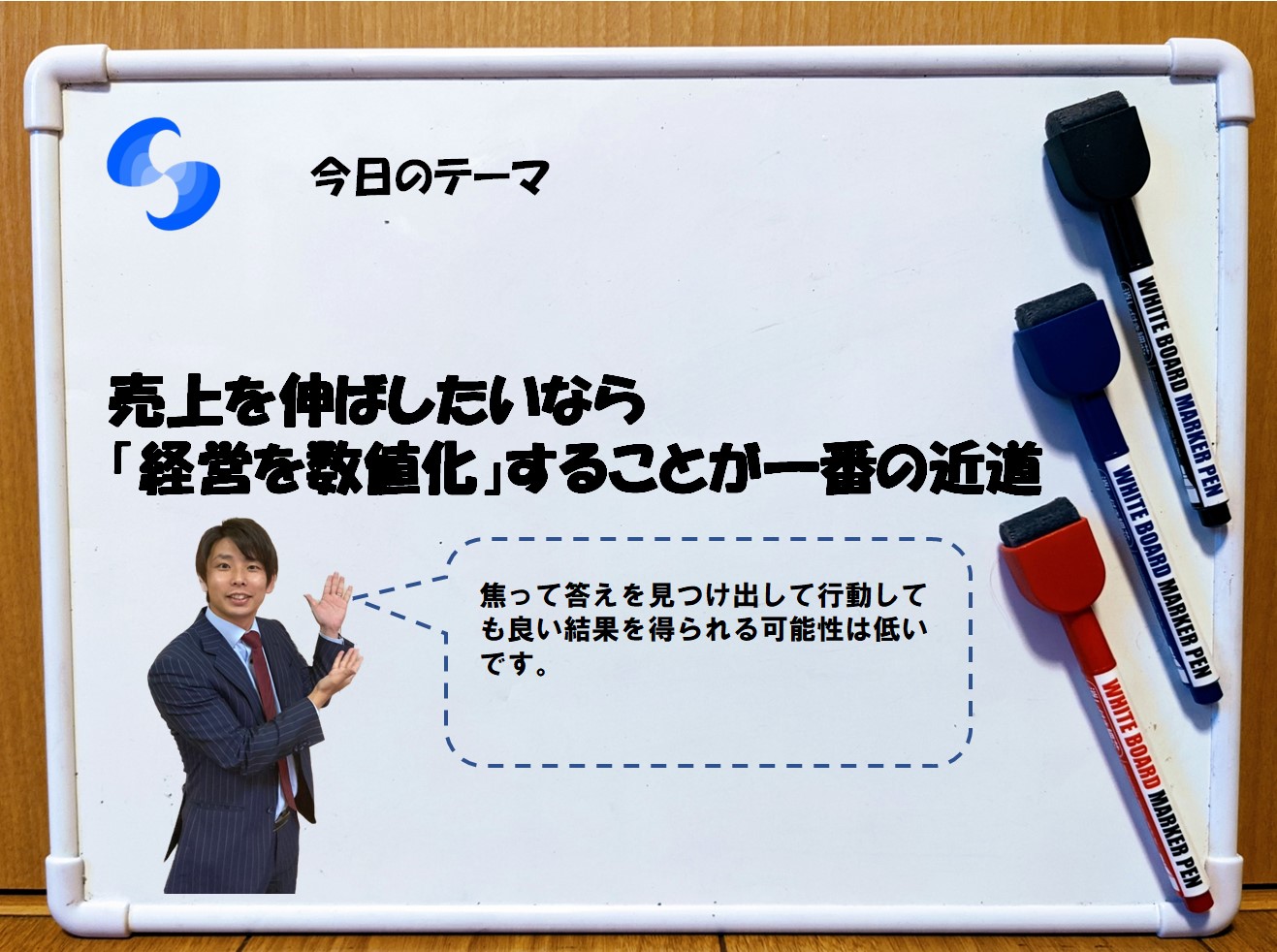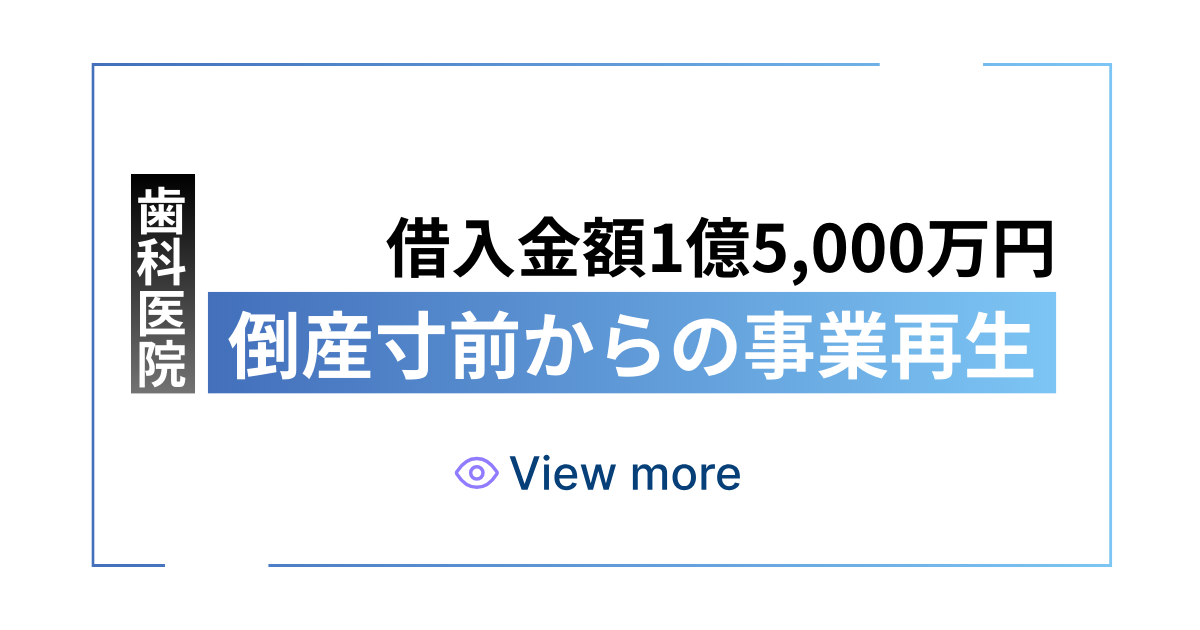売上を伸ばしたいなら「経営を数値化」することが一番の近道
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
開業当初は、目先の売上を確保するための集客や新サービスの開発、従業員育成成など、やらなければならないことに追われてマネジメントが後回しになりがちです。
特に、一人経営者の方や数字に苦手意識のある経営者の方は、どうしても数字を避けたいものです。
解決しないまま後回しにしてしまうと、経営者の勘だけに頼って経営判断をしたり、資金繰りもどんぶり勘定となってしまったり、。
今回は、なぜ数字を見ないと経営がうまく回らないのかという理由を考えながら、経営を数値化する重要性についてお話しします。
経営数値を見ないとダメ?
会社経営をしていく上で、経営数値をきちんと理解できていないとダメという話をよく言います。
店舗ビジネスであっても、それ以外の業種であっても、その重要性は変わりません。
なぜ、数字を見ないとダメなのかについて、主に以下の3つです。
- 現状の経営課題が特定できない
- スタッフとの意識の共有ができない
- 会社経営の命綱である資金繰りが見えない
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
現状の経営課題が特定できない
まず、経営の数字が見えていないことで発生するデメリットとして大きなものが、経営上の課題が特定できないということです。
例えば、多くの経営者は売上を増やしたいと考えていると思いますが、この「売上を増やしたい」というイメージのままでは、何をどうしたらよいうかというのがよくわからないままになってしまうケースが多いです。
漠然とした考えになればなるほど、次に取るべき行動がは明確化しにくいものです。
より具体的に数値に落とし込むことが大切になりますので、「今から〇ヶ月で毎月の売上を100万円増やす」というふうにします。
そうすることによって、月々いくらずつ増やしていかないといけないのか、そのための行動として今行っている取り組み以外にできることは何なのかを洗い出すことができていきます。新しいサービスを作るべきなのか、サービスはそのままで新規集客に注力すべき、などというやるべき課題が見えてきます。
スタッフとの意識の共有ができない
経営数値が見えないと、スタッフとの意識や課題、問題認識のズレが発生します。
先ほどの「売上を増やしたい」という経営者のイメージであれば、
- どれくらい?
- いつまでに?
- どうやって?
というイメージがスタッフそれぞれ違ってきます。
このあたりが、明確になっていないと、スタッフ間でどこに課題があるのか、何を優先してやるべきなのかというような共通認識が曖昧になってしまい、コミュニケーション不足が問題でさらに深刻な問題に発展します。
ビジネスは、一人ではできません。自分以外の誰かの協力のもとに成り立つものです。
たとえ、数人であったとしてもチームが機能しないと結果は出ないので、売上を増やすという経営者のやりたいことが達成できなくなってしまいます。
チームとして成果を出していくためには、数字で会話することが重要なポイントとなります。
会社経営の命綱である資金繰りが見えない
会社経営をしていくための生命線は「お金」です。
経営において、お金は当然に重要なもので、お金がなくなった時点で事業は終わりを迎えますが、赤字であったとしても資金が潤沢に残っていれば終わる事はありません。
いくらでも再生が可能です。
経営していて資金繰りの不安が常にあると、お客さんを集めたり、いい商品を作ったり、従業員やスタッフの育成をしたりしなければならない一方で、お金のことが頭から離れず、本業に集中できないこともしばしば…
そこで、重要になるのが、やはり数字です。
- 売上の入金がきちんとされているか?
- 銀行口座の残高がイメージ通りに増えているか?
- 支払いのためのお金が十分にあるか?
利益を出して、お金を増やしていくことだけが経営ではないですが、お金を管理していかないと経営は継続できません。
安心して経営に集中するためにも、経営数値をしっかり理解して経営することが重要となります。
経営数値の分析を行うメリットとは?
経営分析は、企業が成長するうえで欠かせないプロセスです。
経営分析では、主に以下のようなメリットが得られます。
- 経営状況を客観視できる
- 自社の強み・弱みが洗い出せる
- 経営計画の策定・見直しに活用できる
- 投資の判断材料になる
- 現状分析・将来予測が可能となる
- 問題点やビジネスチャンスを発見できる
- 意思決定のスピードを上げることができる
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
経営状況を客観視できる
利益が出ていて黒字でも、支払いに必要な資金がなく倒産する可能性もあるため、経営状況を主観的に判断するのは高リスクでしょう。
単に売上がある、利益が出ているだけでは、経営状況が必ずしも良好とは判断できません。なぜなら、利益は一時的なものであったり、売上が高くてもコストがかかりすぎて利益が少なかったりするなど、実情は体感や目の前の売上だけではわからないからです。
経営分析では決算書や財務諸表など定量的な情報から分析するため、経営状況が客観視できます。数字という確固たる事実のもと、自社の経営状況を正しく把握することが可能です。
自社の強み・弱みが洗い出せる
経営分析では、自社の強みや弱みも客観的に判断できます。売上高や利益を明確にすると強みのある事業がわかるからです。
一方、売上に問題はないが利益率が低い事業があれば経営における弱みであり改善余地があるとわかるでしょう。
また、確固たる事実である数字から分析すると、潜在的な課題が見つかる場合も多いです。経営者はこうした課題にいち早く気づき、経営悪化に陥らないため早期に対策を講じたり、必要な意思決定を下すことが求められます。
経営計画の策定・見直しに活用できる
経営分析によって明らかになった客観的なデータは、経営方針の策定や見直しに役立ちます。
経営方針は組織全体が従う重要な指標です。
その内容に納得感が得られないと組織で一体的に経営が進められなくなってしまうでしょう。
経営分析の結果は客観的なデータとなるため、経営方針の内容に納得感を持たせられやすく、組織が一体的に動くための理由としても役立ちます。
投資の判断材料になる
経営分析の結果は社内だけでなく、社外でも活用されます。
その代表例が、金融機関や投資家からの資金調達です。
金融機関や投資家は、資金が回収できる見込みのあるリスクの低い企業へと投資します。よってすべての企業が必ずしも融資を受けられるとは限りません。
そこで、経営分析で経営状況が客観的に提示でき、かつ経営リスクが低いことがアピールできれば投資面でも有利になるのです。
自社の経営状況を把握し、弱みの改善を進めていけば、資金調達が受けやすくなる状態を作っていけます。
現状分析・将来予測が可能となる
データをもとに精度の高い現状分析や将来予測ができるようになることです。
ビジネスでは市場の動向や売上推移を予測することが欠かせません。
しかし、そのような未来の情報は不確実性が高く、確度の高い予測をすることが難しいのが現状です。
その悩みを解決するのがデータです。
各データの関連性や因果関係などを分析することで、高度な予測結果を得ることができます。
そうすることで、市場のシェア率の拡大や利益向上など、またそれらに繋がる施策の検討・実施ができるようになります。
問題点やビジネスチャンスを発見できる
見落としていた問題点やビジネスチャンスを発見できるようになることです。
今まで、抱えている問題の解決方法や新しいビジネスは経験や勘に頼ったものが一般的でした。
しかし、「情報化社会」「IT化」など時代の流れが加速し、従来の経験則や勘だけだと、市場に取り残される可能性が高まりました。 そこで必要となるのがデータを活用した、新しいインサイト(洞察)の発見です。
データ分析とは、さまざまな型や組織内に散らばっているデータを集約・分析し、そこから新たな洞察を導きます。分析を行うことでデータ同士の相関関係や因果関係を発見することができるため、人がなかなか続かない問題点やビジネスチャンスの発見ができる可能性があります。
意思決定のスピードを上げることができる
意思決定のスピードを上げることができることです。
経験や勘はその人の主観が絡むため、それをもとに意思決定する際は多くの人とすり合わせる必要があり、時間がかかりました。 もちろん、時には経営者の長年の勘は経営をプラスの道へ導いてくれることもあるでしょう。
しかし、現代の企業活動では加速する時代の流れに取り残されないようにスピーディーに意思決定を行うことが大切です。
データは長年の売り上げや市場の動向から客観的かつ信頼度の高い情報を素早く提供し、意思決定のサポートをしてくれます。
数字で経営するための手順
とはいえ、経営に数字を使いこなすといってもなかなか難しいように思えます。
そんな時は、日常の経営を思い出してみましょう。
例えば、先ほども取り上げた「売上を増やしていく」ということから考えてみます。
目標の数値化
まず、「売上を増やしたい」という漠然としたものではなく、「〇ヶ月で毎月の売上を現状から100万円増やしたい」
というように、目標を数値化しましょう。
繰り返しになりますが、目標の数値化は非常に重要です。
定量的な目標を設定することで、目標が具体化されるだけではなく、実際に結果が出た場合のギャップを知ることができるようになります。
そうすると、何がどれくらい足りなかったのか?を振り返ることができます。
目標の数値化によってスタッフでの共有も具体化されるため、このPDCAサイクルをチーム全員で取り組むことができるようになります。
まずは、毎月の目標を数値化していくことからはじめてみてください。
重要なのは経営数値を読むこと
このように経営イメージを数値化することは小規模事業や中小企業が売上を伸ばし、利益を出して、経営を安定化させるために欠かせない経営手法です。
でも受注が増えても、お客さんの数が増えても、お金がなくなってしまえばその時点で終了です。
ですので、お金の数字もきっちり使いこなしていかないと、経営は継続できません。
まとめ
売り上げを伸ばしたいと思った時には、焦って答えを見つけ出して行動しても良い結果を得られる可能性は低いです。
それよりも、しっかり現状の経営数値を分析して、状況を理解するところから始めましょう。
より専門的な数値分析を行いたい方は、ぜひ翔彩サポートへご相談ください。

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。