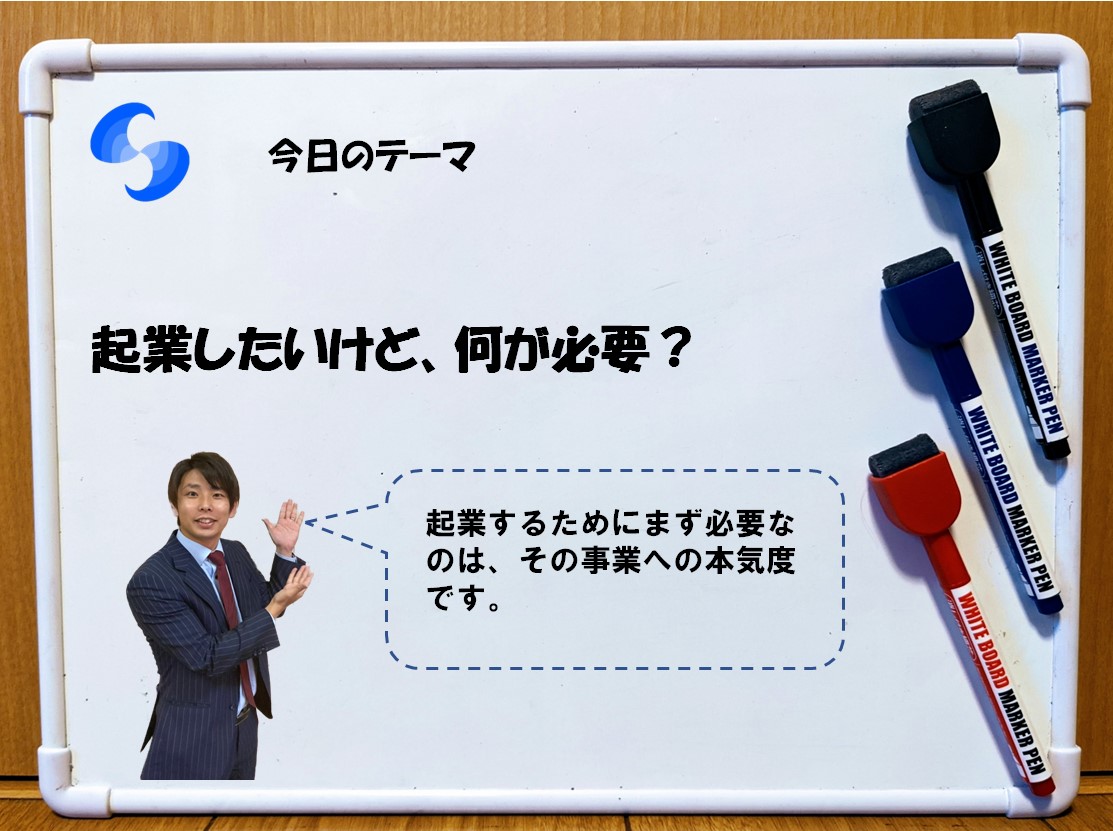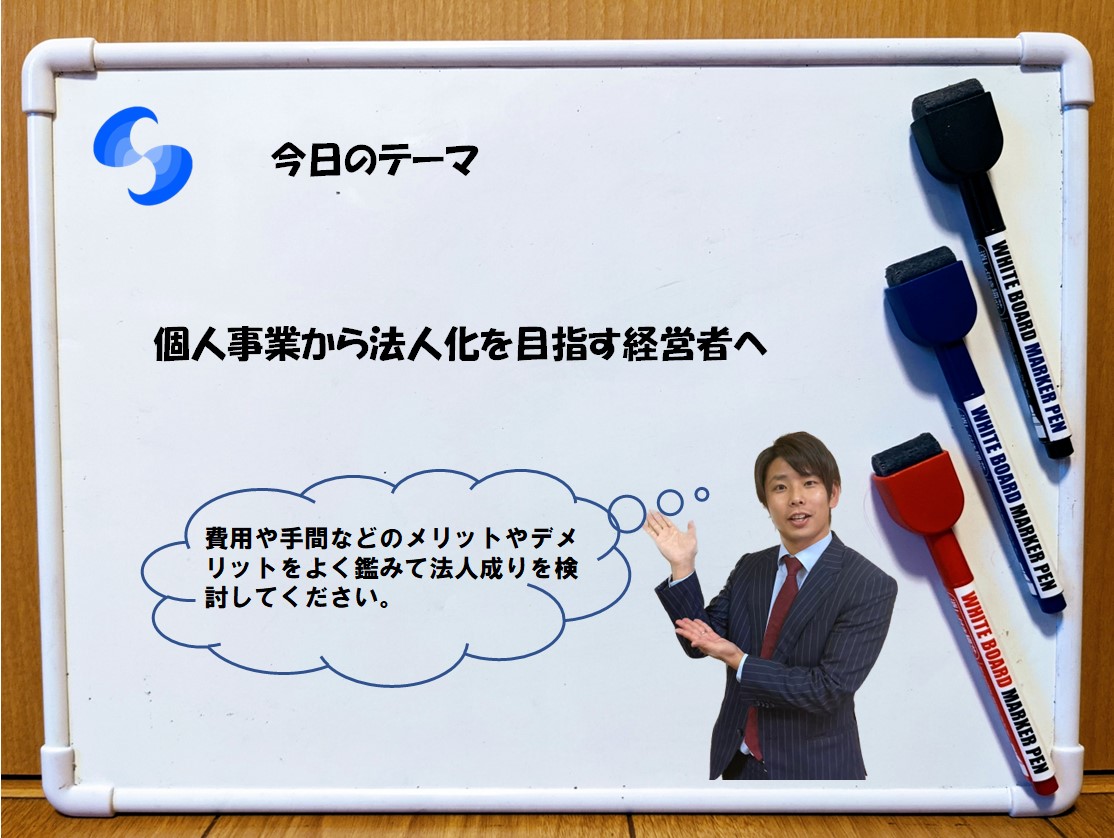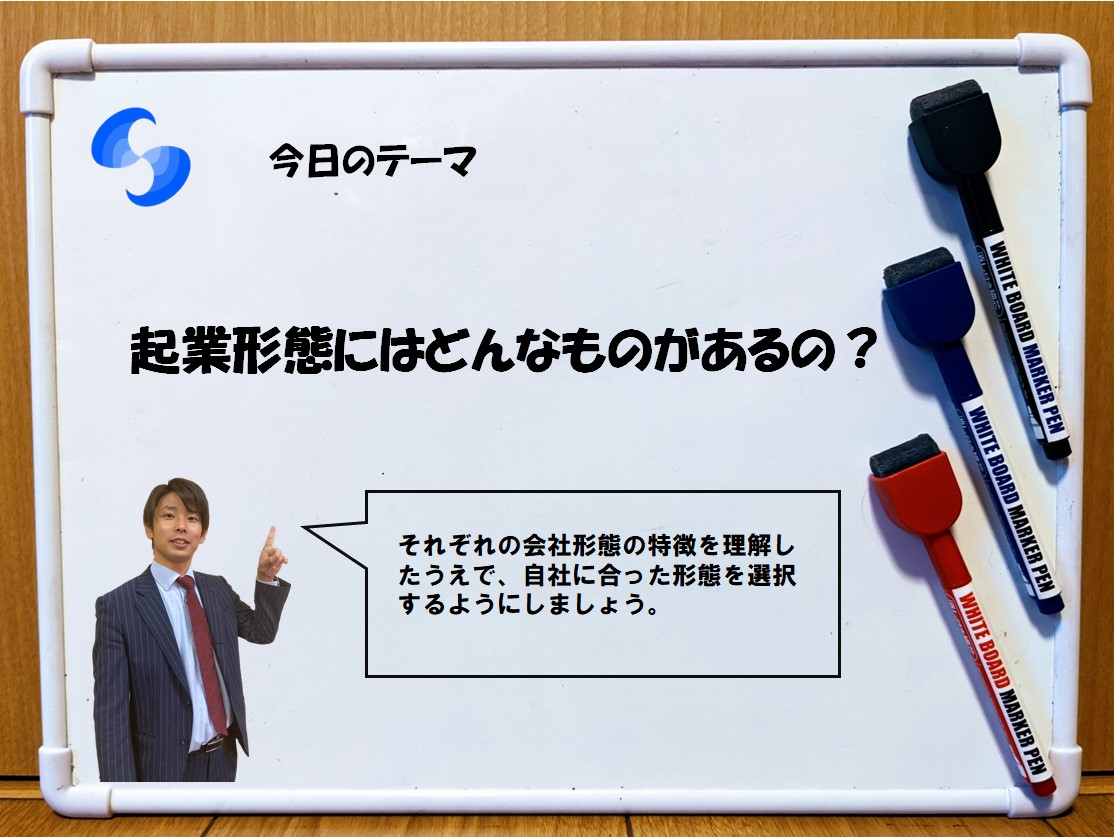起業したいけど、何が必要?
起業したいと思っているけど、何から始めたら良いかわからない
自分は一人で起業して、上手く経営できるか不安しかない
これから起業を志している方の中で、このような不安を抱えていませんか。
【起業する】ことは、とても簡単で誰にだってできます。
例えば、資本金・発起人をそろえ、登記の手続きさえすれば「会社」はできます。
極端な話、資本金が1円からでも始められますし、起業に必要な準備の資金額は低下している傾向にあります。
さらに、起業を支援するために様々なクラウドサービスや公的な創業支援も増えており、資金調達の方法も増えています。起業は、医者や弁護士・税理士などのような国家資格を必要とするわけではありませんので自らが「起業したい」と思えば誰でも起業することできます。
ただし、起業することと「起業を成功」させることは全く違うことを理解してください。中には起業しただけで、成功した気になっている人がいますが勘違いしないようにしましょう。
日本で起業する人の1年目で約3割が廃業すると言われています。この最初の壁を乗り越えて軌道に乗ると事業基盤を確保して安定させることができるでしょう。重要なのは起業初期をいかに早く、突破できるかです。
起業とは?
起業とは、事業を起こして新たなサービスを生み出していくことです。
世の中でみんなが不便に感じていることや悩んでいることを解決する、または利便性を向上させていくために、新たに会社を設立したり、事業を作ることを「起業」といい、起業した人を「起業家」といいます。
「もっとこういうものがあったら便利なのに(価値や市場の創出)」「こういうサービスがあれば不自由しないな(ユーザーペインの解消)」といったアイデアをもとに起業した起業家たちのおかげで、私たちの生活は支えられています。そして、今当たり前にある有名な大企業も、昔は起業家が作ったということを忘れてはいけません。
今ある日本の大企業は100年以内に設立された会社がほとんどです。そこには当時大変な状況でも起業した「起業家」がいたということです。
また、起業家がつくった企業の利益やその従業員へはらう所得の税金によって、日本の国は支えられています。つまり、起業家がいなければ、世の中のサービスや日本の経済活動は存在しませんでした。
そのくらい、起業することはすごいことなのです。
起業する理由を明確にする
「起業を成功」させるために、まず大切なのは、起業の「目的」を明確にすることです。
近年では、SNSの普及もあり誰もが有名人になれる世の中になっています。有名になれたから事業が成功すると思っては大間違いです。
「とりあえず何かの社長になりたい」、「今流行りの事業なら自分がしても儲かりそう」、「会社で働きたくないから起業したい」などという半端な気持ちで起業しないでください。
起業は「目的」を達成するための手段です。これを忘れてしまうと、起業しただけで満足してしまい、モチベーションの維持が難しくなります。
自分が起業する理由を考えてみてください。
「なぜ起業するのか」、「ビジネスを通して、何を実現したいのか」、「この事業を通して、自分はこうなりたい」を突き詰めましょう。
経営者になれば、必ず孤独と戦うことになります。経営者が孤独と言われる所以は経験したら分かります。それまでは、理解できない事でしょう。いつか孤独を感じた時にビジネスを続ける上で折れない起業の「軸」が定まれば、どんな困難にも立ち向かっていけるはずです。
起業するときの流れ
起業する場合の前の準備から事業開始するまでの流れを解説します。
- 目的や軸を考える
- 事業内容を決める
- 起業計画の具体化
- 資金を集める
目的や軸を考える
自分がなぜ起業したいのか、その目的や理由をしっかり考えておくことが大切です。これは起業するずっと前から考えられるはずですし、その気持ちが強ければ強いほど良いです。
単なる思い付きだけでは、起業してもモチベーションが長続きしない可能性があります。
事業計画を立てる
起業の目的や理由が定まったら、次に事業計画を立ててみましょう。
具体的には、下記のようにビジネスの内容と現実的な計画、ターゲットを決めていきます。
■何をやるかを決める
事業計画を立てるうえで第一に考えなければならないのは「起業して何をするか」ということです。
例えば、扱う商品やサービスの他、その特徴や価格などを決めることが大切です。自分の好きなことや強み、得意なこと、社会に求められていることなどを整理して、どのような事業を行っていきたいのかを明確にしましょう。
■誰にどのように販売するかなど収入源を決める
ビジネスは、いくら自分が強くやりたいと思っても、ニーズとマッチしなければ売上は立ちません。起業して何をするかが決まったら、その商品やサービスが誰に向けたものなのかペルソナをきちんと設定しましょう。
■ターゲットへの訴求力や競争優位性を調査する
ビジネスで提供する商品には、物やサービス、知識、技術などさまざまな選択肢があります。いずれにしても、市場ニーズとマッチしなければ、思うような利益を出すことは難しいでしょう。
また、ターゲットの興味を引くには、競合他社との差別化を図る必要があります。その際の分析方法のひとつとして、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4つのカテゴリーから事業戦略を検討する「SWOT分析」をしてみてください。
資金計画を立て、資金を集める
起業形態が固まったら、起業するための資金を確保しましょう。
起業資金を考えるうえでは、自分が始めようとしているビジネスにどれくらいのコストがかかるのかを把握しておくことが重要です。起業に必要な資金は、大きく分けて「設備資金」と「運転資金」の2つです。
それぞれに該当する主なものは下記のとおりです。
設備資金
設備資金とは、店舗やオフィスを借りる場合の敷金や礼金、内装費、家具の他、固定電話やインターネット回線などのインフラ、製造設備など、設備にかかる費用のこと。
運転資金
運転資金は、家賃、光熱費、仕入れ代金、外注費、通信費、広告宣伝費など、事業を運営していくうえで継続的にかかる費用のこと。設備資金と運転資金を分けて考えることで、継続的に必要な費用を割り出すことが可能です。
起業したばかりのころは、安定した売上があるとは限りません。
事業の内容や規模によって異なりますが、一般的には、運転資金の3か月分程度は確保しておいた方がよいといわれています。
また、起業する際には、事業に使える自己資金を確保してスタートさせましょう。融資交渉の際にも自己資金があった方が交渉を有利に進められるケースがほとんどですし、自己資金を準備していた方が起業に対する本気度を金融機関に訴えられるでしょう。
起業形態を決めて、会社設立や開業の手続きを行う
起業するには、法人として会社を設立するだけでなく、個人事業主として事業を起こす方法もあります。自分が始めたいビジネスに合った起業方法を選択し、必要な手続きを進めましょう。
個人事業主と法人のどちらにするか決める
起業する際に、個人事業主でスタートするか会社を設立するかで迷うことがあるかもしれません。
法人と個人事業主には、それぞれメリットとデメリットがありますが、両者の大きな違いの1つは課税される税金の種類です。税金の種類が違うことにより、同じ利益でも納める税金の額が変わってきます。
個人事業主と法人で納める税金にどれくらいの違いがあるかを把握し、起業スタイルを検討する際の参考にするといいでしょう。
そのためには年間の売上や経費がいくらくらいなのか数値に落とし込むことが必須です。
会社を設立するにはさまざまな手続きが必要ですが、個人事業主として開業する場合は、開業から1か月以内に、所轄の税務署に開業届を提出すれば手続きは完了です。
会社設立に必要な手続きを行う
現在、日本で設立できる会社の形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。設立する会社形態を決めてから、それぞれに必要な手続きを行いましょう。
例えば、株式会社を設立する場合の流れは、次のようになります。
株式会社設立の手順
- 会社の概要を決める
- 法人用の実印を作成する
- 定款を作成し、認証を受ける
- 出資金(資本金)を払い込む
- 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
上記の手順のように、会社設立の手続きは必要書類の作成や申請、認証などに意外と時間がかかるものです。
希望する起業時期からスケジュールを逆算し、余裕を持って計画を立てることが大切です。
また、会社を設立する場合、起業資金とは別に設立手続きのための費用がかかります。株式会社か合同会社かによっても設立費用は異なるため、会社形態に合った設立費用をチェックして用意しておきましょう。
起業の手続きを手軽にする方法は?
起業までの一連の流れを把握しても、実際に書類の作成を進めると不安になったり、わからないことも出てきたりするでしょう。特に、法人として会社を設立する場合は、申請書類の作成に手間や時間がかかり、戸惑うことが多いかもしれません。そんなときにおすすめなのが、翔彩サポートの伴走型経営コンサルティングサービスです。
融資に関しても金融機関の交渉までを一緒に行います。
起業した後、スタートで転ばないための方法
失敗しない起業を実現するためには以下のようなものがポイントになります。
- 経営資源の確保
- マーケティング以外に経理や経営に関するスキルの習得
- 固定費を抑えながらスモールスタートで始める経営
経営資源の確保
経営資源とは、事業を進めていくために必要な人材や、資金などのリソースのことです。
最近では「時間」や「知的財産」も経営資源だといわれています。経営資源が確保できていなくても、起業自体は可能です。しかし事業体制を強化するためには、経営資源を揃えておくことが大切になります。
起業するためにはまず資金調達が必要になりますが、それ以外にもメンバーやスキル、オフィス等も必要になります。事業体制を強化するためには多くのリソースが必要になるため、どういった方法により経営資源を確保するか検討しておくといいでしょう。
マーケティング以外に経理や経営に関するスキルの習得
事業を進めるうえではマーケティングの知識はもちろん、経理や経営に関するスキルも習得する必要があります。マーケティングに関する知識があれば、商品やサービスが売れる仕組みを構築することができます。しかし経理の知識がなければ会社の財務状況が把握できず、経営の知識がなければ事業を続けていくことが難しくなってしまいます。
いずれも起業に欠かせない知識であるため、代表者として習得しておけば役立つ場面が来るのではないでしょうか。場合によっては、経理や経営に詳しい人材を登用する方法も考えられます。
固定費を抑えながらスモールスタートで始める経営
事業が軌道に乗るまでは、コストを抑えながらスモールスタートで経営していくことを意識しましょう。初期投資が大きすぎると回収が難しくなってしまうだけでなく、事業から撤退するタイミングを見誤ってしまう可能性があるからです。店舗の内装費や人件費などのコストを抑えながら経営状況を分析して、リスクヘッジをしましょう。
まとめ
起業するためにまず必要なのは、その事業への本気度です。
起業する理由を周囲の人に説明できるような言葉にまとめることができれば、社会的意義のあるビジネスへと進みます。
資金調達には念入りに準備をし、事業をスムーズにスタートさせましょう。
資金繰りに悩む時間は売上を伸ばそうとする経営者の邪魔になってしまいます。
上記以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。