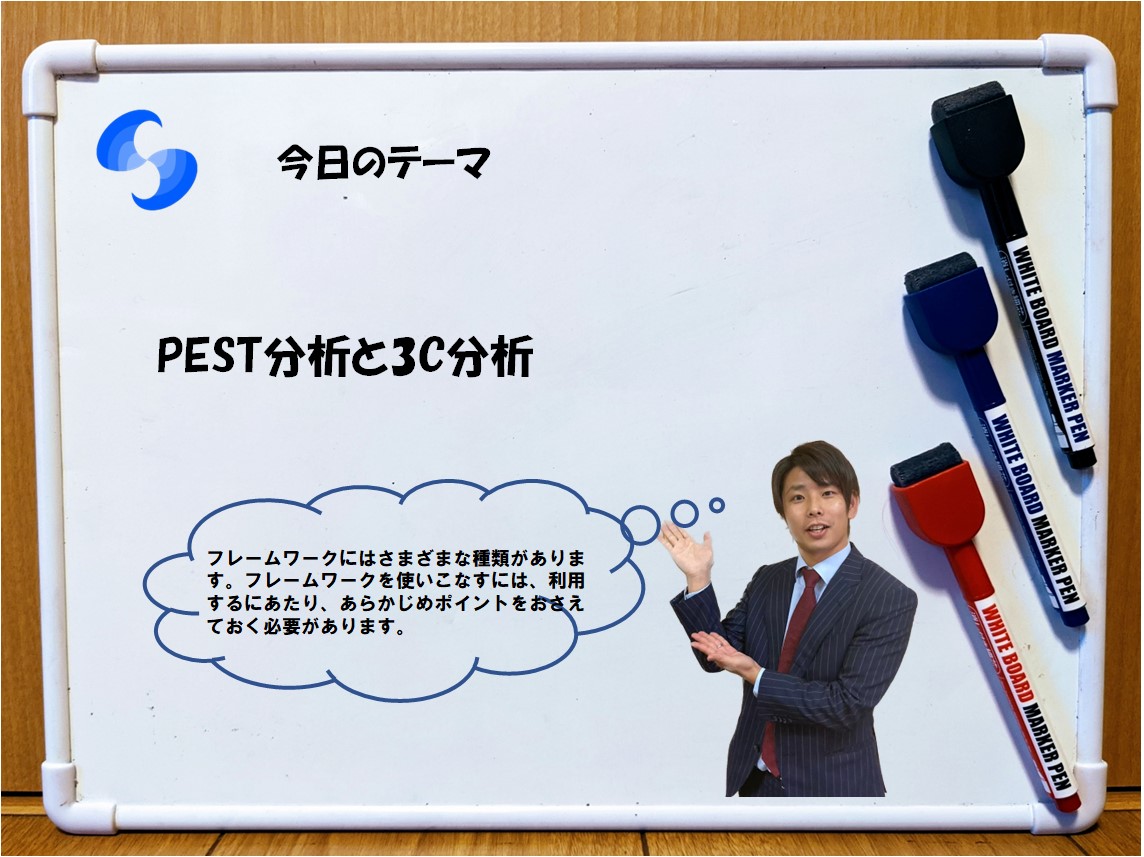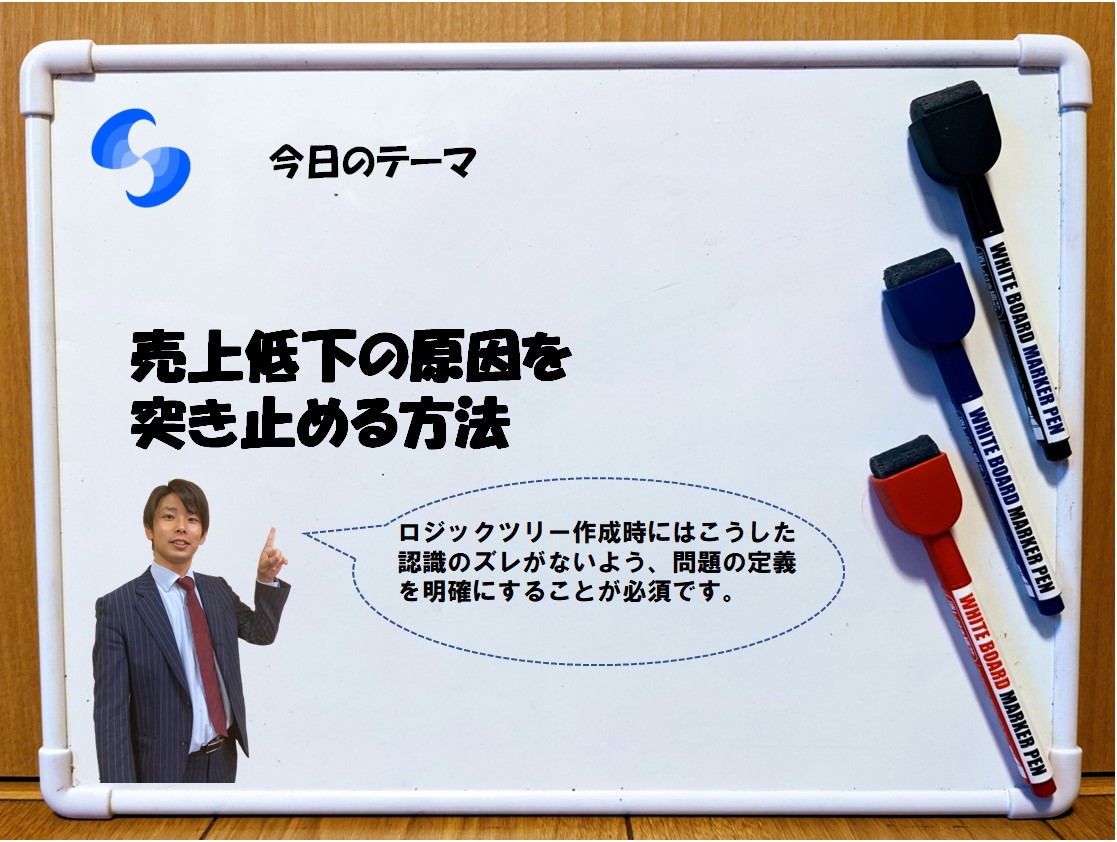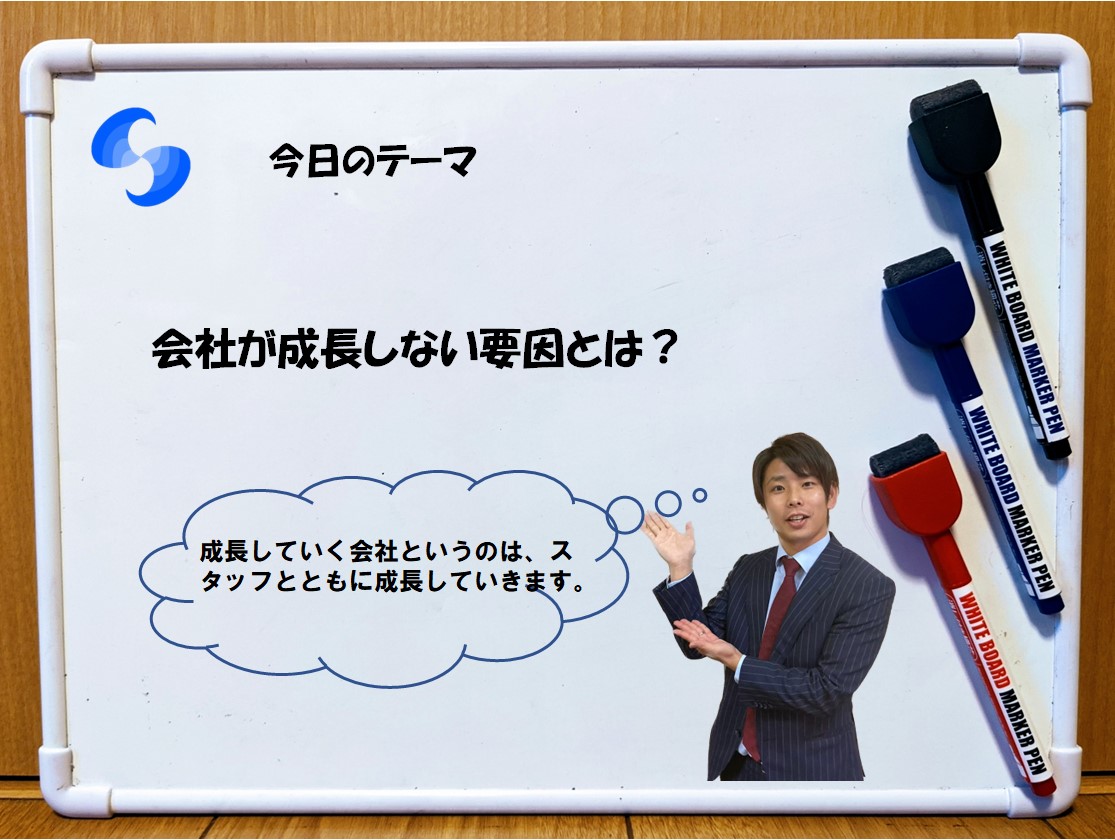PEST分析と3C分析
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「PEST分析と3C分析」について解説します。
前回は売上低下を突き止める方法としてロジックツリーをご紹介しました。
今回はPEST分析と3C分析についてお話します。
PEST分析って?
PEST分析とは、自社を取り巻く外部環境が、現在もしくは将来的にどのような影響を与えるかを把握・予測するためのフレームワークのことです。「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」という4つの外部環境を取り出し、分析対象とします。
社会情勢や経済状況など自社での制御が難しいマクロ環境を分析できるため、市場の将来性や変化を予測したいときに役立ちます。
政治:Politics
- 国際情勢(戦争、紛争を含む)
- 法律、条令、条約の改正
- 判例
- 規制緩和、強化
- 税制の変化
- 補助金制度、交付金制度の変化
- 政策の変化
- 政権交代
- マニフェスト
経済:Economy
- 経済成長率
- 景気動向
- 株価の変化
- 金利の変化
- 為替動向の変化
- 原油価格の変化
- 雇用情勢(失業率など)
- 金動向の変化
- 消費指数の変化
社会:Society
- 人口動態の変化
- 社会問題
- 世論の動向
- 流行
- 活習慣
- ライフスタイル
- 教育制度の変化
- 宗教
- 倫理
技術:Technology
- インフラ整備
- 技術革新
- 特許
- イノベーション
PEST分析の目的
PEST分析は、経営学者でマーケティングの第一人者で、ノースウェスタン大学ケロッグビジネススクールの教授であるフィリップ・コトラー氏によって提唱されました。
コトラー氏は、自身の著作『コトラーの戦略的マーケティング』において、「調査を行わずに市場参入を試みることは、目が見えないのに市場に参入しようとするようなもの」と述べており、環境分析の重要性を説いています。
これまでに成功を収めてきた事業・製品のほとんどは、世の中の変化・流れ・トレンドを味方につけてきたと考えられています。外部環境の変化に伴い、時代に即した事業・製品に変えていくことで、生き残りを目指せるのです。この外部環境(特にマクロ環境)を把握し、自社への影響を図るフレームワークの1つとして、PEST分析が位置付けられています。
PEST分析のメリット
PEST分析を行うメリットは、自社ではコントロールできないマクロ環境を整理・分析することにより、自社が成長するための機会を把握でき、リスクを未然に回避できることです。
PEST分析のデメリット
PEST分析のデメリットを挙げるならば、汎用性の高い分析ではないこと、つまり、必要とされる頻度は必ずしも高くはないということでしょう。さらに、以下の点に注意しましょう。
①PEST分析に限らず、フレームワークの内容を埋めさえすれば分析できたと安心しないこと。
②経営課題の解決のために、必ずしもPESTの4要因全ての分析が必要とは限らないこと。⇒ 意思決定に必要な調査課題において、優先順位の高い要素のみで環境分析する柔軟性も必要です。
③あくまでも背景情報なので、経営層へ報告する場合、すでにわかっている“前置き”として軽視されることもあり、プレゼンテーションの流れに合わせて、柔軟に報告資料を作成する必要があります。
3C分析
3C分析は、マーケティング環境を分析するフレームワークです。外部環境として「市場・顧客」「競合」を、内部環境として「自社」を分析の対象としています。
Customer(市場・顧客)
- 業界の市場規模
- 市場の成長性
- 顧客ニーズ
- 顧客の消費行動・購買行動
Competitor(競合)
- 競合各社の現状シェアと推移
- 各競合の特徴(採用している戦略・保有リソースなど)
- 競合の業界ポジション
- 新規参入・代替品の脅威
- 自社が特に注意すべき対象となる競合企業(主要顧客層、商品特性が似ている、など)
- 注意すべき競合対企業と特徴と今後想定される行動(自社への対抗手段など)
Company(自社)
- 自社の企業理念・ビジョン
- 既存事業・自社製品の現状(売上、シェア、商品ラインナップ、戦略、など)
- 既存ビジネスの特徴、強み、弱み
- ヒト・モノ・カネの現有リソース、強み、弱み
- 資本力・投資能力
3C分析の目的
3C分析の目的は、KFS(Key Factor for Success)を見つけることです。
KFSは具体的には、「価格の安さ」「多くの顧客に商品を届けられる販売網」などのように絞り込まれます。
こうしたシンプルなKFSを正しく導き出すために、企業は経営判断ができるレベルであらゆる角度から3Cを分析する必要があります。
3C分析のメリット
シンプルでわかりやすい
3つのCという枠組がシンプルでわかりやすく、企業内外で合意形成するのに役立ちます。
抜け・漏れがない
3つのCという枠組みだけですが、抜け・漏れなく必要な項目をチェックでき、KFSを導き出すために役立ちます。
優先順位が明確
3C分析では検討の順番が決まっているので、優先順位を誤ることなく分析を進めることができます。
まとめ
フレームワークにはさまざまな種類があります。フレームワークを使いこなすには、利用するにあたり、あらかじめポイントをおさえておく必要があります。それが「目的の明確化」「適切な選択」「理解と共感」の3つです。3つのポイントを軸に、フレームワークを利用し成果につなげていきましょう。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。