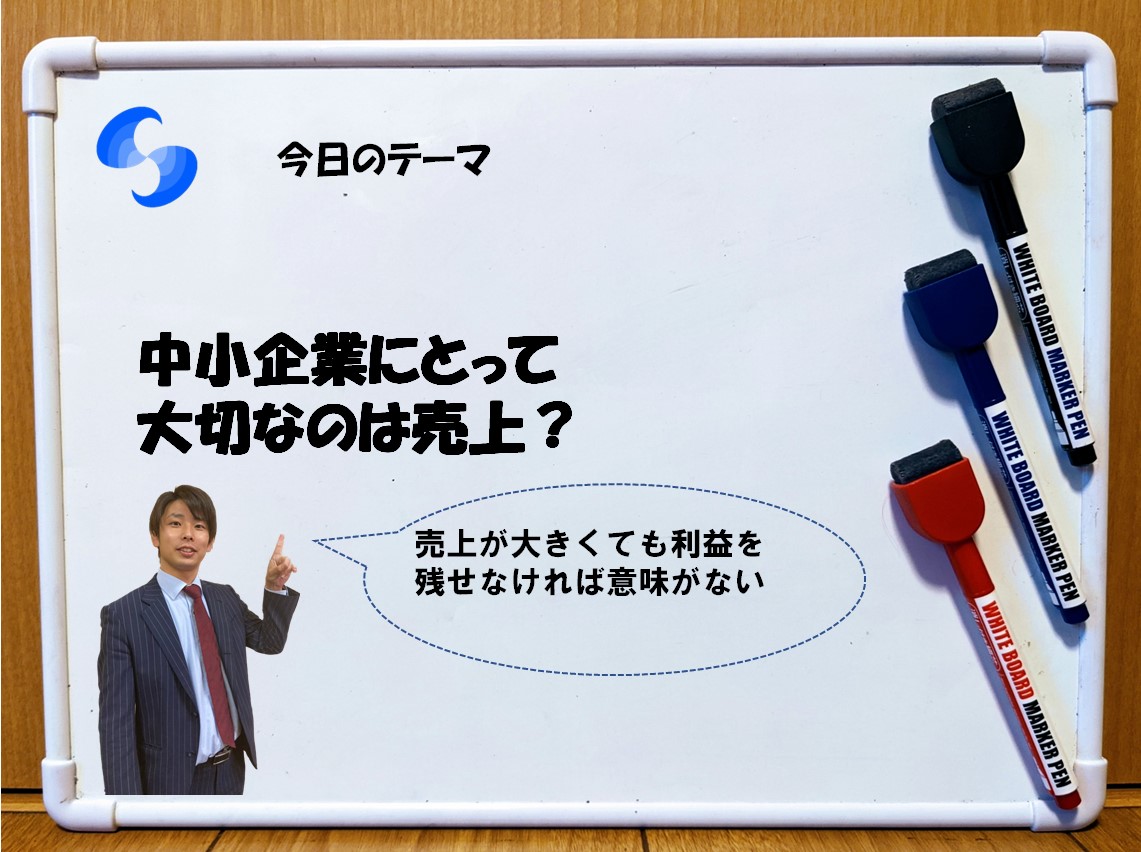売上が増えても利益が増えないのはなぜ?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
『売上は伸ばせているけど、利益が残らない現状が苦しいです』
『利益が増えていかない原因か分からず、何から対策を打てば良いか迷っています』
『どうやって売上と利益を伸ばしていっていいかそ、その道筋が見えません』
売上を伸ばしたい・利益を伸ばしたいと考えている方からこのようなご相談をいただきます。
実際に、売上と利益はイコールではないことを理解していても、経営は売上を伸ばせば何とかなると思っている方も多いです。
そこでこの記事では、増収減益が起こる理由と実例を、開業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。
これから売上・利益をともに伸ばしていきたいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。
【事例】規模に合った利益を確保できなかったことで倒産の危機を迎えた企業の事業再生
この事例は、思ったような利益を伸ばすことができなかった企業の事業再生を行ったものです。
売上の最大化を図りつつも、不要な経費をどのように削減していった経緯を記していますので、ぜひご覧ください。
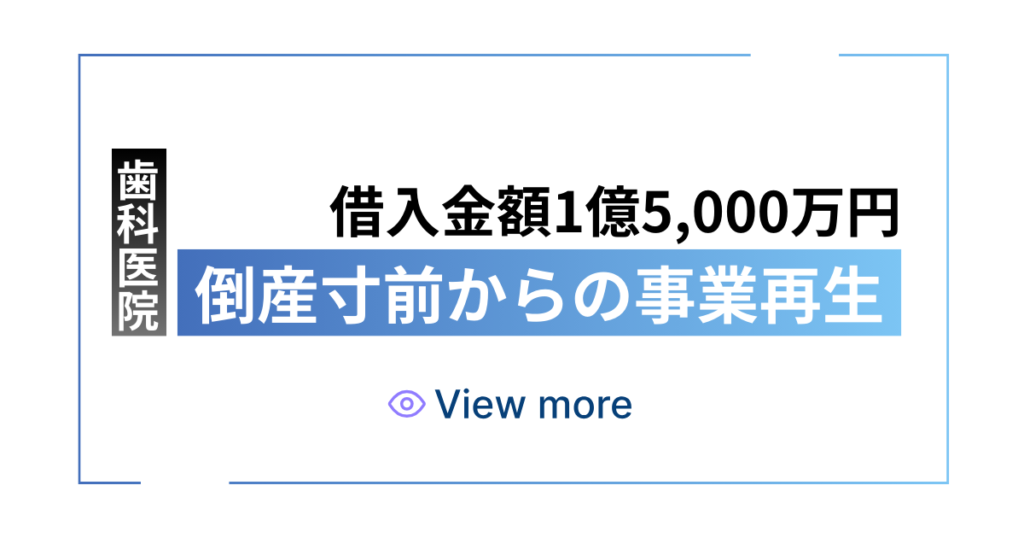
増収減益とは?
営業活動をして売上の数、量を増やしているのに、なぜか利益は思ったように増えていない、または減ってしまったということはありませんか?
このような状態は増収減益と呼ばれます。
また、これとは逆に、減収増益という売上は減少したが利益は増加した、という状態もあります。
売上と利益は必ずしも一緒に変動するとは限りません。
増収減益はなぜ起こる?

増収減益が起こってしまう理由は、主に以下の2点です。
- 採算に合わない人件費
- 売上総利益率の低さ
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
採算に合わない人件費
ひとつ目の原因は、人件費がかかりすぎているケースです。
もしかすると、従業員のみなさんが残業して頑張って売上高や売上総利益を増やしても、残業による給料の増加の方が上回ってしまっているのかもしれません。
残業による売上総利益の増加<残業による給料の増加
この場合、残業をしない方が営業利益を残せます。ビジネスを行う上では、様々なコストがかかってきます。それは人件費だけでなく、オフィス代や備品代も含まれます。
コストを完全にゼロにするのは難しいですが、不要なところにかける必要はありません。
「現在どこにどのようなコストが発生しているか」「それぞれの費用対効果は適切か」などの視点を持って精査すれば売上を維持したままコストを削減することができ、利益率の向上に繋がります。
売上総利益率の低さ
もうひとつの原因は、「売上総利益」そのものが少ないケースです。
もしも、売上総利益が少ないと感じたら、同業他社の売上高総利益率と比較してみるとよいでしょう。
売上総利益率が低いときにチェックしたい項目は以下の3つです。
過度な安売りをしていないか
売上を伸ばすために価格を引き下げ、市場での競争に応じると、売上が増えても利益率が低下する可能性があります。価格競争は、会社が利益を維持できるかどうかに大きな影響を与えることがあります。
適正な金額で仕入が行えているか
売上が増えても、同時に原材料費や生産コスト、流通コストなどが増加することがあります。
これにより、増えた売上がコストの増加に追いつかず、利益率が低下することがあります。
ただ、業種や商品種別によって原価率はある程度一定に保たれているため、原価率が高いせいで利益が出ていない場合は改善が難しいかもしれません。業種を変えたり、より安い仕入れ値をつけてくれる業者を探す必要があります。
あるいは、商品価格を上げることも利益改善手法の一つです。
しかし、値段を上げるというのはイコール商品品質やサービス品質の増加も期待されることになるため、場合によっては難しいところでしょう。
効果的なコスト管理が重要です。
在庫管理がきちんと行えているか
生産が需要を上回り、在庫が過剰になると、在庫の保管や削減のためのコストがかさみ、利益が減少することがあります。
この3つをもう一度確認してみましょう。
削減できた経費はそのまま会社の純利益になります。
コスト削減は社員一人一人の心がけで実現されるといいますが、確かに規模が大きい会社であるほど、取り組みの成果は大きいでしょう。
ですので、コスト削減は単なる心がけにとどめず、目標を明確に設定した上で、成果を可視化しながら計画的におこなっていくことが必要です。
減収増益ってどんな状態?
「販売不振で売上収入は減ったのだが、原材料の仕入価格が下がった」や「部門縮小のために人件費総額が削減され、その結果として利益が増加した」というようなことです。
売上は、利益をあげるための手段ですから、減っても構わないわけではありません。
残った事業や、新たにはじめる事業で、売上を増やせるかどうかが重要です。
また、必要な費用を削って減収増益になる場合もあります。費用のなかには、研究開発費など、必ずしもすぐに利益に結び付かなくても、将来の利益につながるものもあります。
増収減益と減収増益はどっちがいい?
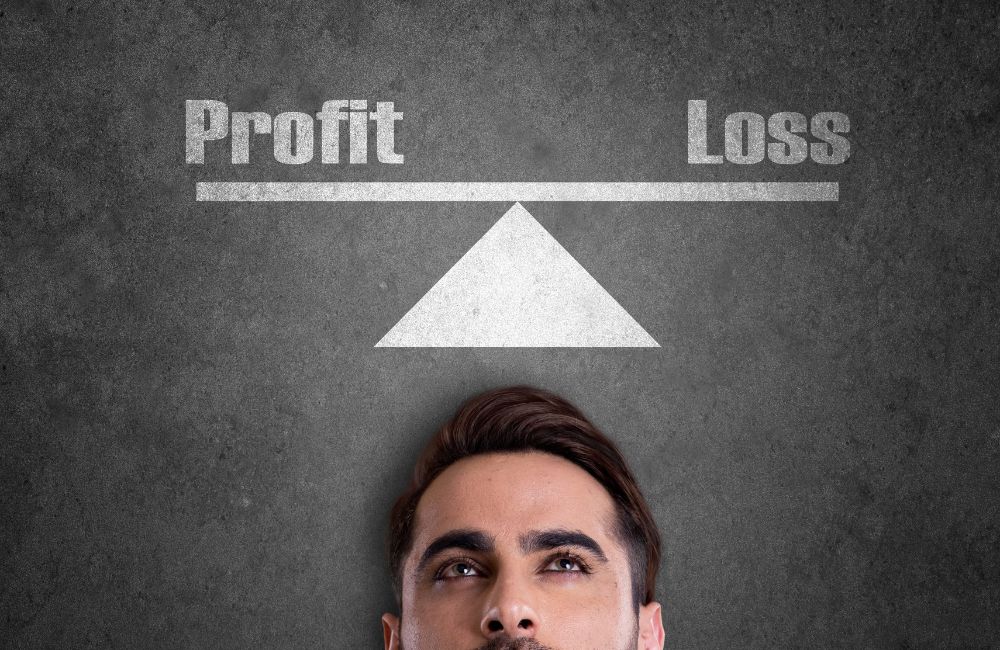
この二つに良し悪しはなく企業活動の局面に過ぎません。
事業展開の局面ごとに損益状態というのは、いくらでも変わります。
新規事業をやるにあたり新商品への投資や販売促進のために広告宣伝をすれば、費用が先行しますし、そうなると、新商品は売れるので売上は上がるけれども、経費がかさんでしまうという増収減益の状態になります。
また、成立したマーケットの売り上げと利益が落ちた後、落ちた売上に合わせて不採算部門などを整理したり、統合したりして経費を削減すると、減収増益になるでしょう。
増収減益は、会社が成長のために新たなチャレンジをしているような印象を受け、減収増益は、リストラとか経費削減という会社規模を縮小して今期の利益は確保できたかもしれないけど、売上規模が小さくなっていると捉える方がおおいのではないでしょうか。
とはいえ、減収増益から会社が再生していく場合も多々あるので、増収減益と減収増益のどちらがよいかは一概にいえません。
また、売上も利益も増えている増収増益なら良いのではとも思えますが、それもまた少し異なります。
増収増益の場合、経営努力はないけれど、世の中の流れでそうなった、という場合があるからです。
そんなときは、総資産は単に膨らむだけです。自己資本比率など、中身の改善にはなりません。
ただし、増収増益でも、会社体力が高まっているのなら、経営努力の要素も加わっていると考えられます。
要するに、増収増益といっても、良い場合も悪い場合もあるのです。
まとめ:売上・利益をともに伸ばしていきたいなら経営全てをサポートできる翔彩サポートまで
会社の業績には様々なパターンがありますが、それをみただけで良い悪いが決まることはありません。
しかし原因に目を向けることは大切です。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。