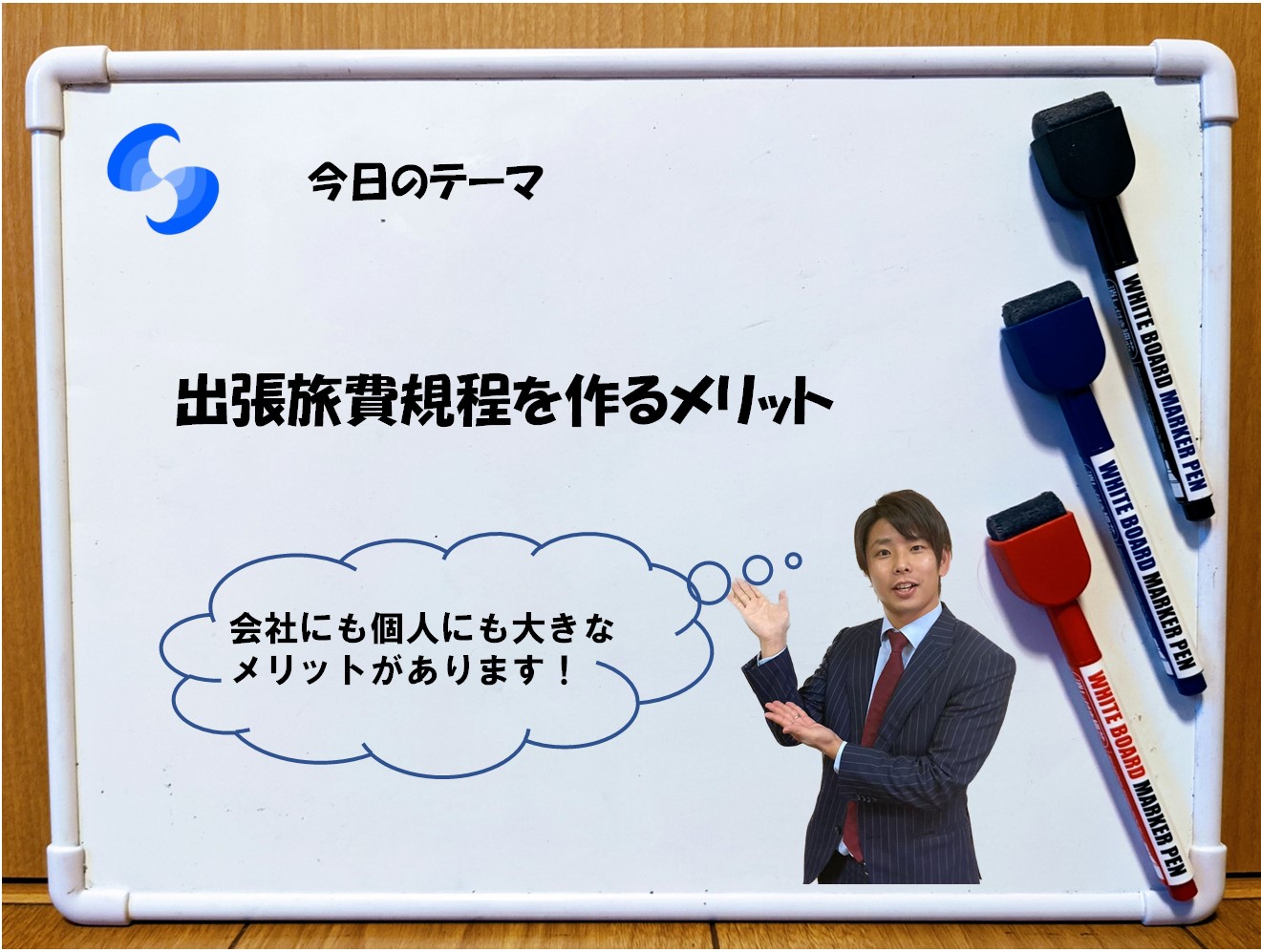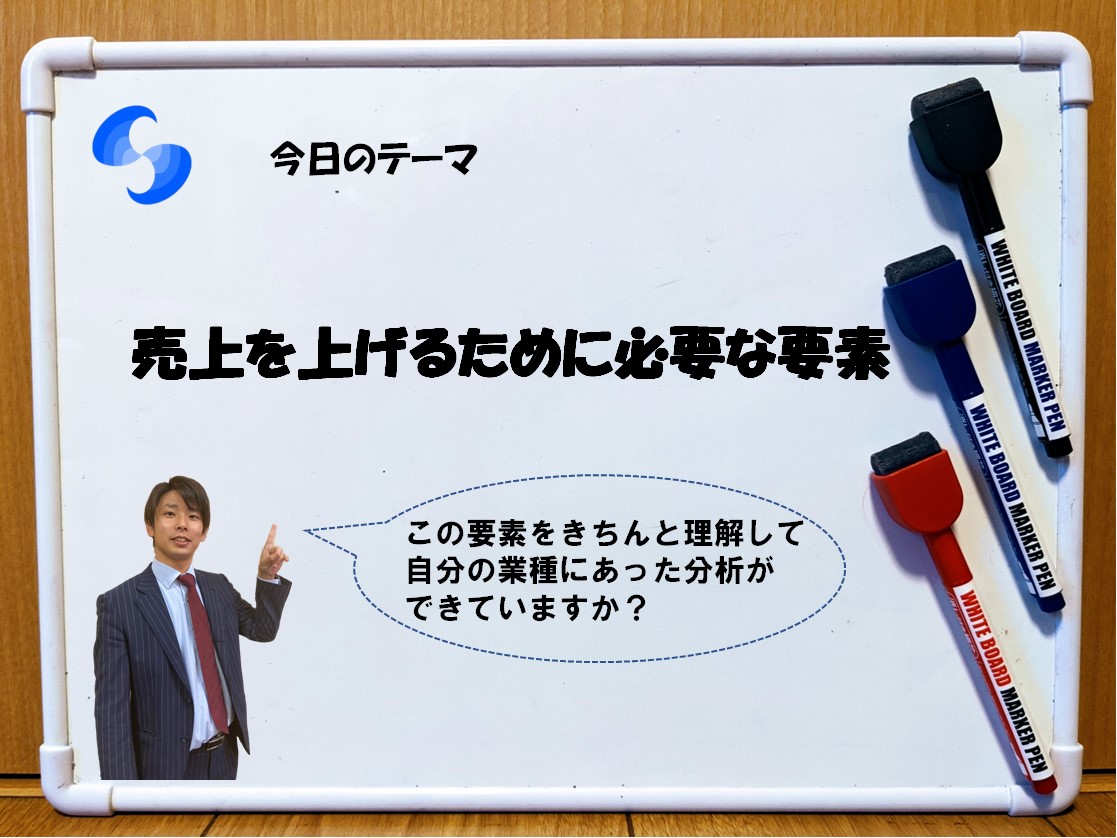年末調整をしないとどうなる?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「年末調整をしないとどうなるか」について解説します。
会社が年末調整をしなかった場合の、罰則やデメリットについて説明します。
年末調整とは?
年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収で天引きされた所得税の過不足を調整する手続きのことで、毎年行います。所得税を納めすぎた場合は還付され、不足があれば追加で徴収します。
年末調整を行う理由は、源泉徴収で天引きされる所得税額は概算だからです。
基本的に会社は、従業員に支払う金額から所得税を計算し、その分を給与から差し引いて国に納税する源泉徴収を毎月行っていますが、その時点では1年間の収入も控除額もまだ確定していません。
そのため、1年分の収入から控除額を差し引いた所得が確定した時点で、正しい所得税額を算出し、過不足なく納税するために年末調整が行われます。
年末調整と確定申告は違う?
原則として企業に勤めている場合は年末調整で所得税の過不足を調整しますが、企業に勤めず、自営業やフリーランスなどで収入を得ている人は、1年間の所得税額を確定するために確定申告をしなければなりません。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日に、納税者本人が1年間に得た収入や事業を行う上でかかった経費などを計算して申告します。
年末調整の対象となる人とは?
年末調整の対象は、会社勤めで源泉徴収があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。主に、年間を通じて勤務している人、年の途中から年末まで勤務している人が対象で、雇用形態に関わらず、正社員、契約社員のほか、パートやアルバイトも含まれます。
なお、年末調整を行う前に転職した場合は、転職先の会社で年末調整を行うことになります。その場合は、転職先に前職の源泉徴収票の提出が必要です。
年末調整の対象とならない人とは?
年末調整は、会社勤めではない人のほか、会社勤めの場合でも条件によっては対象外となる人がいます。
- 年末調整の対象外
- 自営業やフリーランスなどの個人事業主
- 給与所得が2000万円を超える場合
- 副業などで2カ所以上から給与の支払いを受けている場合
- 災害減免法の規定に該当する人
- 継続して同一の雇用主に雇用されない人
年末調整の期限に間に合わないと延滞税が発生する
年末調整で不足額を徴収した場合、翌年1月10日が納付期限です。これを過ぎると、翌日から延滞税が課税され、2カ月以上を過ぎると、延滞税の税率が上がります。
また年末調整は期限内にしたが、誤りにより所得税を少なく納税していた場合は、すぐに修正申告してください。これを税務署から指摘された場合は「過少申告加算税」がかかります。
払い過ぎた税金に対する還付金が受けられない
源泉徴収制度では、年税額よりも多く納付しているケースがほとんどです。しかし会社が年末調整をせず、本来納めるべき年税額を確定しなければ、当然ですが従業員に対しての還付もできません。
従業員が自分で確定申告をしなければいけなくなる
会社が年末調整しなかった場合は、従業員は自分で確定申告をして、年税額の過不足を清算することになります。従業員にとって確定申告をする手間は、負担が非常に大きいものです。その結果、会社への不満から退職を考える人が増えるおそれもあります。
まとめ
年末調整は所得税法で課せられた、給与支払者の義務です。故意に年末調整をしない場合、脱税とみなされることもあり、「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」、悪質な場合は「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が所得税法で定められています。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。