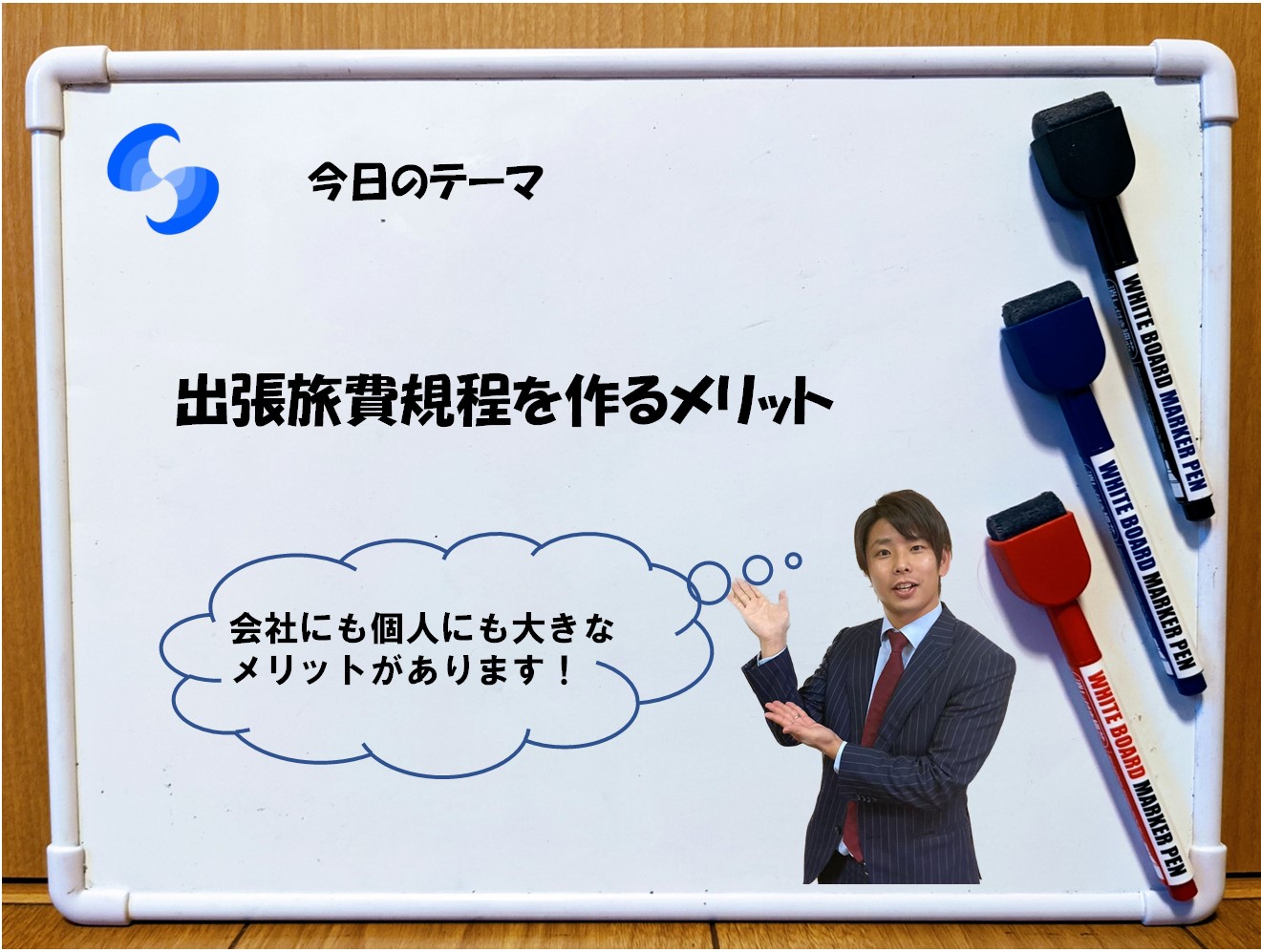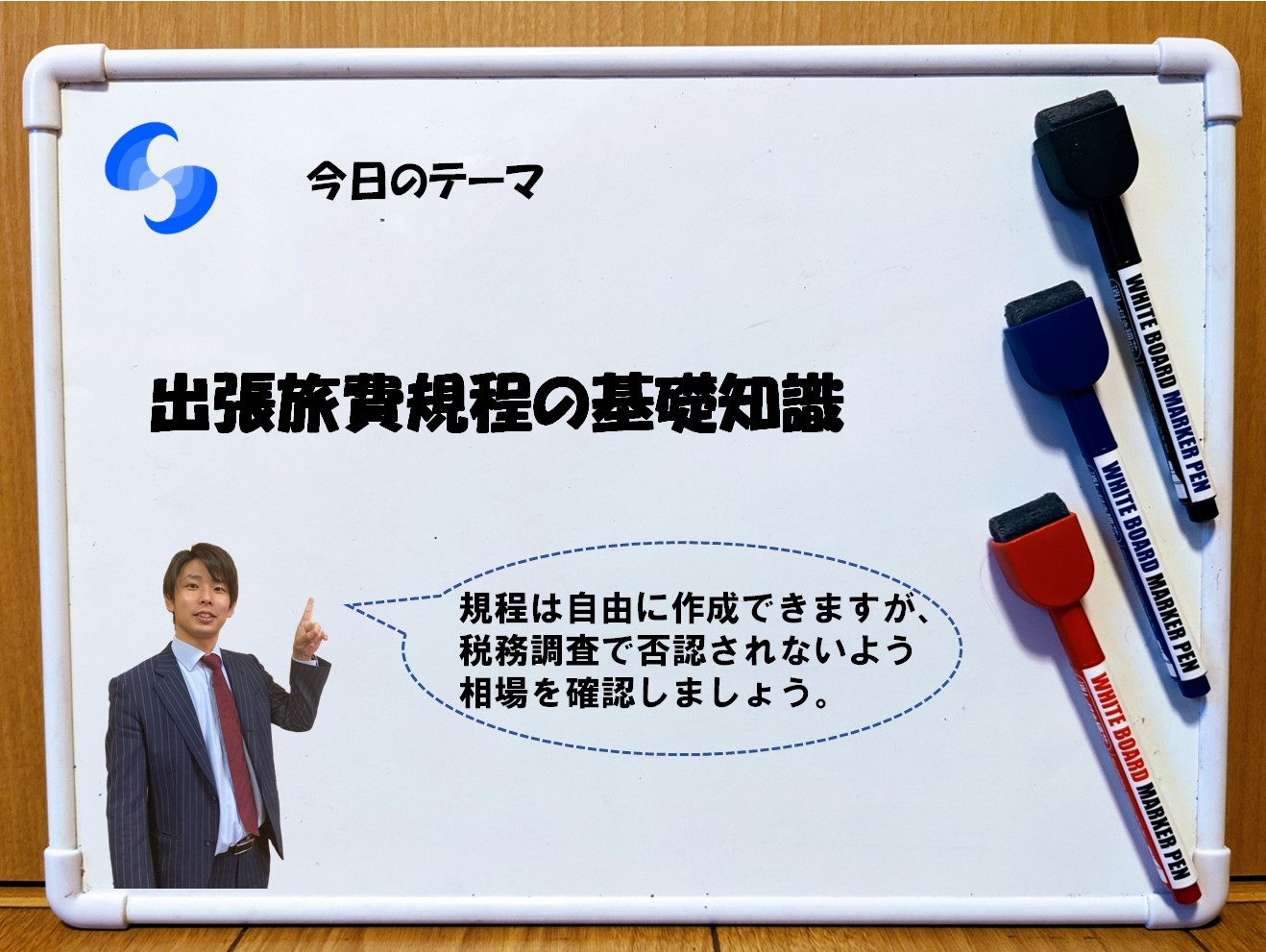出張旅費規程を作るメリット
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「出張旅費規程を作るメリット」について解説します。
出張旅費規程とは?
出張旅費規程とは、従業員が業務のために出張する際の旅費に関するルールや基準を定めたものです。
出張旅費規程を通じ、出張に関連して発生する経費の範囲や精算方法を明確にすることで、企業と従業員双方の利益を守る役割を果たします。
出張旅費規程の作成は会社ごとの任意ですが、すべての従業員に適用される出張旅費規程については、就業規則の一部として取り扱われます。そのため、出張旅費規程を整備する際には、労働基準法に則って作成することが必要です。
就業規則における出張旅費規程
就業規則とは、従業員の賃金や労働時間など、その組織内で働くうえでの労働条件や規律などを定めたルールブックのことです。
企業が作成する就業規則には、法律上、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、社内で制度を設ける場合のみ記載する必要がある「相対的必要記載事項」が存在します。
「絶対的必要記載事項」として記載しなければならない項目は、以下の3つです。
絶対的必要記載事項
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定および計算、支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
一方で「相対的必要記載事項」には、以下の8つの項目が該当します。
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- そのほか全労働者に適用される事項
出張旅費規程は「絶対的必要記載事項」には含まれないため、必ずしもすべての企業が作成する必要はありません。しかし「相対的必要記載事項」のうち、「そのほか全労働者に適用される事項」に該当することから、組織内部で出張旅費規程を作成・運用するのであれば、就業規則に記載する必要があります。
出張旅費規程のメリット
出張旅費規程とは、出張旅費や日当の扱い方を会社ごとでそれぞれルール化できます。
出張旅費規程を作成することで得られる大きなメリットが2つあります。
「手間の削減」と「節税対策」です。
メリット①精算の手間の削減
1つ目のメリットは、「出張費精算の手間の削減」という点です。
1日に多数の従業員が出張に行く会社は、毎日のように旅費交通費などの出張経費を精算する手続きが発生し、大変です。
この手間を削減するため出張旅費規程にて実費精算ではなく固定額を支給することを定め、出張旅費精算の手続きを簡略化する会社があります。
出張先の距離に応じて支給額が定められており、その金額内で旅費交通費、宿泊費を収めるようにする形です。
出張が多い企業でなくても出張の内容や経路などを確認・承認することに苦労されている上席者や、交通機関や宿泊先を一つひとつ調べて処理をする出張経費の精算の手続きで苦労している経理の方は多いと思います。
出張旅費規程はその煩雑な事務作業を減らすことができます。
メリット②会社と個人、双方の節税効果
2つ目のメリットである「節税対策」は、支払側(会社)と受取側(一般社員・役員)にそれぞれメリットがあります。
支払側(会社)
出張手当は、出張の際にかかる食事代や待機時間の喫茶代、細かな交際費や諸々の雑費について、いちいち費目を問わず一律に支給するものです。
それらのお金は、本来、費用として扱うことが難しいものです。いちいち会社に申告し請求することが面倒ですし、業務との関連性を厳密に説明しにくいからです。
したがって、会社の損金にしにくいものも多いのです。
しかし、出張手当として支給することで、そういう細々した費用を損金にしやすくなります。
損金として落としにくいものが、会社の業務のために支出される費用として損金に算入されます。
受取側(個人)
受け取る個人の側から見ると、日当は給与ではなく非課税所得となることから、所得税や住民税が課税されません。
所得税の最高税率は45%(住民税と合わせると55%)ですので、非課税というのは大きなメリットです。
また、個人に対する給与にならないということは、社会保険料の負担も発生しませんので、個人にとっても法人にとっても嬉しい制度です。
まとめ
出張旅費規程をきちんと定め、ルールに従って処理することで支払側と受取側どちらにも大きなメリットを生み出すことができます。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。