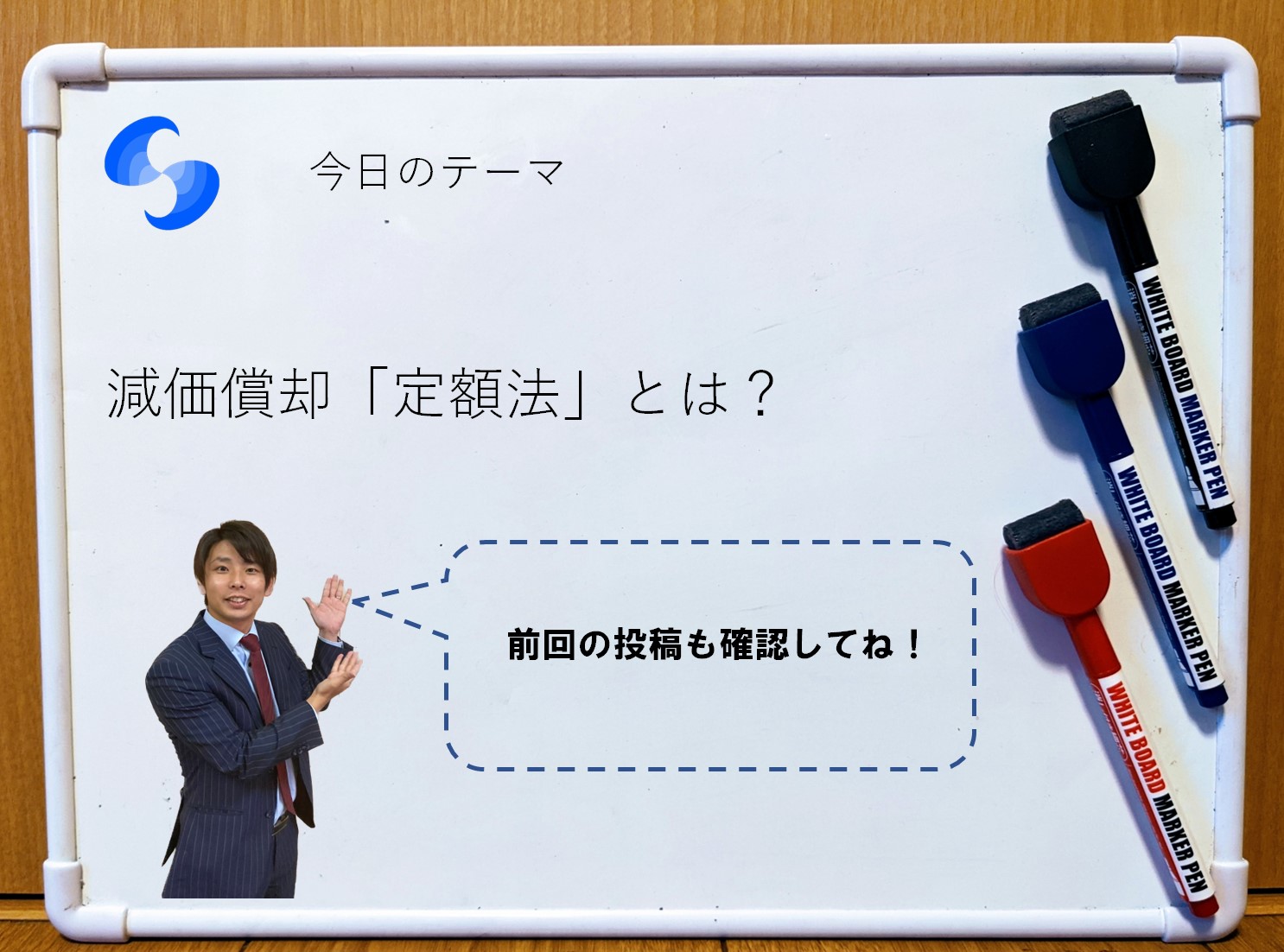減価償却「定率法」とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、「減価償却の定率法」について解説します。
減価償却とは
事業活動において必要となる、建物や建物付属設備などの固定資産は、高額で、且つ、年月が経つにつれてその価値が下がっていきます。このような固定資産のことを「減価償却資産」といいます。
減価償却資産は、使用可能期間の全期間で分割をして経費としてみていくべきです。
減価償却資産の取得にかかった経費を、各年分の経費として費用計上し、分配する手続きを「減価償却」といいます。
定率法とは
定率法とは、「耐用年数の当初に多くの減価が生じ、使用が進むにつれて減価が少なくなっていく」と仮定する減価償却の方法です。
税務署に特に届け出をしていない場合、「定率法」を採用しているとみなされます。
※対応年数とは、固定資産の一般的な使用可能期間のこと。対応年数が5年にわたり減価償却を計上していくことになります。
定率法の償却率と計算方法
定率法による減価償却費の計算式
減価償却費=未償却残高×定率法の償却率
未償却残高とは、減価償却資産を取得した金額から、減価償却した金額を差し引いた残高です。
償却が進むごとに計上できる減価償却費が減少していきます。
さらに、上記の計算の結果が「償却保証額」以下になったときは、計算方法が下記に変わります。
償却保証額以下になった場合の定率法の計算式
減価償却費=改定取得価額×改定償却率
償却保証額は、償却資産の取得価額に耐用年数ごとに定められた保証率を掛けて求めます。
また、改定償却率は、償却率と同じように耐用年数ごとに定められています。改定取得価額は「未償却残高×定率法の償却率」が初めて償却保証額を下回った年の期首未償却残高のことです。
定率法のメリット
減価償却資産を購入した初年度に大きく経費計上ができるのが定率法の計算の仕方です。
売上が良かった年に設備投資を行って経費計上し、節税メリットも大きくなります。
減価償却費にする定額法に比べ、タイミングを見計らった設備投資がしやすくなります。 また、法人は一部の種類を除けば、原則的に定率法で減価償却費の計算を行うので届出がいらないというメリットもあります。
定率法のデメリット
償却率の他に保証率が定められており、毎年の減価償却費が変わります。その影響で帳簿上の計算方法が複雑になり節税効果が 年々薄れてしまいます。
定率法が使えないものもある?
平成28年度税制改正では、一部の減価償却資産において定率法が廃止されました。
具体的には、建物付属設備および構築物、鉱業用の建物などを平成26年4月1日以降に取得した場合、建物付属設備および構築物の償却方法は「定額法」、鉱業用の建物などの償却方法は「定額法」または、「生産高比例法」のいずれかとなります。
定額法については次回の投稿で詳しく説明しますので、そちらをご覧ください。
上記の内容以外にもご不明点等ございましたら翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。